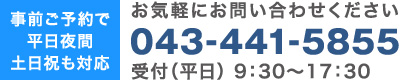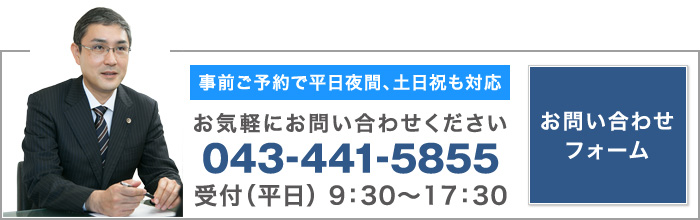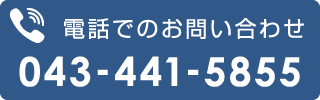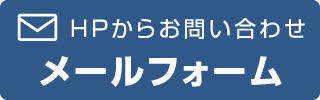遺言の方式には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類があります。
自筆証書遺言とは、文字どおり自分で手書きで作成した遺言書のことです。
公正証書遺言とは、公証人に作成してもらい、公証人役場に保管してもらう遺言書のことです。
秘密証書遺言とは、自分で作成した遺言書に封をした状態で公証人役場に持っていき、遺言書を作成したということを証明してもらう遺言書のことです。
今般相続法の改正により、平成31年1月13日から自筆証書遺言の方式が緩和されました。
これまでの自筆証書遺言は「全文」を遺言者が自書することが求められていました。
例えば、遺言書の内容をパソコンで作成し、日付と署名押印だけ自書でした場合、要式に不備があるとしてその遺言書は無効になってしまいます。
このため、相続財産の具体的な内容(例えば相続させようと思った土地建物や預貯金等の目録)も全て自分で手書きしなければなりませんでした。
しかし、全ての相続財産を手書きするというのはとても大変なことです。特に高齢者の方であれば尚更です。
そこで、改正相続法では、民法第968条第2項を追加し(従前の第2項は第3項へ)、相続財産については財産目録を作成して添付することが認められることになりました(本文、日付、氏名は自書が必要です。)。
例えば、パソコンで作成した財産目録はもちろんのこと、不動産の登記簿謄本(全部事項証明書)や預貯金通帳のコピーを添付することも可能になりました。但し、財産目録の全てのページ(両面ある場合はその両面)に遺言者が署名押印しなければなりません。
<参考条文>
民法第968条
1 自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、自筆証書にこれと一体のものとして相続財産(第997条第1項に規定する場合における同項に規定する権利を含む。)の全部又は一部の目録を添付する場合には、その目録については、自書することを要しない。この場合において、遺言者は、その目録の毎葉(自書によらない記載がその両面にある場合にあっては、その両面)に署名し、印をおさなければならない。
3 自筆証書(前項の目録を含む。)中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印をおさなければ、その効力を生じない。

千葉県・東京23区を中心に活動する秋山慎太郎総合法律事務所です。
私たちは「身近な法律事務所」として、皆様の暮らしの安心を取り戻すお手伝いをしています。
当事務所は、相続、離婚、不動産、交通事故、債務整理、労働事件、刑事事件といった個人案件から、企業間の紛争、債権回収、労務管理等の法人案件、更には分野を特定できない法律問題まで幅広く取り扱う地域密着の総合法律事務所です。
特に、生活に直結する「借金・債務整理」や、突然のトラブルである「交通事故」の分野に力を入れており、豊富な解決実績がございます。法律の専門家として、ご相談者様一人ひとりに親身に寄り添い、迅速な解決を実現することをお約束します。
【借金・交通事故のご相談は初回30分無料】
お困りの際は、一人で悩まずに専門家にご相談ください。お電話やお問い合わせフォームから、まずはお気軽にご連絡いただければ幸いです。