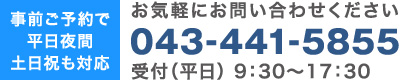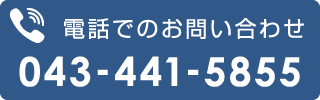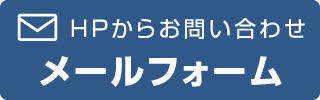Archive for the ‘千葉の弁護士コラム’ Category
【相続】遺産分割協議で注意すべき「利益相反」について
遺産分割協議を進める際には「利益相反」に注意が必要です。
特に相続人に未成年者が含まれている場合、親と子どもの利益が相反してしまうケースが少なくありません。
利益相反しているのに無理に遺産分割協議を進めると、遺産分割協議が無効になってしまいます。
この記事では遺産分割協議で注意すべき利益相反について、解説します。
1.利益相反行為とは
利益相反行為とは、一方の利益になり、他方の不利益になる行為をいいます。
たとえば会社の取締役が自分の利益のために会社の利益を犠牲にして取引する場合などが該当します。
遺産分割の場面でも利益相反行為になる場合があります。
遺産分割協議で利益相反行為があると、その行為は無効になります。
2.相続で利益相反が問題になるケースとは
相続の場面で利益相反が起こるのはどういったケースなのか、みてみましょう。
2-1.未成年者が相続人となる場合
未成年者は、単独で法律行為をできません。未成年者の法律行為は親権者が代理するのが原則です。そこで遺産分割協議の場面でも、親権者が法定代理人として参加するのが原則となっています。
ただ親権者自身が相続人になる場合、親権者と未成年者の利益が相反してしまいます。
「親権者の遺産取得分が増えると未成年者が損をする」という意味で公平な遺産分割協議を期待できないためです。
未成年者が相続放棄する場合も同じです。
未成年者を相続放棄させると親権者の取得できる遺産が増えるので、親権者の利益になります。よって親権者が相続人となる場合、親権者は未成年者に代わって相続放棄ができません(ただし親権者自身も相続放棄するなら可能です)。
2-2.成年被後見人が共同相続人の場合
似たような問題は、成年被後見人が相続人になったケースでも起こります。
成年被後見人とは、判断能力が低下して成年後見人に財産管理などを行ってもらっている人です。成年被後見人と成年後見人が両方とも相続人になる場合、成年後見人が公平に遺産分割することを期待しにくくなります。よって利益相反行為として認められません。
成年被後見人が相続放棄する場合も同様です。成年被後見人が相続放棄すると成年後見人の遺産取得分が増えるという意味で、両者の利益が相反してしまいます。
2-3.遺言言執行者がいる場合
遺言執行者がいる場合にも、利益相反行為が起こる可能性があります。
遺言執行者とは、遺言書の内容を実現する役割を果たす人です。たとえば不動産の名義変更や預貯金の払い戻しなどを行います。
たとえば相続財産を売却する場合に遺言執行者に利益相反が生じる可能性があります。
「相続財産を売却して現金を長男に相続させる」という内容の遺言がある場合、遺言執行者が相続財産の買受人になると「自己契約」として利益相反行為になってしまいます。
3.利益相反する場合の対処方法
遺産分割協議の際に相続人に未成年者や成年被後見人が含まれていて利益相反してしまう場合、相続人はどのように対処すれば良いのでしょうか?
利益相反となる場合には、未成年者や成年被後見人の「特別代理人」を選任しなければなりません。特別代理人は相続に利害関係のない人から選ばれます。特別代理人が選任されれば、特別代理人を交えて遺産分割協議ができますし、特別代理人は未成年者や成年被後見人のために相続放棄もできます。
特別代理人の選任方法
特別代理人を選任するためには、家庭裁判所へ申立てしなければなりません。相続人の中に未成年者や成年被後見人が含まれていて親権者や成年後見人も相続人となる場合には、早めに特別代理人選任の申立てをすると良いでしょう。
千葉県の秋山慎太郎総合法律事務所では遺産分割に積極的に取り組んでいます。利益相反について疑問や不安のある方は、一度お気軽にご相談ください。
【企業・顧問】就業規則を改定すべきケース
いったん就業規則を作成しても、時間が経過すると改定が必要となるケースがよくあります。古い就業規則をそのまま適用していても、効果的に社内規律を維持したりトラブル防止したりできません。
この記事では就業規則を改定すべき状況や改定方法について、弁護士が解説します。
1.就業規則を改定せず放置するデメリット
常時10人以上の従業員を雇用する事業所では、就業規則を作成して労基署へ届け出る必要があります。ただし10人未満の会社でも社内規律維持やトラブル防止のための就業規則を作成するよう推奨しています。
ではいったん作成した就業規則を長年見直さずに放置していても問題はないのでしょうか?
就業規則は定期的に見直すべきです。以下でその理由をお伝えします。
1-1.違法状態になってしまう可能性がある
労働関係法令をはじめとして、法律は頻繁に改正されます。
たとえば2022年10月には「産後パパ育休制度」とよばれる育休制度の改正法が施行されたことも記憶に新しいでしょう。
法改正が行われたら、就業規則もそれに合わせて改定しなければなりません。
放置すると、違法状態になってしまう可能性があります。
1-2.現状に合わない内容になってしまう
違法にはならなくても、就業規則を改定しないデメリットがあります。
たとえば古い就業規則をそのまま放置していると、会社の現状に合わない状況が発生してきます。それでは就業規則が形骸化してしまい、設置している意味がありません。
就業規則は常に最新のものにアップデートしておく必要があります。
2.就業規則を改定すべきタイミング
どのような状況になれば就業規則を改定すべきなのでしょうか?以下で就業規則を改定すべきタイミングをお伝えします。
2-1.法改正に対応するタイミング
1つは法改正に対応しなければならないタイミングです。
働き方改革関連法、育休関連など、最近でも多くの労働関係法令の改正が行われています。
法改正に追いつくには、就業規則の改定が必要になるケースが多いので、改正法が施行される前に就業規則をアップデートしましょう。
2-2.就業規則が形骸化している場合
就業規則が古くなって形骸化しているなら、改定すべきタイミングといえます。
就業規則は従業員に参照させて服務規律を守らせる役割も果たします。
せっかく就業規則を定めても従業員の参考にならない古い内容になっているなら、早めに現在の企業の状態に即した内容に改定しましょう。
2-3.トラブルを防止できなかった場合
せっかく就業規則があっても、効果的にトラブルを防止できなければ意味がありません。
たとえば懲戒解雇した場合などに就業規則が役に立たなかったなら、改定を検討すべき状況となっている可能性があります。
3.就業規則の改定方法
以下では就業規則を改定する手順をお知らせします。
STEP1 労働者の代表者の意見をきいて改定案を作成する
まずは過半数の労働者の代表者から意見を聞きながら改定案を作成しましょう。
労働組合がある場合、過半数が加入している労働組合の代表者が労働者の代表になります。
ただし労働者に不利益な内容に変更する場合、対象となる全労働者の合意が必要になります。
STEP2 就業規則・就業規則変更届を作成する
次に就業規則や就業規則変更届を作成しましょう。
就業規則を作成するときには、雛形を利用するとしても自社のニーズに応じたものとすべきです。
STEP3 所轄労働基準監督署へ提出する
次に所轄の労働基準監督署へ就業規則や就業規則変更届を提出します。
STEP4 労働者へ周知する
就業規則を提出したら、労働者へ周知しなければなりません。
事業所に備え付けていつでも従業員がアクセスできる状態にしたり、共有フォルダに入れて従業員がいつでも閲覧できる状態にしたりしましょう。
周知されなかった場合、就業規則には効力が認められません。周知義務違反として30万円以下の罰金刑となる可能性もあるので、違反しないように注意してください。
千葉県の秋山慎太郎総合法律事務所では労働問題に力を入れて取り組んでおります。就業規則の見直しをご検討の場合、お気軽にご相談ください。
【相続】4種類の遺産分割方法
遺産分割の方法には以下の4種類があります。
- 現物分割
- 代償分割
- 換価分割
- 共有
それぞれメリットとデメリットがあり、状況に応じて分割方法を選択する必要があります。適切な方法を選択できるよう、それぞれの特徴を把握しておきましょう。
今回は遺産分割の4種類の方法に付いて解説しますので、ぜひ参考にしてみてください。
1.現物分割
現物分割は、遺産をそのままのかたちで分割する遺産分割方法です。たとえばAの土地を長男が相続し、Bの土地を次男が相続する場合などです。土地を分筆して分けるケースも現物分割になります。
シンプルに手続きができて手間がかからないのが現物分割のメリットです。
一方で、相続人間で不公平が生じやすいデメリットがあります。またすべての土地を分筆できるわけではありません。条例などで分筆が制限されている場所もありますし、建物はそもそも分筆できません。
2.代償分割
代償分割とは、特定の相続人が遺産を取得する代わりに、他の相続人へ代償金を払って清算する方法です。
たとえば3000万円の価値のある不動産があり、長男が不動産を取得して次男と三男にそれぞれ1000万円ずつ支払って清算する場合などです。
代償分割のメリットは、比較的公平に遺産分割しやすい点です。不動産を相続できなかった相続人も代償金を受け取れるので、納得しやすいでしょう。
ただし代償金を払う相続人に資力が必要です。資力のない相続人が代償分割によって不動産を取得したくても、できません。
また不動産の「評価額」について相続人同士で合意ができず、トラブルになるケースもよくあります。
3.換価分割
換価分割は、相続人全員が合意して財産を売却し、得られた現金を分け合う遺産分割方法です。たとえば3000万円の土地を売却し、売却金を兄弟3人で1000万円ずつ分け合うケースなどです。
換価分割のメリットは、相続人間で公平に遺産を分割できる点です。評価額の問題も発生しません。売ってしまえば固定資産税もかかりませんし管理の手間も省けます。
デメリットは、高く売れるとは限らない点です。売り急ぐと損をしてしまう可能性もあるでしょう。売ろうとしても売れない資産もあります。将来の値上がり益なども逃してしまう可能性がありますし、不動産からの収益も得られなくなってしまいます。
4.共有
共有とは、遺産を相続人同士の共有名義にする方法です。共有持分割合は通常、法定相続分に従います。
共有にすると遺産の形を変えずに全員が平等に相続できるメリットがあります。
しかし共有にはたくさんのデメリットがあるので注意が必要です。
- 売却や増改築、リフォームなどを行う際に共有者全員の同意が必要になってしまう
- 固定資産税を払わない共有者がいるとトラブルになる
- 独占的に不動産を利用する相続人がいると不公平感が生じる
- 再度の遺産相続が起こると権利が細分化されて複雑になり、物件の管理や処分がより難しくなる
5.遺産分割の進め方
遺産分割を進める場合、まずは相続人調査や相続財産調査を行いましょう。その上で相続人が全員参加して遺産分割協議を行う必要があります。
遺産分割協議が整ったら、遺産分割協議書を作成しましょう。不動産の相続登記や相続税申告を行う際にも遺産分割協議書が必要となります。
遺産分割協議の際に、相続人同士の意見が合わずにもめてしまうケースも珍しくありません。その場合には家庭裁判所の遺産分割調停を利用しましょう。調停では調停委員が間に入って調整をしてくれます。
弁護士に遺産分割協議や調停などの代理を依頼することもできます。弁護士に依頼すると自分たちだけで話し合うよりスムーズに話を進められるケースが多いので、もめてしまったら早めに弁護士に依頼するのが良いでしょう。
まとめ
千葉県の秋山慎太郎総合法律事務所では遺産相続案件に力を入れて取り組んでいます。遺産分割方法についてお悩み事がありましたら、お気軽にご相談ください。
【相続】遺産分割審判とは
遺産分割について当事者同士で話し合っても解決できない場合、遺産分割審判を利用して裁判所に遺産分割方法を決めてもらう必要があります。
この記事では遺産分割審判とはどういった手続きなのか、有利に進めるためにどのように対応したら良いのかなど、弁護士が解説します。遺産分割でもめてしまった場合にはぜひ参考にしてみてください。
1.遺産分割審判とは
遺産分割審判(いさんぶんかつしんぱん)とは、裁判所が遺産分割の方法を指定する手続きです。
遺産分割協議や遺産分割調停では当事者同士が合意して遺産分割の方法を決定しますが、遺産分割審判では当事者の合意は不要です。相続人同士がもめていても、審判官(裁判官)が遺産分割の方法を決めてくれます。
また遺産分割審判で遺産分割の方法が決まる場合、基本的には「法定相続分」に応じて遺産が分割されます。協議や調停の場合のように、当事者が自分たちで好きなように遺産の配分を決めることはできません。
遺産分割審判には強制執行力があるので、相続人たちはその内容に従わねばなりません。たとえば代償分割の方法が採用されたら土地建物などの取得者は他の相続人に代償金を払わねばなりません。審判にもとづいて不動産が競売にかかるケースもあります。
遺産分割審判では必ずしも当事者の希望通りに解決できるとは限らないので、過剰に期待しないようにしましょう。希望通りの結果(審判)を獲得するには、審判手続の中で裁判官に自分の希望する遺産分割方法が妥当であることなどについて根拠を示す必要があります。
2.遺産分割審判を利用すべきケース
以下のような場合、遺産分割審判を利用すべきといえます。
- 他の相続人と遺産分割の話し合いをしても合意できない
- 他の相続人と連絡がとれない、調停にも出頭しない
遺産分割審判と遺産分割調停の関係
遺産分割事件について、法律上は調停前置主義が採用されていません。遺産分割調停を先にしなくても遺産分割審判を申し立てられます。
ただし実際に調停なしに遺産分割審判を申し立てると、裁判官がまずは遺産分割調停に付するケースが大多数です。実質的には調停を先にしないで審判をするのは難しいといえるでしょう。
一方で、調停が不成立になると当然のように手続きが審判へと移行します。あえて調停不成立後に審判の準備をして申立を行う必要はありません。
3.遺産分割審判を有利に進める方法
遺産分割審判を有利に進めるにはどのように対応すれば良いのでしょうか?以下でみてみましょう。
3-1.自分の主張の根拠となる資料を提出する
まずは裁判官に対し、自分の主張が法的に正しいことを証明しなければなりません。
さまざまな資料を提出し、自分の主張が正しいことの根拠を示しましょう。
資料なしに言いたいことだけ述べていても、主張が通る可能性は高くはありません。
3-2.法的な主張を行う
遺産分割審判では、法的に意味のある主張を行うべきです。単なる希望を述べていても、法律的に意味が通るものでないと無視されてしまいます。
たとえば理由もなく法定相続分を無視した分け方を主張しても、通らないでしょう。
何が法的に正しいかわからない場合などには、弁護士に依頼するようおすすめします。
3-3,弁護士に依頼する
遺産分割審判を有利に進めるためには、弁護士に依頼すべきと考えます。専門知識のない方が1人で対応しようとしても、難しいためです。
特に対立する相手方に弁護士がついているのにこちらに弁護士がついていないと、著しく不利になってしまう可能性があります。
弁護士を選ぶ際には、日頃から遺産相続案件に力を入れている弁護士を探して依頼しましょう。
千葉県の秋山慎太郎総合法律事務所では遺産分割調停や審判の実績も多数あります。他の相続人ともめてしまってお困りの方がおられましたら、お気軽にご相談ください。
労働訴訟とは?流れや対応ポイントについて弁護士が解説
残業代や解雇などのトラブルが発生して会社側ともめてしまった場合、「労働訴訟」によって解決できる場合があります。
労働訴訟とは、従業員と会社側のトラブルを解決するための訴訟です。
「労働訴訟」という特別の類型があるわけではありませんが、訴訟で労働問題をとりあげるので労働訴訟とよばれます。
労働訴訟を起こすときには、必要な証拠を集めて法律的に正しい主張を行い、立証活動もしなければなりません。
この記事では労働訴訟について、弁護士がわかりやすく解説します。会社相手に裁判を起こそうとしている方はぜひ参考にしてみてください。
1.労働訴訟とは
労働訴訟とは、残業代や解雇などの労働者と企業側の間のトラブルを解決するための訴訟をいいます。労働訴訟を起こすと裁判所が判決を出してくれるので、会社側とのトラブルを解決できます。労働審判と違い、訴訟自体に対する異議申し立てはできません。紛争を最終的に解決できることが労働訴訟のメリットとなります。
労働訴訟で取り扱うことができる事件
労働訴訟で取り扱うことができるのは、労働問題に関するあらゆる法的問題を含む事件です。
労働審判にように「労働者対事業者側」という構図でなくてもかまいません。
たとえばセクハラやパワハラを受けた場合、直接の加害者(上司などの個人)に対しても労働訴訟を起こせます。
よくある労働訴訟の例をみてみましょう。
- 残業代請求
- 解雇無効(不当解雇)
- 安全配慮義務違反(労災関連)
- セクハラやパワハラの損害賠償請求(会社相手、加害者個人相手の両方)
対象となる事件が制限されないのは、労働審判と比べたときの労働訴訟のメリットといえるでしょう。
2.労働訴訟の流れ
労働訴訟の大まかな流れを示します。
STEP1 証拠集め
まずは証拠を集めましょう。たとえば残業代請求であれば、タイムカードやシフト表、営業日報の写し、給与明細書などが必要となります。
STEP2 訴訟提起
証拠が揃ったら訴状を作成して訴訟を提起します。
訴訟提起後、特に不備がなければ担当係が決まって第1回期日の呼出状が届きます。
STEP3 第1回期日
第1回期日が開かれます。被告は答弁書を提出している場合、第1回期日に出席する必要はありません。
STEP4 第2回以降の期日
第2回以降の期日では、争点や証拠の整理を行っていきます。
STEP5 尋問
争点や証拠の整理が終わったら、当事者や証人の尋問が行われます。
STEP6 判決
すべての証拠調べが終わったら判決が言い渡されます。
STEP7 控訴
判決内容に不服がある場合には、控訴して争うことが可能です。控訴は判決書を受け取ってから2週間以内に手続きしなければなりません。
3.労働訴訟のポイント
労働訴訟で主張を認めてもらうには、証拠が必要です。訴訟では立証されない事実は認められないからです。事前にできるだけ多くの証拠力の高い証拠を集めましょう。
証拠の集め方がわからない場合、弁護士までご相談ください。
4.労働訴訟は1人でもできる?
労働訴訟は本人お1人でもできますが、専門知識がない方が1人で進めるのは実質的に困難です。不利になってしまい、敗訴するリスクも高まってしまうでしょう。
有利に訴訟を進めるには弁護士に依頼することをおすすめします。
5.労働訴訟を弁護士に依頼するメリット
5-1.証拠の集め方がわかる
残業代などの証拠の集め方がわからない場合でも、弁護士に相談すれば適切な証拠集めの方法がわかります。
5-2.手間がかからない
訴訟には膨大な手間がかかりますが、弁護士に任せれば大きく手間を省けます。
5-3.裁判所へほとんど行かなくて良い
基本的には弁護士のみが出廷すれば良いので、尋問の日以外はほとんど裁判所に行かずに済みます。
5-4.ストレスが軽減される
弁護士にトラブルを預けてしまえば精神的にも楽になるでしょう。
千葉県の秋山慎太郎総合法律事務所では労働トラブル解決に力を入れて取り組んでいます。お困りの際にはお気軽にご相談ください。
遺言書(公正証書遺言)作成に必要な証人とは?
公正証書遺言を作成するには証人が2名、必要です。
証人は基本的に、遺言者本人が見つけなければなりません。
この記事ではどのような人が証人になれるのか、専門家に証人を依頼する際の費用、証人が見つからないときの対処方法などをお伝えします。
公正証書遺言を作成しようと考えている方は是非参考にしてみてください。
1.公正証書遺言には証人が2人必要
公正証書遺言とは、公証人に公正証書として作成してもらう遺言書です。
自筆証書遺言よりも無効になりにくく破棄や隠匿などの危険も避けやすいメリットがあるので、多くの方に利用されています。
公正証書遺言を作成するには「証人」2人の立会が必要となります。遺言内容が本当に遺言者の意思を反映したものとなっているか、第三者の視点からチェックするのが目的です。
証人になると、後日トラブルが起こって裁判になった場合に「有効な遺言である」という証言を求められる可能性もあります。
なお秘密証書遺言の場合にも証人が必要となりますが、自筆証書遺言の場合には証人は不要です。
証人は自分で用意しなければならない
公正証書遺言を作成する際、証人は基本的に遺言者本人が用意しなければなりません。
証人には遺言書を作成する当日、公証役場に来てもらう必要があります。
2.公正証書遺言の証人になれる人となれない人
公正証書遺言を作成するとき、誰に証人を依頼すれば良いのでしょうか?
以下では証人になれる人となれない人について解説します。
2-1.証人になれる人
遺言書の証人に特別な資格はありません。
弁護士や行政書士などの専門家だけではなく、一般の個人にも証人を依頼できます。親族であっても友人知人などであってもかまいません。
ただし証人になれない欠格者に該当する場合には証人を依頼できません。
2-2.証人になれない人
欠格者となって公正証書遺言の証人になれないのは、以下のような人です。
未成年者
未成年者は遺言内容を正しく把握する能力が認められません。よって公正証書遺言の証人にはなれません。
推定相続人
将来遺産相続する予定の推定相続人にも証人を依頼できません。
受遺者
遺言によって財産を取得する受遺者にも証人を依頼できません。
推定相続人や受遺者の配偶者や直系血族
推定相続人や受遺者の配偶者や直系血族も公正証書遺言の証人になれません。
公証人の配偶者や四親等内の親族、書記、使用人
証人を要求する理由として公証人による不正を防ぐ目的もあります。
そこで公証人と関係のある親族なども遺言書の証人になれません。
3.証人の依頼先が見つからない場合の対処方法
公正証書遺言を作成しようと思っても、適切な証人候補が見つからない場合があります。その場合には、公証役場で紹介してもらいましょう。
紹介を受けると1人あたり6000~7000円程度の費用がかかります。
具体的な金額は公証役場によって異なるので、個別に問い合わせてみてください。
4.専門家に証人を依頼したときにかかる費用の目安
親戚などに適当な証人候補が見つからない場合、行政書士や司法書士、弁護士などの専門家に依頼することも可能です。
そういった場合には、1人あたり1万円程度の費用がかかると考えましょう。
ただし費用は依頼する専門家の種類や依頼先の事務所によっても異なるので、詳細は依頼先の専門家に確認してください。
5.欠格者に証人を依頼すると遺言書が無効になる
間違えて証人になれないはずの欠格者に証人を依頼してしまったら、その遺言書は無効になってしまいます。たとえば利害関係のある推定相続人の親族や未成年者に依頼してしまった場合などには公正証書遺言が無効になります。そのような事態に陥らないよう、自分で証人を用意する場合にはくれぐれも慎重に証人選びをしましょう。
千葉県の秋山慎太郎総合法律事務所では、遺産相続案件に力を入れて取り組んでいます。お気軽にご相談ください。
【相続】遺言を拒否できるケースとは
遺言書があっても必ずしもその内容どおりに遺産分割する必要はありません。
遺言書が無効になるケースもありますし、遺言書の内容を無視できる場合もあります。
この記事では遺言を拒否できるケースについて、弁護士が解説します。
遺言書の内容に納得できない方はぜひ参考にしてみてください。
1.相続人が全員合意した場合
遺言書があっても、相続人全員が納得して別の遺産分割方法を選択するならば遺言書に従う必要はありません。
相続人同士で話し合い、遺言書どおりに遺産分割しないことに決めたら遺言書で指定された以外の方法で遺産分割できます。
相続人同士の合意で遺言書の内容を拒否しても、特にペナルティや罰則はありません。
相続人全員の合意による遺産分割が難しくなる場合
ただし相続人以外の受遺者がいる場合、相続人だけが合意しても遺言書を無視できません。
受遺者の合意も必要となります。
また遺言執行者がいる場合にも、遺言書を無視した遺産分割は難しくなります。その場合、まずは遺言執行者を解任するか辞任を促さなければならないでしょう。
2.遺言書が無効になる場合
遺言書が無効になる場合にも遺言書どおりに遺産分割する必要はありません。
以下でどういった状況において遺言書が無効になるのか、みてみましょう。
2-1.自筆証書遺言の要式を満たしていない
自筆証書遺言の場合、要式を満たしていないと遺言書は無効になります。
たとえば以下のようなケースです。
全文が自筆で書かれていない
自筆証書遺言は全文を遺言者が自筆しなければなりません。一部でも自筆でない箇所があると無効になります。ただし遺産目録の部分だけは自筆する必要がありません。
日付が入っていない
遺言書には日付を入れる必要があります。日付の入っていない遺言書は無効です。
署名押印が抜けている
遺言書には遺言者の署名押印が必須です。署名押印が抜けている遺言書は無効になります。
加除訂正方法が間違っている
遺言書を訂正したり加筆したりする場合には、法律に従った方式で対応しなければなりません。加除訂正方法が間違っていると遺言書は無効になります。
2-2.遺言書作成時に意思能力を失っていた
遺言書作成当時、遺言者が意思能力を失っていると遺言書の種類を問わず無効になります。
たとえば遺言者が強度の認知症にかかっているのに周囲の親族が無理に遺言書を書かせた場合などです。
この理由で遺言書が無効になる場合、遺言書の種類を問いません。公正証書遺言でも遺言書が無効になる場合があります。
2-3.詐欺や脅迫によって書かれた遺言書
周囲の人による詐欺や脅迫行為によって無理に書かされた遺言書は無効です。
2-4.偽造や変造の遺言書
周囲の親族などが勝手に偽造したり書き換えて変造したりした遺言書も無効になります。
遺言書が無効になる場合には「遺言無効確認」の手続きをしなければなりません。
「遺言書が有効」と主張する相続人がいたら「遺言無効確認調停」や「遺言無効確認訴訟」を提起する必要があります。
3.遺留分侵害額請求できるケースも
遺言書が有効でも、兄弟姉妹以外の遺留分を侵害することはできません。
遺留分とは、兄弟姉妹以外の法定相続人に認められる最低限度の遺産取得割合です。
遺留分権利者は遺留分義務者に対し「遺留分侵害額請求」ができます。
遺留分侵害額請求をしても遺言書が無効になるわけではありませんが、遺留分に相当する金銭の支払いを受けられます。
遺言書の内容に納得できない場合には、遺留分侵害額請求の可否も確認してみてください。
まとめ
千葉県の秋山慎太郎総合法律事務所では、遺産相続のサポートに力を入れています。
遺言書の内容に納得できない場合や「遺言書が無効になるのではないか?」と考えられる場合には、お気軽にご相談ください。
遺言書作成を弁護士に相談するメリット
遺言書を作成すると、相続トラブルを予防しやすくなるなどのメリットがあります。
ただ自分1人で遺言書を作成しても、無効になってしまったり発見されなかったりするリスクが心配でしょう。
遺言書を作成するなら、弁護士に依頼するようおすすめします。
この記事では遺言書作成を弁護士に依頼するメリットをお伝えします。
これから遺言書を作成しようと考えている方はぜひ参考にしてみてください。
1.適切な遺言書の種類を選択できる
一般的によく利用されている遺言書には「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」の2種類があります。また自筆証書遺言の管理方法については、自分で保管する方法と法務局に預ける方法があります。
自分1人で遺言書を作成する場合、どの種類の遺言書を作成して良いのか悩んだり、法務局に自筆証書遺言を預けるか公正証書遺言を作成するか迷ったりする方が少なくありません。
弁護士に相談すると、状況に応じて適切な遺言書作成・保管方法を確認できます。遺言書の種類や作成方法に迷ったときには弁護士へ相談しましょう。
2.無効になりにくい
せっかく遺言書を作成しても、無効になっては意味がありません。
ところが実際には個人の方が自己判断で遺言書を作成すると、無効になってしまう事例が多々あります。
弁護士に相談しながら遺言書を作成すると、無効になるリスクを大きく低減できます。
遺言書が無効になりにくいことも弁護士に遺言書作成を依頼するメリットといえるでしょう。
3.手間がかからない
遺言書を作成するには手間がかかります。
詳しい知識がない場合には、まずはどのような方法で遺言書を作成しなければならないのか調べなければなりません。慣れない作業に手間取る方も多数おられます。
弁護士に遺言書作成を相談すれば、正しい作成方法や段取りを確認できるのでスムーズに遺言書を作成できます。
手間をかけずに適切な遺言書を作成できることも弁護士に相談するメリットといえるでしょう。
4.遺言内容について相談できる
「遺言書を作成したい」と思っても、どのような内容にすればよいのか決めかねる方が多数おられます。
法務局や公証役場では、遺言書の内容についての相談はできません。遺言書の内容は遺言者が決めなければならないのです。
弁護士であれば、相続人や相続財産の状況を聞いて遺言書の内容からアドバイスができます。遺言内容について相談しておけば、死後の相続トラブルもより効果的に避けられるでしょう。
内容面でのアドバイスを受けられることも、弁護士に相談する大きなメリットの1つです。
5.遺言執行者になってもらえる
遺言書を作成するときには、遺言執行者をつけておくとより安心感が高まります。
遺言執行者とは、遺言内容を実現する人です。たとえば不動産の相続登記や預貯金の払い戻しなどの作業を行います。
ただ相続人から遺言執行者を選ぶと、他の相続人が反発して手続きがスムーズに進みにくくなるケースが少なくありません。
弁護士に遺言書作成を依頼した場合、弁護士が遺言執行者に就任するケースが多数あります。弁護士が遺言執行者になっていれば、相続人らも納得しやすくなりますし、手続自体もスムーズに進みやすくなるでしょう。
6.トラブルが起こっても対応しやすい
弁護士に遺言書作成を依頼していたら、いざトラブルが起こっても解決しやすくなります。
弁護士は紛争解決のプロなので、当事者の代理人などの立場で効果的に対応できるからです。
千葉県の秋山真太郎総合法律事務所では遺言書作成などの相続関係のサポートに力を入れて取り組んでいます。
遺言書の内容が決まっていない段階でもご相談に乗ることが可能ですし、遺言執行者への就任も受け付けています。遺言書を作成しようとする方は、ぜひともお気軽にご相談ください。
労働審判とは?流れや弁護士に依頼するメリットを解説
労働者の方が雇用先の企業とトラブルになったとき、労働審判を利用するとスムーズに解決できるケースがよくあります。
労働審判は裁判とは異なり「話し合い」をメインとして進められる手続きで、裁判より迅速に終了するメリットもあります。
今回は労働審判の概要や流れ、弁護士に依頼するメリットについて解説します。残業代や解雇トラブルなどに巻き込まれた方はぜひ参考にしてみてください。
1.労働審判とは
労働審判とは、残業代不払いや解雇トラブルなど、労働者と雇用者との間の労働紛争を解決するための裁判所の手続きです。
訴訟よりも迅速に問題を解決できて、原則3回までとして審理を終了します。
当初は話し合いによる解決を目指しますが、最終的に当事者が合意できない場合には「審判」によって裁判所が一定の結論を下します。
ただし当事者が審判に対して異議を申し立てた場合、審判は確定せずに訴訟へと移行します。
労働審判にかかる期間はおおむね2~3か月です。裁判所によると、平成18年から令和3年までに終了した労働審判事件の平均審理期間は80.6日で、全体のうち67.6%が申立てから3か月以内に終了しています。
労働訴訟となると1年やそれ以上かかるケースもあるので、迅速に解決できる労働審判は労働者、企業側双方にとってメリットがあるといえるでしょう。
また労働審判は、訴訟とは異なり「非公開」ですので、他人に傍聴されて知られることもありません。
2.労働審判で扱える事件
労働審判で扱えるのは、「労働者と雇用主との間での労働トラブル」に限られます。すべての労働問題を扱えるわけではありません。
よく利用されるのは、以下のような場合です。
- 残業代に関するトラブル
- 賞与や退職金不払いに関するトラブル
- 不当解雇に関するトラブル
- 企業側の安全配慮義務違反に関するトラブル
一方、以下のような場合、労働者対雇用者の問題ではないので労働審判は利用できません。
- 上司からパワハラやセクハラなどの被害を受け、上司に対して損害賠償請求を行う
この場合、上司は雇用者ではないので「労働者対雇用者」という構図になりません。よって労働審判は利用できないのです。
なお同じセクハラやパワハラのケースでも、会社による職場環境配慮義務違反を問う場合であれば労働審判を利用できます。
3.労働審判の流れ
STEP1 証拠を集める
まずは申立を行う側が証拠を集めましょう。たとえば残業代請求なら、雇用契約書や給与明細書、タイムカードやシフト表の写しなどが必要となります。
STEP2 申立を行う
証拠が揃ったら申立書を作成し、申立を行いましょう。
裁判所の管轄は以下の3つのうちいずれかとなります。
- 相手方の住所や居所、営業所などを管轄する地方裁判所
- 現在の就業場所あるいは最後に就業した場所を管轄する地方裁判所
- 当事者間の合意によって定めた地方裁判所
STEP3 企業側から答弁書が提出される
申立後、通常は企業側から答弁書が提出されます。
STEP4 第1回期日
第1回期日では企業側との話し合いを進めます。間に労働審判委員が介入するので、当事者同士で話し合うよりはスムーズに進むケースが多数です。1回目で調停が成立すれば1回で手続きが終了します。
STEP5 第2回期日、第3回期日
継続して話し合いを行います。両者で合意ができれば調停が成立します。
STEP6 審判
3回の期日においても合意できない場合には、裁判所が審判によって結論を出します。
STEP7 異議申立て
当事者が審判内容に納得できない場合、異議申し立てが可能です。異議申し立ては、審判書を受け取ってから2週間以内に行う必要があります。
4.労働審判を弁護士に依頼するメリット
労働審判は自分でもできますが、主張を認めてもらうには的確な証拠を集めて法律的な主張を行わねばなりません。
専門知識のない方が1人で取り組むと不利になりやすいでしょう。
弁護士に依頼すると専門家である弁護士が証拠や主張をまとめるので、手間が省けるだけではなく有利に進めやすくなるものです。精神的負担も軽減されるでしょう。
千葉県の秋山慎太郎総合法律事務所では労働者の法的サポートにも力を入れて取り組んでいます。会社とトラブルになってお悩みの方がおられましたら、お気軽にご相談ください。
【借金】奨学金を返せないときの対処方法
奨学金を返済できずに放置していると、日本学生支援機構などの債権者から訴訟を起こされる可能性もあります。
返せないときには放置せず、減額返還制度などを使って適切に対応しましょう。
今回は奨学金を返せないときの対処方法を解説します。
1.奨学金を返せないとどうなるのか
奨学金を返せないで放置していると何が起こるのか、みてみましょう。
STEP1 請求される
まずは借入先である日本学生支援機構から督促が来ます。
郵便による督促が行われるケースが多数です。
STEP2 信用情報に事故情報が登録される
次に個人信用情報に事故情報が登録されて、いわゆる「ブラックリスト状態」になります。
いったんブラックリスト状態になると、ローンやクレジットカードを利用できません。
今使っているクレジットカードもいずれ解約されてしまいます。
ブラックリスト状態になるのは、奨学金の滞納後約3か月後となるのが標準的です。
STEP3 訴訟を起こされる
奨学金を長期にわたって払わずに放置しておくと、日本学生支援機構から訴訟を起こされる可能性もあります。
STEP4差し押さえを受ける
訴訟で判決が出たら、日本学生支援機構から給料や預金などの差し押さえを受ける可能性があります。差し押さえは奨学金を完済するまで止まりません。
2.奨学金を返せないときの対処方法
奨学金を返せないなら、以下のような方法で対処しましょう。
2-1.減額返還制度
まずは減額返還制度の利用を検討するようおすすめします。
減額返還制度とは、一定期間、奨学金の返還額を減額してもらえる措置です。
認められれば毎月の返済額が2分の1または3分の1になるので、有効な対処方法となるでしょう。
減額返還できる期間は最長15年です。ただし1年ごとに願い出る必要があります。
また減額返還とはいっても償還総額が減額されるわけではありません。単に返還期間が延びるだけなので、間違えないようにしましょう。
天災に遭った場合や低所得の場合などに減額返還制度を申請できます。
なおすでに奨学金を滞納していると減額返還制度は利用できません。
2-2.返還期限猶予制度
返還期限猶予制度とは、一定期間、奨学金の支払いを延ばしてもらえる制度です。
猶予してもらえる期間は最長10年です。
返還期限猶予制度の場合にも単に返還期限が延びるだけであり、利息を含めた総支払額が減額されるわけではありません。
滞納していても返還期限猶予制度を利用できることもあります。
2-3.免除制度
ご本人が死亡した場合や重度障害者となった場合には、免除制度を利用して奨学金の残金を免除してもらえることもあります。
3.どうしても返せないときには債務整理をする
奨学金の減額返還制度などを利用してもどうしても支払いが難しい方もいるでしょう。
その場合には債務整理を検討するようおすすめします。
3-1.個人再生
個人再生をすると、奨学金の債務を含めたほとんどすべての負債を減額してもらえます。
たとえば奨学金以外にカードローンなどの借り入れがある場合にも、個人再生をしたらまとめて減額してもらえます。
住宅ローン返済中の方の場合「住宅ローン特則」を利用すれば、住宅ローンの支払いは継続して家を守ることも可能です。
- 継続的な収入がある
- 家を失いたくない
- 財産を失いたくない
- 自己破産はしたくない
こういった状況の方は個人再生を検討すると良いでしょう。
3-2.自己破産
自己破産とは、裁判所へ申立をしてほとんどすべての負債を免除してもらう手続きです。
奨学金も全額免除してもらえるので、支払いの必要はなくなります。
ただし自己破産をすると、生活に必要な最低限を超える資産が失われます。
以下のような状況なら自己破産を検討しましょう。
- 収入がない
- 守りたい資産はない
- 奨学金の額が大きすぎて個人再生で減額されても払えない
なお個人再生や自己破産をすると、連帯保証人に一括請求されます。親族に連帯保証人になってもらっている場合、事前に相談しておくと良いでしょう。
奨学金の返済が難しい場合、ひとりで抱え込まずに専門家へご相談ください。
« Older Entries