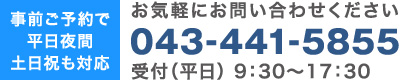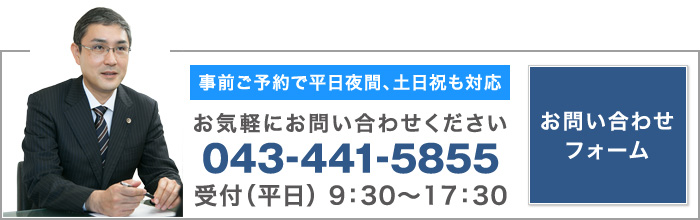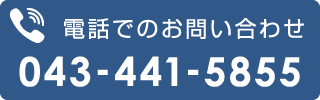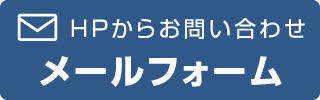遺産相続の際に大きな意味を持つ遺言書。そこに名前があれば、本来は相続権のない内縁の妻や夫でも、遺産を受け取ることができるようになります。
では、もしも相続人の立場にありながら遺言書に自分の名前がなかったら、その人は相続を諦めなければならないのでしょうか。
遺言書に名前がない、という問題は遺産相続においてよく発生します。
ここでは、遺言書に自分の名前がない場合における相続人の権利についてご紹介します。
相続人には遺留分がある!
遺言書に自分の名前がなかった場合でも、被相続人の兄弟姉妹以外の相続人(配偶者、子、親)であれば、法律で定められた最低限の遺産を受け取る権利があります。それを遺留分と呼びます。
本来、被相続人には自分の財産を自由に処分する権利があります。被相続人が特定の相続人に全財産を相続させたり、第三者に全財産を贈与したり遺贈したりすることは、被相続人の自由であり、相続人が口を挟むことではありません。しかし、これによって相続人の相続分に対する正当な期待が裏切られ、相続人の生活が脅かされるような事態になることは、決して好ましいことではありません。
そこで、被相続人の自由な財産処分と相続人の保護との調和の観点から、遺言でも侵し得ない、相続人の最低限の取得分の確保を目的として定められたのが遺留分という制度です。
相続人は、遺言書に自分の名前がなかったとしても、遺留分侵害額請求権を行使して、法律で定められた割合の遺産を取得することができるのです。
遺留分の割合
遺留分の割合については民法1028条で以下のように定められています。
① 直系尊属のみが相続人である場合 被相続人の財産の3分の1
② 前号に掲げる場合以外の場合 被相続人の財産の2分の1
被相続人の父母や祖父母などの直系尊属のみが相続人の場合(被相続人に配偶者や子どもがいない場合)は①に該当し、遺留分割合は3分の1。相続人が配偶者や子どもの場合は②に該当し、遺留分割合は2分の1になります。例えば、相続人が妻と子ども3人の場合には、妻の遺留分割合は4分の1、子どもの遺留分割合は各12分の1となります。
遺留分侵害額請求の方法
では、遺留分はどのようにして請求するのでしょうか。
遺留分は、受遺者および受贈者に対して遺留分侵害額請求の意思表示をします。遺留分侵害額請求は、口頭でも書面でもおこなうことができますが、請求したことを証拠に残しておくために内容証明郵便で通知した方が良いでしょう。なぜなら、遺留分侵害額請求権には消滅時効があるからです。民法1042条は「減殺の請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知った時から1年間行使しないときは、時効によって消滅する。」と定めています。以後は、遺留分を請求することができなくなってしまうのです。
遺留分侵害額請求の意思表示は、できるだけ早めに内容証明郵便で通知するようにしましょう。
以上のように、相続人には遺留分が認められており、遺言書に名前がなかった場合でも、相続財産に対して最低限の割合は確保することができます。
遺言書に自分の名前がなかったと言う方も、ここで紹介したことを参考に、落ち着いて対処するようにしてください。

千葉県・東京23区を中心に活動する秋山慎太郎総合法律事務所です。
私たちは「身近な法律事務所」として、皆様の暮らしの安心を取り戻すお手伝いをしています。
当事務所は、相続、離婚、不動産、交通事故、債務整理、労働事件、刑事事件といった個人案件から、企業間の紛争、債権回収、労務管理等の法人案件、更には分野を特定できない法律問題まで幅広く取り扱う地域密着の総合法律事務所です。
特に、生活に直結する「借金・債務整理」や、突然のトラブルである「交通事故」の分野に力を入れており、豊富な解決実績がございます。法律の専門家として、ご相談者様一人ひとりに親身に寄り添い、迅速な解決を実現することをお約束します。
【借金・交通事故のご相談は初回30分無料】
お困りの際は、一人で悩まずに専門家にご相談ください。お電話やお問い合わせフォームから、まずはお気軽にご連絡いただければ幸いです。