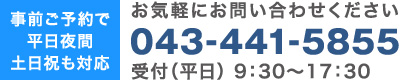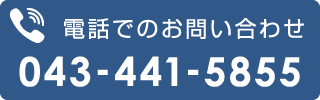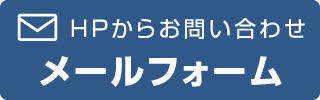Archive for the ‘千葉の弁護士コラム’ Category
【企業・顧問】退職勧奨とは?メリットとデメリットを解説
「退職させたい従業員がいるけれど、法律上の解雇理由があるかどうかわからない」
そんなときには「退職勧奨」が役立ちます。
退職勧奨により従業員が自主的に退職すれば、基本的に「不当解雇」にはなりません。
今回は退職勧奨とはどういった手続きなのか、企業にとってのメリットとデメリットや退職勧奨をお勧めする状況など、お伝えします。
1.退職勧奨とは
退職勧奨とは、企業側が従業員に対し、自主的な退職を促すことです。
対象の従業員に「退職してはどうか?」と告げて説得し、本人が納得して自ら退職届を提出することによって退職を実現します。
退職勧奨以外の方法で従業員を辞めさせるには「解雇」しなければなりません。
しかし解雇が有効になるには「客観的合理的理由」や「社会的相当性」といった厳格な要件を満たす必要があります。現実には、企業側が辞めさせたくても退職理由が認められないケースも少なくありません。退職勧奨の場合、解雇と異なり、法律上の解雇理由がなくても退職させることができます。
辞めさせたい従業員がいる場合、いきなり解雇するより退職勧奨を行う方が安全といえるでしょう。
2.退職勧奨のメリットとデメリット
メリット
法律上の解雇理由がなくても解雇できる
従業員を解雇するには「解雇の客観的合理性」と「社会的相当性」の厳格な要件を満たさねばなりません。満たさなければ解雇は無効になってしまいます。
たとえば「他の社員より成績が悪い」「遅刻や早退が目立つ」といった程度であれば、解雇が認められない可能性が高くなります。
退職勧奨であれば、厳密な解雇の要件を満たす必要はありません。勤務態度が悪い、成績が振るわないなどの理由であっても従業員が納得さえすれば、退職させることができます。
不当解雇と主張されるおそれが低い
従業員を解雇すると、後に「解雇理由がなかった」「不当解雇」と主張される可能性があります。「従業員としての地位確認」や「未払い賃金」「慰謝料」などを請求され、最終的には訴訟に発展してしまうケースも少なくありません。
退職勧奨であれば、従業員は納得して自主的に辞めるので「不当解雇」にはなりません。
後に法的トラブルとなるリスクを大きく軽減できるメリットがあります。
デメリット
手間がかかる
退職勧奨には手間がかかります。
どういった方法で退職を勧めるか事前に検討しなければならず、従業員を説得する必要もあります。従業員がすぐには納得しない場合、粘り強く説得しなければなりません。
退職金の上乗せが必要なケースもある
従業員に自主退職を受け入れさせるには、説得だけでは足りず「退職金の上乗せ」が必要となるケースもよくあります。
解雇であれば退職金を上乗せする必要はありません。
退職勧奨をすると経済的にデメリットが生じる可能性があります。
従業員が受け入れるとは限らない
退職勧奨をしても従業員が必ず受け入れるとは限りません。強要はできないので、断られると退職勧奨には失敗してしまいます。
3.退職勧奨でよくある理由、検討すべき状況
以下のような従業員を辞めさせたいなら、退職勧奨を検討してみてください。
勤務態度が悪い
遅刻や早退、欠勤を繰り返すなど、勤務態度が悪い従業員に対しては、退職勧奨が有効です。
周囲とトラブルを起こす
協調性に欠け、同僚や上司、部下、他の部署の従業員など周囲とのトラブルを起こす人、パワハラやセクハラ行為をする人などへ退職勧奨するケースもよくあります。
能力不足
成績があまりに悪い、飲み込みが悪い、いくら指摘してもミスが続く、顧客から苦情が来ているなど、能力があまりに劣る従業員についても退職勧奨が有効です。
経営上の理由
経営が苦しくなって人員削減するとき、いわゆる「リストラ」として退職勧奨を行うケースもあります。
退職勧奨を行う際には退職を強要してはなりません。強要すると「退職が無効」と判断される可能性があり、正しい方法で進める必要があります。辞めさせたい従業員がいるときには弁護士がお力になりますので、お気軽にご相談ください。

千葉県・東京23区を中心に活動する秋山慎太郎総合法律事務所です。
私たちは「身近な法律事務所」として、皆様の暮らしの安心を取り戻すお手伝いをしています。
当事務所は、相続、離婚、不動産、交通事故、債務整理、労働事件、刑事事件といった個人案件から、企業間の紛争、債権回収、労務管理等の法人案件、更には分野を特定できない法律問題まで幅広く取り扱う地域密着の総合法律事務所です。
特に、生活に直結する「借金・債務整理」や、突然のトラブルである「交通事故」の分野に力を入れており、豊富な解決実績がございます。法律の専門家として、ご相談者様一人ひとりに親身に寄り添い、迅速な解決を実現することをお約束します。
【借金・交通事故のご相談は初回30分無料】
お困りの際は、一人で悩まずに専門家にご相談ください。お電話やお問い合わせフォームから、まずはお気軽にご連絡いただければ幸いです。
【企業・顧問】残業代請求されたときの対処方法
従業員が残業代請求をしてきても、必ずしも全額の支払いに応じる必要はありません。
まずは弁護士に相談し、本当に支払い義務があるのか、いくら払うべきなのか確かめましょう。
今回は従業員から残業代請求されたときの対処方法をお伝えします。
残業代請求を無視するリスク
残業代が発生しているにもかかわらず支払わないと、企業側には多大なリスクが発生します。以下のような金額が加算されて、支払うべき額が上がってしまう可能性があるのです。
遅延損害金
未払い残業代には遅延損害金が加算されます。
従業員の在職中は年3%ですが、退職すると年14.6%に上がります。
放置していると遅延損害金がどんどん膨らんでしまうリスクがあります。
付加金
残業代請求を無視すると、従業員は残業代請求訴訟を起こす可能性があります。
判決で支払い命令が出るときには、裁判所が「付加金」というペナルティの金額を加算することができます。付加金は「残業代と同等の金額」なので、元本と付加金を合計すると「2倍」の残業代を支払わねばなりません。
従業員からの残業代請求を放置していると過大な支払いが必要になってしまうおそれがあるので、無視してはなりません。
従業員側の残業代計算が正しいとは限らない
従業員から送られてきた請求書に書かれている金額を、鵜呑みにする必要はありません。
従業員側の計算は間違っているケースも多々あります。従業員側に弁護士がついているからといって、正しいとは限りません。
自社に残っている資料と従業員側が送ってきた残業代の明細書を照らし合わせて、本当に払うべき金額といえるのか検討してみるべきです。
残業代を払わなくてよいケース
以下のような場合、残業代を払う必要はありません。
時効が成立している
残業代請求権には時効があります。
2020年3月までに発生した残業代は2年、4月以降に発生した残業代は3年で時効消滅します。従業員の主張する残業時期が古ければ、支払いを拒絶できる可能性があります。
管理監督者である
請求者が労働基準法上の管理監督者に該当する場合、残業代を支払う必要はありません。管理監督者とは経営者側と一体的な立場にあり企業内で相当の権限や報酬が与えられている人です。
管理監督者かどうかは実質的に判断されます。単に「課長」や「マネージャー」という名目を与えているだけでは管理監督者と認められない可能性があるので、自己判断は禁物です。
残業を禁止していた
残業を禁止していたにもかかわらず従業員が違反して残業を行ったら、残業代支払いを拒絶できる可能性があります。ただし従業員が残業していることを知りながら黙認していた場合などには支払い義務が発生するので、判断に困ったときには弁護士へ相談しましょう。
残業代をすでに支払い済みである
固定残業代制度を採用していて予定された範囲内の残業時間であれば、別途残業代を支払う必要はありません。
ただし固定残業制を導入していても、予定された時間を超過した場合には支払う必要があります。
裁量労働制が適用される
裁量労働制が適用されて適正に運営できている状態であれば、個別の残業代請求に応じる必要はありません。ただし深夜労働や休日労働をした場合には割増賃金を支払わねばなりません。
事業場外のみなし労働時間制が適用される
営業担当などで外回りが多く、「事業場外のみなし労働時間制」が適用される労働者の場合にも、個別の残業代は発生しません。ただし深夜労働や休日労働については割増賃金を払う必要があります。
交渉によって減額できることも
従業員側の計算が正しく残業代を払わねばならない状況でも、交渉によって減額できる可能性があります。
弁護士が代理人となって交渉すると、企業側の反論材料をあますところなく主張できて、有利な条件で解決できる可能性が高くなるものです。対応のための労力も削減できてコストカットできるメリットもあるでしょう。
残業代請求されてお困りの方がおられましたらお気軽に弁護士までご相談ください。

千葉県・東京23区を中心に活動する秋山慎太郎総合法律事務所です。
私たちは「身近な法律事務所」として、皆様の暮らしの安心を取り戻すお手伝いをしています。
当事務所は、相続、離婚、不動産、交通事故、債務整理、労働事件、刑事事件といった個人案件から、企業間の紛争、債権回収、労務管理等の法人案件、更には分野を特定できない法律問題まで幅広く取り扱う地域密着の総合法律事務所です。
特に、生活に直結する「借金・債務整理」や、突然のトラブルである「交通事故」の分野に力を入れており、豊富な解決実績がございます。法律の専門家として、ご相談者様一人ひとりに親身に寄り添い、迅速な解決を実現することをお約束します。
【借金・交通事故のご相談は初回30分無料】
お困りの際は、一人で悩まずに専門家にご相談ください。お電話やお問い合わせフォームから、まずはお気軽にご連絡いただければ幸いです。
【相続】遺産の使い込みトラブルを弁護士に相談するメリット
他の相続人が預金などの遺産を使い込んでトラブルになったら、できるだけ早めに弁護士に相談しましょう。
自分で対応するよりスムーズかつ有利な条件で解決できる可能性が高くなります。
今回は使い込み問題を弁護士に相談するメリットをお伝えします。
1.有効な証拠集めができる
使い込みトラブルが起こったら、相手から遺産を取り戻さねばなりません。
そのためにはさまざまな「証拠」となる資料が必要です。
ところが素人ではどのような証拠をどうやって集めたらよいか、わからないケースが多いでしょう。
弁護士に相談したら訴訟になっても有効となる証拠の種類や集め方を確認できますし、証拠収集の依頼もできます。
有効な証拠集めができるメリットがあるといえます。
2.相手との交渉を任せられる
遺産を使い込まれた場合、相手に請求をして取り戻すための交渉を進めなければなりません。
ただ交渉のためには法的な知識が必要ですし証拠も集めなければなりません。本やネットで情報収集をしなければならないでしょうし、相手と連絡をとる手間もかかります。
また親族同士で遺産問題について話し合うと、どうしても感情的になりトラブルが拡大してしまいがちな問題もあります。
弁護士に使い込み金の取り戻しを依頼したら、弁護士が全面的に話し合いに対応します。
依頼者の方にご負担をおかけすることはありません。貴重な労力や時間を節約できることも大きなメリットとなるでしょう。
3.相手の態度が変わるケースが多い
当事者が自分で相手に使い込み金の返還を要求しても、真摯に対応してもらえないケースが多々あります。無視されるケースも多いですし「使い込みをしていない」と否定される事例も少なくありません。
弁護士を代理人に立てれば、相手の態度が変わる可能性があります。
これまで無視されていた場合や「使い込んでいない」と否定されていた場合でも、弁護士が法的根拠をもって返還を要求すれば話合いに応じさせることができて、遺産を取り戻せるケースがよくあります。
4.有利な条件で解決しやすくなる
自分で相手と交渉しても、期待していた通りに遺産を取り戻せるとは限りません。
相手との関係性なども影響して「これだけしか返還しない」といわれ、少額の返還で納得せざるを得ないケースもあります。
弁護士に交渉を任せれば、法的な根拠をもって相手に請求するので正当な金額の取り戻しが可能となります。
自分で交渉するよりも有利な条件で解決できる可能性があることも弁護士に依頼するメリットです。
5.ストレスがかからない
使い込まれた遺産を取り戻すため、相手と交渉するのは大変なストレスとなるものです。
返答や反論があるたびに怒りや焦りを感じて不眠などの症状が出てしまう方も少なくありません。
弁護士に対応を依頼すると、相手とのやり取りはすべて弁護士が進めます。自分で直接トラブルの相手と話す必要がなくなり、ストレスが大きく軽減されるメリットも得られるでしょう。
6.訴訟になっても安心して任せられる
使い込みトラブルが発生してどうしても話し合いでは解決できない場合、最終的には「訴訟(裁判)」を起こさねばなりません。ただ、素人の方が自力で訴訟を進めるのは困難です。
訴訟を避けるため、相手の提示した不利な条件で妥協してしまう方も少なくありません。
弁護士に交渉を任せていれば、交渉が決裂しても引き続いて訴訟を任せられます。
訴訟を避ける必要がないので最後まで強気で交渉できますし、万一訴訟が必要になっても適切に対応して使い込み金を取り戻しやすくなります。
7.相続に強い弁護士へ相談を
使い込みトラブルを有利な条件で解決するには、遺産相続に詳しく親身になって対応してくれる弁護士に依頼する必要があります。
当事務所は千葉県エリアを中心として、これまで多数の相続トラブルを解決してきました。使い込みトラブルでお困りの方がおられましたら、お気軽にご相談ください。

千葉県・東京23区を中心に活動する秋山慎太郎総合法律事務所です。
私たちは「身近な法律事務所」として、皆様の暮らしの安心を取り戻すお手伝いをしています。
当事務所は、相続、離婚、不動産、交通事故、債務整理、労働事件、刑事事件といった個人案件から、企業間の紛争、債権回収、労務管理等の法人案件、更には分野を特定できない法律問題まで幅広く取り扱う地域密着の総合法律事務所です。
特に、生活に直結する「借金・債務整理」や、突然のトラブルである「交通事故」の分野に力を入れており、豊富な解決実績がございます。法律の専門家として、ご相談者様一人ひとりに親身に寄り添い、迅速な解決を実現することをお約束します。
【借金・交通事故のご相談は初回30分無料】
お困りの際は、一人で悩まずに専門家にご相談ください。お電話やお問い合わせフォームから、まずはお気軽にご連絡いただければ幸いです。
【相続】自筆証書遺言を法務局に預ける制度について
2020年7月10日から、自筆証書遺言を法務局で保管してもらえる制度が開始されました。
この制度を利用すると、自筆証書遺言を自分で保管する必要がなく、紛失や破棄などのリスクもなくなります。
メリットも多い制度ですが、利用の際には費用もかかり注意点もあります。
今回は自筆証書遺言の法務局における保管制度について弁護士がわかりやすくお伝えしますので、ぜひ参考にしてみてください。
1.自筆証書遺言の保管制度とは
自筆証書遺言の法務局における保管制度とは、遺言者が作成した自筆証書遺言を管轄の法務局で預かってもらえる制度です。
これまで、自筆証書遺言を作成したら遺言者が自分で管理しなければなりませんでした。
すると、死亡時までに紛失してしまったり、死亡後に発見されなかったり、あるいは発見した相続人が破棄、隠匿したり書き換えてしまったりするリスクがあります。
そこで今回自筆証書遺言を法務局に預けられる制度を作り、遺言者が自分で管理しなくてよいようになりました。
なおすべての自筆証書遺言を法務局に預けなければならないわけではなく、自分で管理してもかまいません。その場合には従来通りの取り扱いになります。
2.自筆証書遺言を法務局に預けるメリット
自筆証書遺言を法務局に預けると、以下のようなメリットがあります。
2-1.紛失、破棄隠匿のリスクがない
自筆証書遺言を自分で管理していると、なくしてしまう可能性があります。
発見した相続人が中身を見て捨ててしまったり、隠してしまったりするリスクもあるでしょう。
法務局に預ければ、紛失のリスクはありませんし相続人が破棄隠匿することもできません。
遺言者の遺志を実現しやすくなるメリットがあります。
2-2.検認が不要
遺言者が自分で自筆証書遺言を管理していた場合、死後に相続人は家庭裁判所で「検認」をうけなければなりません。検認を受けない遺言書では相続登記や預貯金払い戻しなどの相続手続きを進められません。
一方、自筆証書遺言が法務局に預けられていた場合、検認は不要です。相続人に手間をかけずに済む点もメリットといえるでしょう。
2-3.相続人へ通知できるので発見されないリスクを低下させられる
自筆証書遺言を自分で保管していると、相続人が発見してくれない可能性もあります。
そうなったらせっかく遺言書を作成しても意味がありません。
法務局に預けた場合、死後に相続人へ通知するサービスを利用できます。
通知を受ければほぼ確実に遺言書が発見され、遺志を実現しやすくなるメリットがあります。
3.自筆証書遺言を法務局に預ける際の費用と注意点
3-1.費用
自筆証書遺言を法務局に預ける際には1通について3900円かかります。公正証書遺言の場合には数万円単位の費用がかかるのが一般的ですから、法務局における保管制度の方が随分低額といえるでしょう。遺言書の閲覧請求をする場合、モニター越しであれば1回1400円、原本確認は1回1700円かかります。
預けた遺言書を撤回したり内容変更の届出をしたりする際には、費用はかかりません。
3-2.注意点
法務局に自筆証書遺言を預ける場合、内容の審査は受けられません。不備があれば無効になってしまう可能性があります。内容について不安があるなら弁護士へ相談しましょう。
また法務局での保管制度を利用するには「遺言者本人」が管轄の法務局へ遺言書を持参しなければなりません。その際、運転免許証などの「写真付きの本人確認書類」が必要です。
代理人による申請はできません。ご本人が法務局に行けない状態であれば、公正証書遺言を利用する必要があります。
遺言書を作成するとき、自筆証書遺言を法務局に預けるべきか公正証書遺言を利用すべきかについては、ケースバイケースで判断する必要があります。迷ったときには弁護士へご相談ください。

千葉県・東京23区を中心に活動する秋山慎太郎総合法律事務所です。
私たちは「身近な法律事務所」として、皆様の暮らしの安心を取り戻すお手伝いをしています。
当事務所は、相続、離婚、不動産、交通事故、債務整理、労働事件、刑事事件といった個人案件から、企業間の紛争、債権回収、労務管理等の法人案件、更には分野を特定できない法律問題まで幅広く取り扱う地域密着の総合法律事務所です。
特に、生活に直結する「借金・債務整理」や、突然のトラブルである「交通事故」の分野に力を入れており、豊富な解決実績がございます。法律の専門家として、ご相談者様一人ひとりに親身に寄り添い、迅速な解決を実現することをお約束します。
【借金・交通事故のご相談は初回30分無料】
お困りの際は、一人で悩まずに専門家にご相談ください。お電話やお問い合わせフォームから、まずはお気軽にご連絡いただければ幸いです。
【相続】遺言執行者をつけるメリット
遺言書を作成するときには「遺言執行者」をつけておくようお勧めします。
遺言執行者がいなければ、せっかく遺言書を作成しても遺言どおりに相続や遺贈の手続きが行われないリスクが高まります。
今回は遺言執行者とは何か、選任するとどういったメリットがあるのか、選任方法もふまえて弁護士が解説します。
1.遺言執行者とは
遺言執行者とは「遺言で指定された内容を具体化する」任務を負う人です。
以下のようなことを行う権限があります。
- 相続財産の管理
- 遺産分割
- 不動産の名義変更や預貯金払い戻しなどの相続手続き
- 遺贈
- 寄付
- 子どもの認知
- 相続人の廃除
- 生命保険の受取人変更
遺言執行者を指定しておけば、相続人たちが自分で名義変更や寄付などの手続きを行う必要がありません。遺贈もスムーズに行われます。
遺言執行者にしかできないこと
以下の手続きは遺言執行者にしかできません。遺言で指定するなら必ず遺言執行者を選任しましょう。
- 子どもの認知
- 相続人の廃除や取り消し
2.遺言執行者をつけるメリット
遺言書を作成するとき、遺言執行者の選任は必須ではありません。
選任しておくとどういったメリットがあるのかみてみましょう。
2-1.遺言内容をより確実に実現できる
遺言書によって相続方法や遺産分割方法を指定したり遺贈を定めたりしても、相続人や受遺者が指示されたとおりに行動するとは限りません。手続きが面倒で放置される可能性もありますし、相続人間で対立が起こりトラブルになってしまうケースもよくあります。
遺言執行者を定めておけば、相続開始後速やかに遺言執行者が相続や遺贈などの手続きを行うので、スムーズかつ確実に遺言内容を実現しやすくなります。
2-2.相続人や受遺者に手間をかけさせない
相続や遺贈、寄付などを遺言書で指定すると、相続人や受遺者が自分で手続きをしなければなりません。
相続人らが子育てや仕事などで忙しくしている場合、負担をかけてしまうでしょう。
遺言執行者を指定しておけば必要な手続きは遺言執行者が行うので相続人や受遺者に手間をかけずに済みます。
2-3.遺言執行者への妨害行為は禁止される
遺言執行者には、遺言執行のために強い権限が認められます。相続人は遺言執行者の行為を妨害できず、妨害行為は無効になります。
2-4.訴訟になったときに遺言執行者が対応できる
遺言内容によっては子どもたちなどの相続人同士で対立が起こり、「訴訟」となってしまうケースもあります。親族同士であっても原告と被告の立場になれば、関係性は根本的に破壊されてしまうでしょう。
遺言執行者がいれば、遺言執行者が訴訟の一方当事者となるため「相続人同士の対立構造」を避けられます。親族関係悪化を防止しやすい点もメリットとなるでしょう。
3.遺言執行者の選任方法
遺言執行者を選任するには以下の3種類の方法があります。
- 遺言書において直接指定する(複数人を選任してもかまいません)
- 遺言書で「遺言執行者を指定する人」を指定する(友人や親戚などでかまいません)
- 家庭裁判所に申立をして選任してもらう
遺言執行者になれるのは「未成年者や破産者以外の人」です。相続人や法人であっても遺言執行者になれます。
遺言執行者を相続人から選任する場合の問題点
遺言執行者を相続人の中から選任すると、他の相続人との間で感情的な軋轢が生じるケースが少なくありません。指定された相続人は名義変更などの各種手続きを行わねばならず、負担をかけてしまうのも問題です。
できれば弁護士などの信頼できる第三者を遺言執行者としておくほうが、トラブル防止になりますしスムーズに遺言内容を実現しやすくなります。
当事務所では遺言書作成のサポートに積極的に取り組んでいますので、遺言執行者をつけようか迷っている方、これから遺言書を作成しようとしている方はぜひご相談ください。

千葉県・東京23区を中心に活動する秋山慎太郎総合法律事務所です。
私たちは「身近な法律事務所」として、皆様の暮らしの安心を取り戻すお手伝いをしています。
当事務所は、相続、離婚、不動産、交通事故、債務整理、労働事件、刑事事件といった個人案件から、企業間の紛争、債権回収、労務管理等の法人案件、更には分野を特定できない法律問題まで幅広く取り扱う地域密着の総合法律事務所です。
特に、生活に直結する「借金・債務整理」や、突然のトラブルである「交通事故」の分野に力を入れており、豊富な解決実績がございます。法律の専門家として、ご相談者様一人ひとりに親身に寄り添い、迅速な解決を実現することをお約束します。
【借金・交通事故のご相談は初回30分無料】
お困りの際は、一人で悩まずに専門家にご相談ください。お電話やお問い合わせフォームから、まずはお気軽にご連絡いただければ幸いです。
【相続】遺言書の種類と選び方
遺言書を作成するときには、いくつかの「種類」から適正なものを選ばなければなりません。
通常時に利用できる遺言書には以下の3種類があります。
- 自筆証書遺言
- 秘密証書遺言
- 公正証書遺言
以下でそれぞれの特徴と選び方をお伝えしますので、これから遺言書を作成する方はぜひ参考にしてみてください。
1.自筆証書遺言
自筆証書遺言は、遺言者が全文を自筆して作成する遺言書です。
タイトル、内容、日付、署名押印欄など「すべて自筆」しないと無効になり、パソコンを使ったり代筆を依頼したりはできません。
寝たきり状態など、自筆できない方が作成するのは難しくなります。
ただし「遺産目録」の部分だけは自筆しなくてもかまいません。パソコンで作成したり預金通帳のコピーや不動産の全部事項証明書を添付したりする方法を使えます。
なお添付するコピーなどにも署名押印が必要です。
法務局における保管制度
自筆証書遺言の保管方法として、自分で管理するほか「法務局で保管してもらえる制度」を利用できます。作成した自筆証書遺言を遺言者本人が法務局へ持ち込み、申請をすれば預かってもらえるのです。
法務局に預ければ遺言書の紛失や破棄、変造などのリスクがなくなります。また法務局に保管を依頼した場合、死後の「検認」も不要になるメリットがあります。
ただし法務局では遺言内容の審査まではしてもらえません。そもそも内容的に無効であれば、法務局に預けても遺志の実現は難しくなります。
2.秘密証書遺言
秘密証書遺言は、内容を誰にもみられず秘密にできて存在のみを公証役場で認証してもらえるタイプの遺言書です。
まずは遺言者が自分で遺言書を作成し、封入します。作成の際にはパソコンを使っても構いません。
封入したら、遺言書を公証役場へ持参して認証してもらいます。公証人や証人に遺言内容を知られることはありません。保管は自分で行う必要があります。
秘密証書遺言は誰にも内容を知られないメリットがある一方で、不備があれば無効になり発見されないリスク、破棄されるリスクもあります。
「どうしても内容をみられたくない特殊事情」がある場合以外ではあまりおすすめではありません。
3.公正証書遺言
公正証書遺言は、公証役場で公文書として作成してもらう遺言書です。
遺言内容は遺言者本人が決める必要がありますが、書面化は公証人に任せます。
メリット
公正証書遺言の場合、内容も公証人が確認しますし公証人が「公文書」として作成する書類なので、要式不備で無効になるリスクはほぼありません。自筆が不要で口授によっても作成できるので、寝たきりの方でも遺言できます。
公証人に病院や自宅に出張してきてもらうことも可能です。
原本を公証役場で預かってもらえるので破棄や隠匿のリスクがありませんし、謄本をなくしても再発行を申請できます。
死後は相続人が遺言書を検索して調べられますし、検認も不要で負担がかかりません。
無効になる場合もある
遺言者が認知症にかかった後など判断能力が低下してから公正証書遺言を作成すると「意思能力を欠いて無効」となる可能性があります。
公正証書遺言を作成するとしても、早めに対応するのがよいでしょう。
4.おすすめは公正証書遺言
通常時に作成できる遺言書には上記の3種類がありますが、もっともおすすめの方法は公正証書遺言です。
3種類のうちもっとも無効になるリスクが低く、破棄や隠匿、偽造や変造の可能性もありません。確実に遺志を実現しやすくトラブル要因にもなりにくいためです。
ただし公証役場では「遺言内容」についての相談には乗ってくれません。遺留分への配慮など、トラブルを避けるための遺言内容とするには弁護士への相談が必要となるでしょう。
当事務所には千葉県を中心として多くのご家庭の遺言書作成を支援してきた実績があります。遺言書作成を検討されている方は、ぜひとも一度ご相談ください。

千葉県・東京23区を中心に活動する秋山慎太郎総合法律事務所です。
私たちは「身近な法律事務所」として、皆様の暮らしの安心を取り戻すお手伝いをしています。
当事務所は、相続、離婚、不動産、交通事故、債務整理、労働事件、刑事事件といった個人案件から、企業間の紛争、債権回収、労務管理等の法人案件、更には分野を特定できない法律問題まで幅広く取り扱う地域密着の総合法律事務所です。
特に、生活に直結する「借金・債務整理」や、突然のトラブルである「交通事故」の分野に力を入れており、豊富な解決実績がございます。法律の専門家として、ご相談者様一人ひとりに親身に寄り添い、迅速な解決を実現することをお約束します。
【借金・交通事故のご相談は初回30分無料】
お困りの際は、一人で悩まずに専門家にご相談ください。お電話やお問い合わせフォームから、まずはお気軽にご連絡いただければ幸いです。
【相続】預金使い込みで集めるべき証拠
使い込まれた預金を取り戻すには「証拠」を集めなければなりません。
証拠がなければ相手が「使い込みをしていない」と主張し、言い逃れをされてしまうためです。
今回は預金使い込みで必要な証拠の内容や集め方をご説明します。
1.預金使い込みで必要な証拠
預金使い込みを証明するために必要な証拠は、以下の2種類です。
1-1.使い込まれた証拠
使い込みそのものに関する証拠です。
被相続人名義の預金口座からいついくらの金額が出金されたのか、証明します。
1-2.被相続人が自分で出金していない証拠
被相続人名義の口座から出金されたとしても「被相続人本人が使い込んだ」といわれる可能性があります。その抗弁を崩すため「被相続人が自分で出金できなかった事情」を証明しなければなりません。出金当時の被相続人の状況を証明するための資料が必要です。
以下でそれぞれの証拠の例や集め方をみていきましょう。
2.使い込まれた証拠の例と集め方
2-1.預金取引履歴や通帳
使い込まれた証拠としては、被相続人名義の預金取引履歴や通帳が必要です。
たとえば以下のような記載があると使い込みを立証しやすくなります。
- 不自然に多額の出金が行われている
- 何日も連続して数十万円ずつの出金が行われている
- 相続人口座へ送金されている
2-2.取引履歴の入手方法
被相続人名義の預金口座取引履歴は、対象の金融機関へ請求すれば開示してもらえます。
相続人であることがわかる戸籍謄本類や申請者の身分証明書、印鑑などを用意して金融機関へ行き、申請書を提出しましょう。
3.被相続人が自分で出金していない証拠
3-1.医療機関の診療記録
被相続人が入院していた場合、自分で出金するのは困難です。認知症にかかっていた場合にも、自分の判断で出金したとは考えにくいでしょう。
病状を確認するため、病院へカルテや看護記録、診断書などの資料を請求してみてください。
請求方法について
相続人が病院へ申請すると開示を受けられるケースがありますが、病院によってはスムーズに開示を受けられない可能性もあります。
自分たちで請求しても難しい場合には、弁護士に相談しましょう。弁護士法23条照会を行うと開示を受けられる可能性があります。
3-2.介護認定の記録
介護認定を受けていた場合には、介護認定の際の資料も証拠になります。
たとえば役所から届いた通知書、主治医の意見書、提出した診断書の写しなど。
介護認定に関する記録は市区町村役場で保管されているので、行政文書の開示請求をしてみてください。
なお相続人の請求によって開示される自治体もありますが、裁判所からの照会でないと回答しない自治体もあり、ケースバイケースの対応が必要です。
3-3.介護日誌などの介護記録
被相続人が介護施設に入所していた場合や在宅で介護サービスを受けていた場合、利用していた介護事業所に記録が残っているはずです。
介護日誌や介護計画書などの資料の開示を受けましょう。
相続人が請求しても開示してもらえない場合、弁護士から弁護士法23条照会を行うと開示を受けられる可能性があります。
4.証拠の申請先
使い込みを立証するための証拠について、それぞれの申請先は以下の通りです。
- 預金の取引履歴…該当する金融機関
- 介護認定記録…自治体
- 介護記録…介護事業所
- 認知症の状態や入院記録…該当する医療機関
開示請求の手順
まずは相続人であることを示す戸籍謄本などの資料をもって、上記機関へそれぞれ申請してみてください。対応してもらえない場合、弁護士が「弁護士法23条照会」という情報照会手続きを利用すれば開示してもらえる可能性があります。
それでも開示されない場合、最終的に訴訟を申し立てて職権調査嘱託を行い、裁判所から照会をしてもらえればほとんどのケースで開示されます。
状況によっては「証拠保全」などの手続きを利用できる可能性もあります。
預金の使い込みが疑われる場合、早めに証拠を集めて相手に返還請求しましょう。お困りの方がおられましたら弁護士までご相談ください。

千葉県・東京23区を中心に活動する秋山慎太郎総合法律事務所です。
私たちは「身近な法律事務所」として、皆様の暮らしの安心を取り戻すお手伝いをしています。
当事務所は、相続、離婚、不動産、交通事故、債務整理、労働事件、刑事事件といった個人案件から、企業間の紛争、債権回収、労務管理等の法人案件、更には分野を特定できない法律問題まで幅広く取り扱う地域密着の総合法律事務所です。
特に、生活に直結する「借金・債務整理」や、突然のトラブルである「交通事故」の分野に力を入れており、豊富な解決実績がございます。法律の専門家として、ご相談者様一人ひとりに親身に寄り添い、迅速な解決を実現することをお約束します。
【借金・交通事故のご相談は初回30分無料】
お困りの際は、一人で悩まずに専門家にご相談ください。お電話やお問い合わせフォームから、まずはお気軽にご連絡いただければ幸いです。
【相続】預金の使いこみが発覚したときの「不当利得返還請求」とは
相続の発生後、被相続人と同居していた相続人による「預金の使い込み」が発覚するケースが少なくありません。
使い込まれた預金は「不当利得返還請求」によって取り戻せる可能性があります。
今回は「不当利得返還請求」とはなにか、預金を使い込まれたらどうすればよいのか解説します。
1.預金の使い込みとは
遺産相続における「預金の使い込み」とは、相続人や第三者が被相続人名義の預金を自分のものにしてしまうことです。
よくあるのが被相続人と同居していた相続人による使い込みです。
被相続人名義の預金を無断で出金して自分や家族のものを買ったり遊興費に使ったり、あるいは自分名義の口座へ移したりします。
介護サービス事業者などの第三者が被相続人名義のキャッシュカードを使って預金を使い込むケースもあります。
預金を使い込まれると、他の相続人が受け取れる遺産が目減りしてしまうので損失が発生します。そこで使い込まれた預金を取り戻すための手段の1つが「不当利得返還請求」です。
2.不当利得返還請求とは
不当利得返還請求とは、法律上の原因がないのにある人が利益を得て、反面損失を被った人がいるときに損失を受けた人が利得者へ利益の返還を要求することです。
遺産の内容となるはずだった預金が使い込まれたとき、使い込まれた相続人には損失が発生するので使い込んだ人へ不当利得返還請求ができます。
不当利得返還請求の要件は以下のとおりです。
2-1.利益を得ている
相手が「財産上の利益」を得ていることが必要です。
預金使い込みの場合、使い込んだ人は利益を獲得するのでこの要件を満たします。
2-2.法律上の原因がない
不当利得といえるためには「法律上の原因がない」ことが必要です。
売買や贈与などの契約が行われておらず遺贈されたわけでもないなら「法律上の原因がない」といえます。預金を被相続人に無断で勝手に使い込んだ場合には法律上の原因は認められません。
2-3.損失が発生している
不当利得返還請求を行うには、請求者に「損失が発生」している必要があります。
預金が使い込まれると相続人は本来相続できるはずだった預金を相続できなくなるので損失が認められます。
2-4.請求できる限度
不当利得返還請求によって相手に請求できるのは、基本的に「現存利益」に限られます。つまり「現在残っている分」しか請求できません。ただし相手が悪意の場合、利得の全額に遅延損害金をつけて請求できます。
預金を使い込まれた場合、利得者は通常「自分に権利がない」と知っているので「全額プラス遅延損害金」を請求できます。
3.不当利得返還請求の手順
不当利得返還請求を行う際には以下のような手順で進めましょう。
3-1.証拠を集める
まずは預金が使い込まれた証拠を集めなければなりません。
被相続人名義の預金口座の取引履歴を入手し、いつどのくらいの金額が出金されて使い込まれたのか計算しましょう。また「被相続人自身が出金した」と反論されないように、介護や入院記録なども集めるべきです。
3-2.相手に請求する
証拠を揃えて使い込まれた金額も明らかになったら、使い込まれた預金を請求しましょう。
内容証明郵便を使って請求書を送ると相手にプレッシャーを与えられますし、請求した証拠も残せます。
3-3.話し合う
請求を行ったら、使い込まれた預金の返還方法について相手と話し合いましょう。
任意に返還を受けられるのであれば、合意した内容を合意書にまとめます。
分割払いにするなら、合意書を公正証書にしましょう。公正証書を作成しておけば、相手が支払わないときにすぐに差し押さえができるからです。
3-4.訴訟を提起する
話し合いでは解決できない場合、訴訟を提起しましょう。
訴訟で使い込みを立証できれば裁判官が相手に支払い命令を出してくれます。
ただし訴訟手続きは複雑で専門的なので、素人の方には対処が困難となるのが通常です。
必ず弁護士へ相談しましょう。
預金を使い込まれとき、泣き寝入りする必要はありません。困ったときには弁護士までご相談ください。

千葉県・東京23区を中心に活動する秋山慎太郎総合法律事務所です。
私たちは「身近な法律事務所」として、皆様の暮らしの安心を取り戻すお手伝いをしています。
当事務所は、相続、離婚、不動産、交通事故、債務整理、労働事件、刑事事件といった個人案件から、企業間の紛争、債権回収、労務管理等の法人案件、更には分野を特定できない法律問題まで幅広く取り扱う地域密着の総合法律事務所です。
特に、生活に直結する「借金・債務整理」や、突然のトラブルである「交通事故」の分野に力を入れており、豊富な解決実績がございます。法律の専門家として、ご相談者様一人ひとりに親身に寄り添い、迅速な解決を実現することをお約束します。
【借金・交通事故のご相談は初回30分無料】
お困りの際は、一人で悩まずに専門家にご相談ください。お電話やお問い合わせフォームから、まずはお気軽にご連絡いただければ幸いです。
【相続】「時期」によって異なる預金使い込みへの対処方法
預金が使い込まれた場合、使い込みのあった「時期(タイミング)」によって取り戻す方法が異なります。
相続開始前であれば不当利得返還請求などの手続きが必要ですが、相続開始後の使い込みであれば遺産分割協議で一回的に解決できます。
今回は預金使い込みに対する対処方法を「時期別」にご説明しますので、ぜひ参考にしてみてください。
1.相続開始前の使い込み
財産の使い込み時期が相続開始前の場合、取り戻すには「不当利得返還請求」または「不法行為にもとづく損害賠償請求」をしなければなりません。
1-1.不当利得返還請求とは
不当利得返還請求とは、法律上の原因なしに利益を得た人があり、反面損失を被った人がいるときに損失を受けた人が利得者へ利益の返還を請求することです。
遺産を使い込まれたら使い込んだ人に利益が発生して使い込まれた相続人に損失が発生するので、不当利得返還請求が可能です。
1-2.不法行為にもとづく損害賠償請求とは
不法行為にもとづく損害賠償請求とは、故意や過失にもとづく違法行為によって損害を受けた人が加害者へ賠償金を請求することです。
預金使い込みは違法行為であり、通常は故意によって行われます。
相続人は使い込みによって遺産を受け取れなくなり損害を受けるので、使い込んだ相手に損害賠償請求ができます。
1-3.遺産分割協議は別途行う必要がある
「不当利得返還請求」や「不法行為にもとづく損害賠償請求」は「遺産分割協議」と異なる手続きです。
使い込んだ本人が共同相続人であっても、遺産分割協議とは別途不当利得返還請求等の手続きをしなければなりません。
話し合いで解決できない場合、「不当利得返還請求訴訟」や「不法行為にもとづく損害賠償請求訴訟」を提起する必要があります。これらの裁判は簡易裁判所または地方裁判所で行います。
一方、遺産分割については家庭裁判所で「遺産分割調停」や「遺産分割審判」を行わねばなりません。
このように、相続開始前に遺産が使い込まれると、相続人は2つの事件にかかわる必要があり、多大な負担がかかる可能性があります。
2.相続開始後の使い込み
相続開始後に預金などの遺産が使い込まれた場合には、不当利得返還請求や不法行為にもとづく損害賠償請求をしなくてもトラブルを解決できる可能性があります。
「相続開始後遺産分割前」に使い込まれた遺産については、共同相続人が全員合意すれば「遺産分割時に存在するもの」として遺産分割の対象にできるからです(民法906条の2の1項)。
使い込んだ人が相続人の場合、使い込んだ相続人の同意は不要で「他の相続人(使い込まれた相続人)全員」が合意すれば遺産内容に含められます(民法906条の2の2項)。
このように、相続開始後の使い込み財産を遺産分割の対象にすれば、使い込み問題も含めて遺産分割協議により一回で解決できます。
遺産分割協議を行っても意見が合わず合意できない場合、家庭裁判所で遺産分割調停や遺産分割審判を申し立てれば済みます。相続開始前の使い込みと異なり、別途簡易裁判所や地方裁判所で訴訟を起こす必要はありません。
3.相続開始前と開始後の両方の使い込みがある場合
相続開始前から開始後にわたって預金が使い込まれている場合には、不当利得返還請求や不法行為にもとづく損害賠償請求が必要になります。
確かに相続開始後の分だけであれば遺産分割協議で解決できるのですが、それだけでは相続開始前の使い込み分を取り戻せないからです。
4.話し合いであれば自由に解決が可能
以上はあくまで法律の定めによる取り扱いであり、相続人同士が話し合いで解決するならより自由かつ柔軟に解決できます。
たとえば使いこんだ相続人が納得して返還に応じるなら、相続開始前の使い込みであっても遺産分割協議時にまとめて返してもらってかまいません。
使い込み問題を解決するには、相手方の態度や証拠の内容などによって状況に応じた対処が必要です。弁護士にご相談いただければ証拠の集め方や返還請求方法など、アドバイスをさせていただきますし代理交渉も承ります。まずはお気軽にお問い合わせください。

千葉県・東京23区を中心に活動する秋山慎太郎総合法律事務所です。
私たちは「身近な法律事務所」として、皆様の暮らしの安心を取り戻すお手伝いをしています。
当事務所は、相続、離婚、不動産、交通事故、債務整理、労働事件、刑事事件といった個人案件から、企業間の紛争、債権回収、労務管理等の法人案件、更には分野を特定できない法律問題まで幅広く取り扱う地域密着の総合法律事務所です。
特に、生活に直結する「借金・債務整理」や、突然のトラブルである「交通事故」の分野に力を入れており、豊富な解決実績がございます。法律の専門家として、ご相談者様一人ひとりに親身に寄り添い、迅速な解決を実現することをお約束します。
【借金・交通事故のご相談は初回30分無料】
お困りの際は、一人で悩まずに専門家にご相談ください。お電話やお問い合わせフォームから、まずはお気軽にご連絡いただければ幸いです。
【相続】遺産使い込みのよくあるパターンと対処方法~株式、投資信託、賃料、保険の使い込み~
遺産が使い込まれる場合、「預金」以外にもいろいろな財産が対象になる可能性があります。
今回はよくある遺産使い込みの具体例や、使い込まれたときの対処方法をお伝えします。
1.生命保険の解約
被相続人が加入していた生命保険を勝手に解約し、解約返戻金を使い込んでしまうパターンです。同居の相続人が被相続人の印鑑などを利用して解約するケースが典型です。
2.賃料の使い込み
被相続人が不動産を所有して賃料を得ていた場合、同居の相続人が賃料を受け取って自分のものにしてしまうケースがよくあります。
特に被相続人が同居の相続人に賃料の管理を任せていた場合、当初はきちんと被相続人のために取り分けていても、だんだんとずさんになってきて使い込みが行われやすくなります。相続発生後の賃料収益も特定の相続人が独り占めし続けるので、トラブルにつながりやすいパターンです。
3.株式や投資信託の売却、使い込み
被相続人が証券会社で取引していた株式や投資信託を、相続人が勝手に売却したり売却金を使い込んだりするパターンがあります。
特に最近ではネット証券を利用する方が多いので、同居人が勝手にログインして売却したり売却金を送金したりするのも容易になっています。
「被相続人自身が売却した」と抗弁されやすいので注意が必要な類型です。
4.現金の使い込み
被相続人が自宅においていた現金を使い込むパターンです。
現金の場合、預金と違って「取引履歴」が残りません。いついくらが使い込まれたのか証拠をつかみにくい問題があります。
5.不動産の売却
被相続人が不動産を所有していた場合、同居の相続人が勝手に委任状等を作成し、被相続人の実印を使って売却してしまうケースもあります。
以上のように、遺産の使い込みには預金以外にもさまざまなパターンがあります。
5.遺産が使い込まれたときの対処方法
5-1.使い込みの証拠を集める
遺産が使い込まれたら、まずは証拠を集めなければなりません。
使い込んだ本人はほとんどの場合、使い込みを否定するからです。
生命保険の解約事例
生命保険会社へ保険解約請求書の開示を求めましょう。相続人の筆跡であれば使い込みを証明しやすくなります。
株式取引の事例
証券会社に請求し、株式売却や売却金の振り込み指示の記録を集めましょう。
ネット上で取引履歴を確認できる証券会社も多数あります。
売却時に被相続人が自分で取引できる状態でなかったことを証明できれば使い込みを立証しやすくなります。
賃料使い込みの事例
賃料管理していた預金通帳や取引履歴の取得と内容分析を行いましょう。
賃料が相続人名義の口座へ送金されていたり多額の出金があったりすると、使い込みを証明しやすくなります。
現金
現金の場合、そもそもいくら現金が自宅にあったのかを証明しなければなりません。
いつ、いくらを何に使ったのかも推測しなければならず、証明のハードルが高くなります。
個別的な対応が必要となるので、弁護士へ相談されるようお勧めします。
5-2.話し合う
証拠が揃ったら、相手に返還請求しましょう。
ただし相手が法定相続人の場合、相手にも相続分が認められるのでその分は請求できません。「請求する相続人の法定相続割合に相当する額」が請求できる金額です。
話し合いによって相手が任意に返還に応じるなら、合意書を作成して支払ってもらいましょう。一括で支払えない場合、分割払いによる対応が必要となります。
5-3.訴訟を起こす
相手が任意に支払いに応じない場合には、訴訟を起こしましょう。
使い込みを立証できれば、裁判所が支払い命令の判決を下してくれます。
相手が判決に従わない場合には、相手名義の資産を差し押さえることも可能です。
ただし訴訟で支払い命令を出してもらうには使い込みを証拠によって証明するとともに法律に従った主張を展開しなければなりません。
ご自身で対応するのは困難なので、弁護士までご依頼ください。
遺産を使い込まれたときには個々の状況に応じた対応が要求されます。当事務所では預金以外のさまざまな使い込み問題にも対応しておりますので、お困りの方はご相談ください。

千葉県・東京23区を中心に活動する秋山慎太郎総合法律事務所です。
私たちは「身近な法律事務所」として、皆様の暮らしの安心を取り戻すお手伝いをしています。
当事務所は、相続、離婚、不動産、交通事故、債務整理、労働事件、刑事事件といった個人案件から、企業間の紛争、債権回収、労務管理等の法人案件、更には分野を特定できない法律問題まで幅広く取り扱う地域密着の総合法律事務所です。
特に、生活に直結する「借金・債務整理」や、突然のトラブルである「交通事故」の分野に力を入れており、豊富な解決実績がございます。法律の専門家として、ご相談者様一人ひとりに親身に寄り添い、迅速な解決を実現することをお約束します。
【借金・交通事故のご相談は初回30分無料】
お困りの際は、一人で悩まずに専門家にご相談ください。お電話やお問い合わせフォームから、まずはお気軽にご連絡いただければ幸いです。