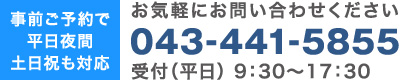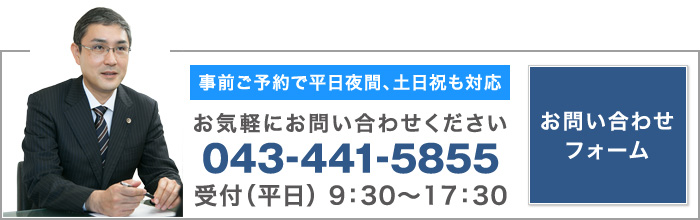近年ではビジネスの場においても急激にデジタル化が進んでおり「電子契約」を導入する企業が増えています。
ただ「電子契約や電子署名には法的効力が認められるのか?」「契約として有効なのか?」と不安を感じる方も少なくありません。
要件さえ満たせば電子署名にも法的効力が認められます。
今回は電子契約や電子署名の法的効力や有効性について、弁護士が解説します。
1,多くの契約では「契約書」は不要
「電子契約でも契約は有効に成立するのか?」
といった疑問を持つ方がおられます。
実は法律上、ほとんどの契約の成立に「契約書」は必要ありません。
書面やその他の資料がなくても、口頭で契約が成立するのです。
ただ口頭では証拠が残らず、後に証明できません。内容について争いが発生したときに大きなトラブルになってしまいます。
そこで契約内容を明らかにして証拠を残すため、通常のビジネスの場では契約書を作成するのです。
単純に「契約が成立するかどうか?」という意味では、電子契約であっても十分に契約が成立するといえます。
ただし一定の契約については「必ず書面(または電子)で締結しなければならない」と定められています。そういった類型の契約は、契約書や電子契約データを作成しなければ成立しません。
2.電子署名が有効となる要件
次に「電子署名」の有効性についてみてみましょう。
電子契約を締結する際には「電子署名」を付します。
電子データに付す署名であっても、電子署名法の定める要件を満たせば法的効力が認められます。
電子署名法では、2条において「有効な電子署名となるための要件」が規定されています。
- 本人が作成したもの(本人性)
- 改変されていないことを確認できるもの(非改ざん性)
つまり本人確認が行われていて、作成されてから改ざんされていないことを確認できるものであってはじめて有効な「電子署名」となります。
具体的には認証局の発行する「電子証明書」と「タイムスタンプ」によって上記の要件を満たします。
クラウドの電子署名サービスを利用した場合でも、きちんと本人確認されていてタイムスタンプが付与されていれば有効な電子署名となります。
3.電子署名に推定効が及ぶ要件
電子署名法3条では、電子署名に「推定効」が及ぶ要件が規定されています。
推定効とは「本人による電子署名が付されているときに電子データが真正に成立したと推定する」効力です。つまり本人が電子署名していれば、その電子データは署名者自身が作成したと推定できます。
第3条 電磁的記録であって情報を表すために作成されたもの(公務員が職務上作成したものを除く。)は、当該電磁的記録に記録された情報について本人による電子署名(これを行うために必要な符号及び物件を適正に管理することにより、本人だけが行うことができることとなるものに限る。)が行われているときは、真正に成立したものと推定する。
紙の書面に対する署名押印にも同様の効果が認められています。これを「2段の推定」といいます。
電子署名法3条の電子署名といえるには、以下の要件を満たさねばなりません。
- 本人性
- 非改ざん性
- 固有性
電子署名法2条の要件に足して、「本人だけが行うことができる」という固有性の要件を満たす必要があります。
具体的には以下のような方法が考えられます。
- 本人が認証局へ申請して電子証明書を取得して電子署名する
- クラウドの電子署名サービスを使う場合、2要素認証によって厳格に本人確認する
上記のような対応ができれば、電子契約であっても紙の契約書と同等の法的効力が認められます。
4.電子契約を適用される範囲が拡大
現在、電子契約を適用できる範囲は拡大しつつあります。従来は紙の契約書を必要としていた不動産の賃貸や売買などにおいても電子契約を利用できるようになる予定です(ただし事業用定期借地権契約を除く)。
電子契約導入の際に不安な点がありましたら弁護士がアドバイスいたしますので、お気軽にご相談ください。

千葉県・東京23区を中心に活動する秋山慎太郎総合法律事務所です。
私たちは「身近な法律事務所」として、皆様の暮らしの安心を取り戻すお手伝いをしています。
当事務所は、相続、離婚、不動産、交通事故、債務整理、労働事件、刑事事件といった個人案件から、企業間の紛争、債権回収、労務管理等の法人案件、更には分野を特定できない法律問題まで幅広く取り扱う地域密着の総合法律事務所です。
特に、生活に直結する「借金・債務整理」や、突然のトラブルである「交通事故」の分野に力を入れており、豊富な解決実績がございます。法律の専門家として、ご相談者様一人ひとりに親身に寄り添い、迅速な解決を実現することをお約束します。
【借金・交通事故のご相談は初回30分無料】
お困りの際は、一人で悩まずに専門家にご相談ください。お電話やお問い合わせフォームから、まずはお気軽にご連絡いただければ幸いです。