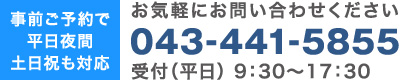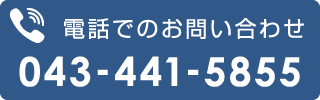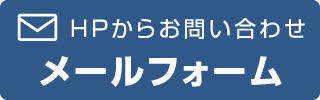Archive for the ‘千葉の弁護士コラム’ Category
【相続】相続トラブルになりやすいパターン
「相続トラブル」と聞くと、「一部の富裕層の家庭で起こるもの」というイメージがあります。しかし現実には、多くのトラブルは一般の中流家庭で起こっています。
親の生前は仲の良かった子ども達でも、親の死後に熾烈な相続争いを繰り広げるケースが少なくありません。
今回は相続トラブルになりやすい「要注意」のパターンをご紹介します。対処方法もお伝えしますので、是非参考にしてみてください。
1.遺産が「実家不動産」のみ
遺された遺産が「実家の土地建物だけ」の場合、親としては「こんな少しの遺産なのでトラブルにならないだろう」と考えるでしょう。
しかし現実には、このパターンが非常に危険です。
実家の不動産しか遺産がないと、子ども達が「公平に遺産分割する」ことが困難となります。
実家を維持したい子ども、実家を売って分けたい子ども、実家は要らないので代償金を払ってほしい子どもなど、いろんな意見があって合意できなくなってしまうのです。
実家しか遺産がないなら、必ず誰に家を残すのか、代償金をいくらとするのかなど遺言書によって明らかにしておきましょう。
2.前婚の子どもがいる
再婚している方も、遺産相続で要注意です。前婚の際に生まれた子どもにも、今の家族の子どもと同様に遺産相続権が認められるためです。
今の家族の子どもや配偶者は、前婚の子どもに遺産を渡したくないと考えるでしょう。しかし法的には前婚の子どもにも権利があるので、意見が合わずにトラブルにつながります。
再婚している方は、必ず遺言書で今の家族に多めに遺産を遺すなど、相続方法を指定しておきましょう。
3.不公平な遺言書
遺言すれば相続トラブルを避けられる、というものでもありません。
遺言書がトラブルの種になるケースがあるので注意しましょう。
「特定の相続人にすべて相続させる」などの不公平な遺言があると、相続できなくなった相続人が「遺留分」を主張する可能性があります。すると、遺留分を侵害された相続人が遺留分を侵害した人へ「遺留分侵害額請求」という金銭の要求をして、トラブルにつながってしまいます。
遺言書を書くときには、相続人の遺留分を侵害しないよう配慮しなければなりません。
3.生前贈与した
高額な生前贈与を行った場合にも、トラブルが発生します。
たとえば長女が結婚するときに高額な持参金を出した場合を考えてみましょう。
こういった場合には、遺産分割の際、長女がもらった持参金を「遺産の先渡し」として差引計算ができます。これを「特別受益の持ち戻し計算」といいます。
ただ、「本当に特別受益になるのか」「特別受益の金額はどのくらいが妥当か」など、相続人間で意見が合わずトラブルになってしまうケースが少なくありません。
特別受益の持ち戻し計算は、遺言書などの方法で免除できます。相続トラブルを避けたいなら、特別受益の持ち戻し計算を免除しておくか、特別受益を考慮した内容の遺言書を書いておくと良いでしょう。
4.献身的に介護した相続人がいる
献身的に被相続人を介護した相続人がいる場合にも、トラブルになりやすい傾向があります。献身的に介護をすると、その相続人には「寄与分」が認められる可能性があるからです。寄与分が認められると、その相続人の遺産取得分が増額されます。
ただ、他の相続人は寄与を認めなかったり、金額を低く見積もったりするので意見がまとまらなくなってしまうのです。
寄与分が認められそうな相続人がいる場合にも、やはり遺言書できっちり相続方法を指定しておきましょう。
5.遺言書作成、相続トラブル予防は弁護士へお任せを
遺産相続トラブルを防ぐには、遺言書が有効です。ただ遺言書にもいろいろな方式があり、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言、それぞれ特徴やメリット・デメリットがあります。
内容面にも配慮しなければならないので、素人判断では遺言書がトラブルの種になるリスクも懸念されるでしょう。
弁護士が相続トラブル予防・解決支援をいたします。心配な方はお早めにご相談ください。

千葉県・東京23区を中心に活動する秋山慎太郎総合法律事務所です。
私たちは「身近な法律事務所」として、皆様の暮らしの安心を取り戻すお手伝いをしています。
当事務所は、相続、離婚、不動産、交通事故、債務整理、労働事件、刑事事件といった個人案件から、企業間の紛争、債権回収、労務管理等の法人案件、更には分野を特定できない法律問題まで幅広く取り扱う地域密着の総合法律事務所です。
特に、生活に直結する「借金・債務整理」や、突然のトラブルである「交通事故」の分野に力を入れており、豊富な解決実績がございます。法律の専門家として、ご相談者様一人ひとりに親身に寄り添い、迅速な解決を実現することをお約束します。
【借金・交通事故のご相談は初回30分無料】
お困りの際は、一人で悩まずに専門家にご相談ください。お電話やお問い合わせフォームから、まずはお気軽にご連絡いただければ幸いです。
【相続】遺産相続の流れと期限を解説
遺産相続が発生したら、やるべきことが非常にたくさんあります。
期限のある手続きも多いので、段取りよく進めていきましょう。
今回は遺産相続の流れを、それぞれの期限も含めてご紹介します。相続して対応に迷っている方は、ぜひ参考にしてみてください。
1.死亡から7日以内にすべき手続き
人が死亡したら、7日以内に死亡届を提出しなければなりません。
死亡届を提出すると、引換に「火葬許可証」を交付してもらえます。
葬儀社などと協議して、お葬式や火葬を行いましょう。
2.死亡から14日以内にすべき手続き
死亡後14日以内に、以下の手続きをする必要があります。
- 健康保険、介護保険の資格喪失届
- 国民年金受給停止の手続き(ただし厚生年金の場合は死亡後10日以内)
- 世帯主変更届
3.遺言書を探す
次に遺言書を探しましょう。遺言書があれば、指定された方法で相続を行う必要があり、遺産分割協議は不要となります。公正証書遺言は公証役場で検索してもらえるので、心当たりがあれば公証役場を訪ねましょう。
自筆証書遺言が法務局で保管されている場合には、法務局で調べられます。
遺言書の検認
自筆証書遺言が自宅で保管されていた場合や秘密証書遺言の場合、家庭裁判所で「遺言書の検認」を受けなければなりません。
4.相続人調査
次に相続人調査をしましょう。相続人が明らかにならないと、誰が遺産を受け取るべきか定まりません。
家族関係が簡単で相続人が明確な場合でも相続人調査が必要です。
被相続人の生まれてから死亡するまでの戸籍謄本類を取得して、実子や養子、認知した子どもの有無なども含めて確認してください。
5.相続財産調査
遺産を分ける前提として相続財産内容も知る必要があります。
預貯金、株式、不動産、出資金、貴金属などの財産を調べましょう。
6.3ヶ月以内に相続放棄や限定承認
相続放棄や限定承認をする場合、被相続人が死亡してから3ヶ月以内に家庭裁判所で申述しなければなりません。
借金を相続してしまった場合などには、急いでこれらの手続きを利用するかしないか決定しましょう。
7.4ヶ月以内に準確定申告
被相続人が事業主だった場合などには、相続人が代わりに「確定申告」をしなければなりません。これを「準確定申告」といいます。
相続開始後4ヶ月以内に税務署で手続きしなければならないので、注意しましょう。
8.遺産分割
相続人と相続財産が明らかになったら、遺産分割協議を行います。
遺産分割協議には、相続人が全員参加しなければなりません。
相続財産の具体的な分け方を決めて「遺産分割協議書」を作成しましょう。
9.10か月以内に相続税の申告と納税
相続財産の評価額が相続税の「基礎控除」を超えている場合、相続税の申告と納税が必要です。期限は相続開始後10ヶ月とされているので、急いで手続きしましょう。
10.名義変更などの相続手続き
遺産分割が終了したら、速やかに不動産の名義変更などの相続手続きをしましょう。
名義変更せずに放っておくと混乱のもとになるので、早めに対応するようお勧めします。
11.1年以内に遺留分侵害額請求
不公平な遺言書が遺された場合や高額な生前贈与があった場合などには、兄弟姉妹以外の法定相続人は「遺留分侵害額請求」できる可能性があります。遺留分侵害額請求とは、最低限の遺産取得割合である「遺留分」をお金で取り戻す手続き。遺言や生前贈与で「遺留分」を侵害されたら、侵害した人へ「遺留分」に相当する金額のお金を要求できます。
遺留分侵害額請求は相続開始後1年以内に行わねばならないので、納得できないなら早めに手続きしましょう。
12.3年以内に生命保険の受け取り
被相続人の死亡によって生命保険金が支払われる場合、死亡後3年以内に手続きしなければなりません。できれば死亡後すぐに申請するのがベストですが、遅れた場合でも必ず3年以内には申請しましょう。
相続人になると、たくさんやるべきことがあって対応に迷ってしまうでしょう。困ったときやトラブルになりそうなときには、お気軽に弁護士までご相談ください。

千葉県・東京23区を中心に活動する秋山慎太郎総合法律事務所です。
私たちは「身近な法律事務所」として、皆様の暮らしの安心を取り戻すお手伝いをしています。
当事務所は、相続、離婚、不動産、交通事故、債務整理、労働事件、刑事事件といった個人案件から、企業間の紛争、債権回収、労務管理等の法人案件、更には分野を特定できない法律問題まで幅広く取り扱う地域密着の総合法律事務所です。
特に、生活に直結する「借金・債務整理」や、突然のトラブルである「交通事故」の分野に力を入れており、豊富な解決実績がございます。法律の専門家として、ご相談者様一人ひとりに親身に寄り添い、迅速な解決を実現することをお約束します。
【借金・交通事故のご相談は初回30分無料】
お困りの際は、一人で悩まずに専門家にご相談ください。お電話やお問い合わせフォームから、まずはお気軽にご連絡いただければ幸いです。
【相続】遺産相続とはどう違うの? 「生前贈与」のメリットとは
「生きているうちに、財産を分け与えたい」と考える方も少なくないでしょう。
生きているうちに、配偶者や血縁者などに財産を分け与えることを「生前贈与」と言います。
生前贈与は相続財産を減らして相続税を抑えることができますが、一方で贈与税がかかる場合もあります。ここでは生前贈与の条件やメリットについてご紹介します。
生前贈与とは?
生前贈与とは、自分が亡くなる前に自分の財産を人に分け与える行為を指します。
一般的に生前贈与は「将来負担することになる相続税を抑えたい」という動機で行われるケースが多いようです。
遺産分割においては、相続人の中に生前贈与を受けた人がある場合には、その人に対する相続分の前渡しとみて、計算上は相続財産に加算した上で各相続人の相続分を算定することになります。このように扱われる生前贈与のことを「特別受益」と言います。
なお、全ての生前贈与が特別受益となる訳ではありません。被相続人から特定の相続人に対して、“婚姻”や“養子縁組”のため、あるいは“生計の資本”としての贈与があった場合に、特別受益として扱われることになります(民法903条)。
生前贈与の注意点
前述のとおり、財産の一部を生前贈与すると、遺産分割の際には特別受益として扱われる場合があります。
特別受益となる場合、この金額は、計算上相続財産に加算し、その上で各相続人の相続分が算定されることになります。これを特別受益の持戻しと言います。
例えば、本人(被相続人)、配偶者と息子A・息子Bの4人家族で、本人が息子Aに生計の資本として200万円を生前贈与していたとします。
本人が亡くなった後、遺産が1000万円あった場合、遺産分割の際には先の生前贈与200万円を特別受益として1000万円に加算し、その上で平等になるよう各相続分を算定します。具体的な相続分は、配偶者が600万円、息子Aが100万円、息子Bが300万円となります。
(計算)
みなし相続財産 遺産1000万円+特別受益200万円=1200万円
各相続人の具体的相続分
配偶者 1200万円×1/2=600万円
息子A 1200万円×1/2×1/2-200万円=100万円
息子B 1200万円×1/2×1/2=300万円
本人(被相続人)が、将来の自分の遺産分割において特別受益の持戻しを望まない場合には、「持戻し免除の意思表示」をしておく必要があります。
生前贈与のメリット
生前贈与は、主に相続税対策という点でメリットがあります。この点につきましては、相続税に詳しい税理士さんにご相談されることをお勧めします(当事務所からご紹介することも可能です。)。
但し、生前贈与のメリットは、あくまで税法上のメリットです。税法上控除を受けられるからといって、遺産分割の際にも生前贈与を考慮しなくて良いということにはなりません。
あくまで遺産分割においては、特別受益に該当する生前贈与は相続財産に持ち戻して相続分を算定することになりますのでご注意ください。
生前贈与を行う場合は、贈与の方法や課税対象となる金額に注意が必要です。また贈与を受ける側のライフプランなどに合わせて、計画的に生前贈与をしましょう。
生前贈与には、条件や税金など細かい規定があるため、専門家に相談するようにしましょう。

千葉県・東京23区を中心に活動する秋山慎太郎総合法律事務所です。
私たちは「身近な法律事務所」として、皆様の暮らしの安心を取り戻すお手伝いをしています。
当事務所は、相続、離婚、不動産、交通事故、債務整理、労働事件、刑事事件といった個人案件から、企業間の紛争、債権回収、労務管理等の法人案件、更には分野を特定できない法律問題まで幅広く取り扱う地域密着の総合法律事務所です。
特に、生活に直結する「借金・債務整理」や、突然のトラブルである「交通事故」の分野に力を入れており、豊富な解決実績がございます。法律の専門家として、ご相談者様一人ひとりに親身に寄り添い、迅速な解決を実現することをお約束します。
【借金・交通事故のご相談は初回30分無料】
お困りの際は、一人で悩まずに専門家にご相談ください。お電話やお問い合わせフォームから、まずはお気軽にご連絡いただければ幸いです。
相続トラブルQ&A
(1)兄が遺産を独占しようとしています。
先日父が亡くなり、残された兄と弟である私で遺産を相続する予定です。
ところが、父が施設に入ったころから父の財産を管理していた兄は、父の預金や不動産等の財産を独り占めにしようとし、私が何度話合いを求めても、はぐらかされたり無視されたりしていて、ついには遺産の話をすると怒り出すようになってしまいました。
私は遺産相続を断念しないといけないのでしょうか?
【回答】
お父様の遺産を相続する権利は、当然ながら弟さんにもありますので、断念する必要はありません。遺産分割協議をして、どのように遺産を分割するのか、お兄様とよく話し合って決めていくことになります。
ただし、今回のケースのように他の相続人が遺産分割協議に応じなかったり、あるいはこちらの要望を全く聞き入れてくれないような場合には、弁護士を代理人に立てて話合いを求めたり、家庭裁判所に遺産分割調停や遺産分割審判を申し立てることが有効です。
(2)兄が遺産分割協議書への署名押印を要求していますが、内容に同意できません。
父が亡くなりました。相続人は私(弟)と兄です。
先日、実家に行って兄と遺産分割の話合いをしたのですが、兄は「自分は長男で実家の家業を手伝って来たし、自分達夫婦が父親の介護もして来たのだから、父の遺産は全部自分が相続する」などと言って、兄が事前に準備していた「遺産分割協議書」に署名押印するよう強く求められました。その「遺産分割協議書」は、兄ひとりが遺産全部を取得し、私は何も取得しないという内容のものでした。
兄が実家の家業を手伝い、また、兄夫婦が父の介護をしてくれていたのは事実なのですが、全ての遺産を兄が取得するという内容の「遺産分割協議書」には納得がいかず、その日は物別れになって帰宅しました。今後どのようにすればよいでしょうか。
【回答】
お兄さんが実家のお父さんの家業を手伝い、また、お父さんの介護をしていたということであれば、お兄さんの貢献を「寄与分」と評価し、遺産に対するお兄さんの取得分があなたの取得分より多くなるということはあります。しかし、そうは言っても、お兄さんが遺産の全てを取得できるということにはなりません。
お兄さんとの話合いが難しいようであれば、弁護士を代理人に立てて話合いを求めたり、家庭裁判所に遺産分割調停や遺産分割審判を申し立てることで、解決することができます。
安易に「遺産分割協議書」に署名押印をしてしまい、後になって悔やまないよう、ご自分だけで判断せずに、一度は弁護士にご相談されることをお勧めします。
(3)兄が遺産の内容を教えてくれません。
父が他界しました。兄と私(弟)に相続の資格があります。亡くなる2年ほど前から父は施設で生活をしており、兄はその頃より父保有の財産を全て預かって管理するようになりました。
しかし、先日、兄から父は財産をほとんど残していなかったと告げられ、相続放棄の書類に署名押印するように求められました。
兄が私より多く相続することは一向に構わないですし、本当に財産がほとんどなかったのであれば放棄してもよいと思っているのですが、兄からは父の預金通帳を見せてもらえず、本当に遺産が残っていないのか確認することが出来ません。
実際に父の遺産がどれくらいだったのか確認もなしに署名押印することは避けたいのですが・・・。
【回答】
あなたはお父様の相続人ですので、相続人として金融機関にお父様の預貯金残高や取引履歴の開示を求めることができます。また、不動産については、市役所で固定資産税台帳を閲覧する等して確認することができます。
(4)兄が遺言書を理由に遺産の内容を教えてくれません。
母が他界しました。兄と私(妹)が相続人です。兄から見せられた母の遺言書には、現金200万円を私が相続し、それ以外の財産は全て兄に相続させるとだけ記載されていました。
その後、私は兄から現金200万円を渡されたのですが、母の財産が全部でどれだけあったのかは私には分かりません。
兄に尋ねましたが、兄は「おまえは現金200万円しか相続出来ないのだから、遺産総額を知っても意味がないだろう」と言って教えてくれません。
そういうものなのでしょうか。
【回答】
あなたには、最低でもお母様の相続財産に対して4分の1の遺留分がありますので、遺言書に記載されている現金200万円がお母様の相続財産の4分の1に満たなければ、あなたは遺留分が侵害されているということになり、その差額をお兄様に請求することができます。
簡単に説明しますと、例えば、お母様の相続財産の総額が1,600万円とすると、あなたの遺留分は400万円です。そうすると、あなたが遺言により取得した現金200万円と遺留分400万円との差額である200万円を、お兄様に請求することができます。
あなたの遺留分が侵害されているか否か確認するためには、お母様の遺産の全容を知る必要がありますので、お兄様に教えてもらうか、教えてくれなければ調査をしなければなりません。また、念のため遺留分減殺請求の意思表示を時効期間内にしておいた方が良いでしょう。お兄様との協議が難しいようでしたら弁護士にご相談ください。
(5)姉から見せられた遺言書の信憑性に疑問があるのですが・・・。
母親が亡くなりました。姉と私(妹)が相続人になるので、私は遺産を2人で平等に分割しようと考えていたのですが、姉から見せられた母の遺言書には、手書きで母の遺産の全てを姉に相続させると記載されていました。その遺言書は、姉が母へ指示をして書かせたもののようです。
姉は遺言書の内容は絶対だと言うのですが、生前母は常々「遺産は二人で半分に分けるように」と言っていましたし、遺言書の作成日を見たところ、母の認知症がかなり進行していたころに作成されたものであることが分かりました。
このようなことから、私は遺言書の信憑性に疑問を感じています。よく見ると、筆跡も母のものとは異なるような気もしてきました。
この様な状況で、どのような手続をすればよいのでしょうか?
【回答】
仮に遺言書の筆跡がお母様のものではないとすると、遺言書は偽造ですので無効となります。また、偽造ではなくお母様がご自身で作成された遺言書であったとしても、作成当時お母様の認知症がかなり進行していたということになりますと、お母様の遺言能力が問題となります。お母様に遺言能力がない状態で作成された遺言書は無効です。
このような場合、遺言無効確認訴訟を提起して、裁判所の判断を仰ぐことになります。
なお、裁判所に遺言書が有効であると判断される可能性もありますので、その場合に備えて、予備的にお姉様に対する遺留分減殺請求の意思表示を時効期間内にしておくべきでしょう。
(6)遺言書で私の取り分は全くありませんでした。
母が先ごろ他界しました。相続人は私(妹)と兄の2人になります。
葬儀の後、兄から母が「遺言公正証書」というものを作成していたことを知らされましたが、その内容は、全ての遺産を兄へ相続させ、私の取り分は全くないという偏ったものでした。
兄は「遺言は母の希望なのだからそれに従うべきだ」の一点張りで、私が遺産の分割を求めても拒否し続けています。
私は遺産を全く分けてもらえないのでしょうか?
【回答】
たとえ遺言書であなたの取得分がないものとされていても、あなたには、最低でもお母様の相続財産に対して4分の1の遺留分がありますので、この権利が侵害されているとして、お兄様に遺留分減殺請求をすることができます。
ただし、遺留分減殺請求の意思表示は、遺留分が侵害されていることを知ってから1年以内にしなければ時効によって消滅してしまいますので、速やかにお手続ください。
(7)亡くなった父が多額の借金をしていました。
父が亡くなりました。相続人は母と兄弟2人なのですが、生前父が多額の借金をしており返済もまだ終わっていませんでした。今現在、母は父名義のマンションで生活をしています。
父の遺産を相続するということは、父の借金も引き継ぐことになると聞いたのですが、私達残された家族で父の借金を返済しなければいけないのでしょうか?
【回答】
遺産の相続は、不動産や預貯金といったプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も引き継ぐということになりますので、あなた方ご家族がお父様の遺産を相続するのであれば、お父様の借金を返済しなければなりません。
お父様の借金が高額で返済は難しいということであれば、家庭裁判所で相続放棄の手続きをすることをお勧めします。ただし、この場合、相続放棄により、お父様名義のマンションも放棄することになりますので、お母様が引き続きマンションで生活することは難しくなります。
(8)遺留分放棄を要求されました。
私の両親は、私が幼いころ離婚し、母に引き取られた私はその後一度も父と会ったことはありませんでしたが、先日父の後妻の方から父が亡くなったとの手紙が届きました。
後妻の方に連絡をし、ご自宅に線香をあげに行った際、後妻の方から、父は全ての財産を後妻に相続させるとの遺言書を作成している、私に遺留分を放棄して欲しい、と頼まれました。
私は父の顔も覚えていないですし、後妻の方の気持ちも分かりますが、私も経済的余裕があまりないので少しでも何かいただければ助かります。
そうは言っても、後妻の方と直接会って話合いをするのは気が引けるので、出来れば避けたいと思っているのですが・・・。
【回答】
例えお父様と長年交流がなかったとしても、あなたが実の息子である以上、法律的にあなたには遺留分があります。そこで、遺留分を放棄するという100か0かということにするのではなく、お互いの事情を考慮しながら、遺留分としてのあなたが取得する分をどれくらいにするのが妥当なのかを協議していくのが良いのではないでしょうか。
もしも後妻の方との話合いが気まずいのであれば、弁護士に委任して手続を進めることも可能です。
(9)ほとんど交流がなかった父が亡くなりました。
何十年もの間ほとんど交流がなかった父が亡くなりました。連絡をして来た叔父からは「親子関係が途絶えていたのだからおまえは何も相続できない」と一方的に告げられました。
叔父と相続の協議を行うのは厳しい状態です。
【回答】
長期に渡り交流がなかった親子関係だったとしても、お父様の実子である以上、あなたはお父様の相続人となります。他方、叔父様は、お父様の相続人ではありませんので、遺産分割協議の相手方ではありません。
先ずは、長年交流のなかったお父様の相続人として、他にどなたがいるのか、あなたが知らないお父様のお子様がいないか、お父様が養子をとっていないか等を戸籍謄本等で確認する必要があります。また、お父様の遺産の調査も必要です。
その上で、他の相続人に対して遺産分割協議を求めていくことになります。
(10)連絡を取っていなかった弟が他界しました。
長期間連絡を取っていなかった弟が亡くなりました。弟の家族は子供なしの夫婦2人。兄弟は兄である私と弟の2人でした。
先ごろ弟の妻より、私は弟と疎遠だったので相続を放棄してほしいと告げられました。
弟と何十年も連絡を取っていなかったのは事実なので、遺産相続にあれこれ意見を言うべきでないと思っています。これといって遺産がないということであれば、私は遺産を取得しなくても構いません。
とは言え、両親は生前弟にかなり金銭的な支援をしていましたし、両親の遺産も弟が相続したという事情もありますので、余裕があるのであれば、私も相続したいと思っています。
ところが、弟の妻は遺産の内容を教えてくれません。どうしたらよいでしょうか。
【回答】
交流の有無に関わらず、あなたは弟さんの遺産の4分の1を相続する権利があります。
弟さんの妻が遺産の内容を教えてくれないということであれば、相続人として、金融機関に弟さんの預貯金残高や取引履歴の開示を求めたり、市役所で固定資産税台帳を閲覧する等して遺産を調査する必要があります。
弟さんの妻と対面で協議をするのが気まずければ、弁護士を代理人に立てて弟さんの妻と交渉し、解決を図ることができます。

千葉県・東京23区を中心に活動する秋山慎太郎総合法律事務所です。
私たちは「身近な法律事務所」として、皆様の暮らしの安心を取り戻すお手伝いをしています。
当事務所は、相続、離婚、不動産、交通事故、債務整理、労働事件、刑事事件といった個人案件から、企業間の紛争、債権回収、労務管理等の法人案件、更には分野を特定できない法律問題まで幅広く取り扱う地域密着の総合法律事務所です。
特に、生活に直結する「借金・債務整理」や、突然のトラブルである「交通事故」の分野に力を入れており、豊富な解決実績がございます。法律の専門家として、ご相談者様一人ひとりに親身に寄り添い、迅速な解決を実現することをお約束します。
【借金・交通事故のご相談は初回30分無料】
お困りの際は、一人で悩まずに専門家にご相談ください。お電話やお問い合わせフォームから、まずはお気軽にご連絡いただければ幸いです。
【相続】相続開始から3か月以上経過してからの相続放棄
事例
前回の事例の続きになります。
Yさんは、6年前に亡くなった伯母さんの相続人として、市原市にある亡伯母さん名義の固定資産税を支払わなければならないことになってしまいました。建物は老朽化しており、Yさんとしては、建物を相続するつもりはなく、滞納している固定資産税も支払いたくはありません。
しかし、Yさんは「相続放棄は3か月以内にしなければならない」と聞いたことがあり、伯母さんが亡くなってから既に6年も経ってしまっているため相続放棄できないのではないかと不安になりました。
回答
相続放棄は、相続開始(被相続人の死亡)から3か月以上経ってもできる場合があります。
相続の承認または放棄をすべき期間について、民法第915条第1項は「相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三個月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。」と規定しています。
本件は「自己のために相続の開始があったことを知った時」に該当するか否かの問題であり、判例は「相続人が相続開始の原因たる事実の発生を知り、かつそのために自己が相続人となったことを覚知した時を指す」(大決大15.8.3民集5-679)という基準を示しています。
Yさんは、6年前に伯母さんが亡くなったのは知っていましたが、従兄弟が伯母さんの養子だったことも、伯母さんと離縁していたことも知らず、伯母さんの相続人は従兄弟だと思っていました。Yさんにとって「相続開始の原因たる事実の発生」すなわち伯母さんが亡くなった事実を知っただけでは「自己のために相続の開始があったことを知った」ことにはなりません。Yさんが、従兄弟は伯母さんの相続人ではないという事実を知ってはじめて「自己が相続人となったことを覚知した」ことになります。
よって、Yさんが、従兄弟は伯母さんの相続人ではないこと、すなわち伯母さんの相続人はYさん自身だということを知ってから3か月以内に相続放棄の手続をすればまだ間に合います。
当事務所において相続放棄の手続をし、無事、Yさんは固定資産税を支払わなくて良いことになりました。
相続放棄の手続について
被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所で手続します。
相続放棄の申述書を作成し、
①被相続人の除籍謄本
②被相続人の住民票除票又は戸籍の附票
③放棄する人の戸籍謄本
④被相続人と放棄する人との関係が分かる戸籍謄本(①③で分かれば不要)
と一緒に家庭裁判所に提出します。印紙800円と指定された券種の郵便切手も納付します。
申述書には「相続の開始を知った日」「放棄の理由」「相続財産の概略(資産・負債)」を記載します。
申述書を提出してからおよそ1か月で家庭裁判所から「相続放棄申述受理通知書」が届きます。さらに「相続放棄申述受理証明書」を希望する場合には、家庭裁判所に印紙150円を納付して発行を受けることができます。

千葉県・東京23区を中心に活動する秋山慎太郎総合法律事務所です。
私たちは「身近な法律事務所」として、皆様の暮らしの安心を取り戻すお手伝いをしています。
当事務所は、相続、離婚、不動産、交通事故、債務整理、労働事件、刑事事件といった個人案件から、企業間の紛争、債権回収、労務管理等の法人案件、更には分野を特定できない法律問題まで幅広く取り扱う地域密着の総合法律事務所です。
特に、生活に直結する「借金・債務整理」や、突然のトラブルである「交通事故」の分野に力を入れており、豊富な解決実績がございます。法律の専門家として、ご相談者様一人ひとりに親身に寄り添い、迅速な解決を実現することをお約束します。
【借金・交通事故のご相談は初回30分無料】
お困りの際は、一人で悩まずに専門家にご相談ください。お電話やお問い合わせフォームから、まずはお気軽にご連絡いただければ幸いです。
【相続】他の相続人が相続放棄しているか否かの調査方法
<事例>
Yさんは、ある日突然、市原市役所から手紙を受け取りました。手紙には、6年前に亡くなった伯母さん名義の建物の固定資産税を納付するよう書いてありました。伯母さんが亡くなってからずっと固定資産税の滞納が続いているようです。
Yさんの亡くなった両親と伯母さんとは不仲であったため、Yさんも生前の伯母さんとは全く交流がありませんでした。伯母さんには子供(Yさんの従兄弟)が1人いたはずであり、Yさんとしては伯母さんの相続人でも何でもないので支払う必要はないと思っています。しかし、役所からの手紙でもあるので心配になり、市役所の窓口に行って聞いてみたのですが、詳しいことは「個人情報」を理由に教えてくれません。そこで、弁護士に相談することにしました。
<回答>
Yさんは伯母さんの相続人になっている可能性があります。Yさんが考えているとおり、本来伯母さんの相続人は伯母さんの子供でありYさんではありません。しかし、市役所が相続人の調査をしないままYさんに手紙を送って来たとは考えられません。考えられるのは、伯母さんの子供は相続放棄をしており、その結果Yさんが相続人となったのではないかということです。そこで、伯母さんの子供が相続放棄をしているか否かを調査する必要があります。
相続放棄の調査方法
相続人が相続放棄をしているか否かは、被相続人(亡くなった方)の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に照会することによって調べることができます。照会手数料は無料です。
「相続放棄・限定承認の申述の有無についての照会申請書」と「被相続人等目録」を作成し、
①被相続人の住民票除票(本籍地が表示されているもの)
②照会者と被相続人との関係がわかる戸籍謄本
③照会者の住民票(本籍地が表示されているもの)
④相続関係図
と一緒に家庭裁判所に提出します。返信用封筒と返信用切手を一緒に提出すれば郵送で回答してもらえます。
「被相続人等目録」には被相続人の本籍・最後の住所地・氏名・死亡日と,照会したい相続人の氏名を記載します。
申請をしてからおよそ1か月以内には家庭裁判所から回答が届きます。
<解決>
当事務所は、Yさんから相続放棄の有無の照会手続の依頼を受け、被相続人の最後の住所地である市原市を管轄する千葉家庭裁判所に照会をする予定で準備を開始しました。ところが、被相続人(伯母さん)の除籍謄本を確認したところ、新事実が判明しました。
Yさんが伯母さんの実子だと思っていた従兄弟は、実は伯母さんの養子であり、生前伯母さんは養子縁組を解消していたことが判明したのです。市原市役所がYさんから詳しい事情を聴かれても回答しなかったのは、亡伯母さんと従兄弟の養子縁組解消の事実を「個人情報」と判断したためだったのでしょう。
本件では、伯母さんと養子が離縁していたため、伯母さんの相続人はYさんで間違いなく、Yさんは亡伯母さん名義の建物の固定資産税を支払わなければならないということになります。
なお、実際には、その後、当事務所において、Yさんは伯母さんの遺産に対する相続放棄の手続をしましたので、固定資産税は支払わずに済みました(相続開始から3か月以上経過してからの相続放棄)。

千葉県・東京23区を中心に活動する秋山慎太郎総合法律事務所です。
私たちは「身近な法律事務所」として、皆様の暮らしの安心を取り戻すお手伝いをしています。
当事務所は、相続、離婚、不動産、交通事故、債務整理、労働事件、刑事事件といった個人案件から、企業間の紛争、債権回収、労務管理等の法人案件、更には分野を特定できない法律問題まで幅広く取り扱う地域密着の総合法律事務所です。
特に、生活に直結する「借金・債務整理」や、突然のトラブルである「交通事故」の分野に力を入れており、豊富な解決実績がございます。法律の専門家として、ご相談者様一人ひとりに親身に寄り添い、迅速な解決を実現することをお約束します。
【借金・交通事故のご相談は初回30分無料】
お困りの際は、一人で悩まずに専門家にご相談ください。お電話やお問い合わせフォームから、まずはお気軽にご連絡いただければ幸いです。
【不動産】昔つけられたままになっている抵当権登記の抹消
事例
今年40歳になるAさんは、3年前に亡くなった父から、千葉県市原市にある2000㎡の土地を相続しました。幕張でサラリーマンをしているAさんにとって特に使い道もなかったのでそのまま放置していたところ、市原市の不動産業者から土地を売って欲しいと頼まれました。
使い道のない土地を持て余していたAさんは、まさに「渡りに舟」と思い、さっそく売却の話を進めようと思ったのですが、そこで問題が発覚しました。法務局に行って土地の全部事項証明書(登記簿謄本)を確認したところ、生前に父が土地を担保にお金を借りていたようで、Z興業株式会社を債権者とする2000万円の抵当権設定登記が昭和48年に設定されていました。
当時まだ生まれていなかったAさんにとって、抵当権設定登記がどのような経緯で土地に付けられたものなのか、全く分かりませんでしたが、不動産業者からは「抵当権を抹消してもらってからでないと、土地は買えません。」と言われています。
そこで、Aさんは、稲毛にあるZ興業株式会社の所在地のビルを訪ねてみたのですが、ビルには全く別のテナントが入っていてZ興業株式会社はありませんでした。
Aさんとしては何とかして抵当権設定登記を抹消して、土地を不動産業者に売りたいと思っています。
解決方法
何十年も前に不動産に設定された抵当権の登記がそのままになっているという事案は、ときどき見かけます。登記がそのまま残ってしまっている理由としては、借金を完済しないうちに貸主が倒産してしまった場合、借金を返済し終わったけれども登記を抹消するのを忘れてしまっていた場合、元々執行逃れなどを目的とする実体のない架空の登記であった場合などが考えられます。
消滅時効を援用して抵当権設定登記の抹消手続を請求する
通常のケースであれば、Aさんの場合、亡父が2000万円の借金を完済したという証拠(領収証)などが残っていれば、それを理由にZ興業株式会社に債権の消滅を主張して抵当権登記の抹消手続を請求することができます。しかし、大昔の借金完済の証拠が残っていることなどあまり期待できません。
このような場合には、消滅時効を主張して債権を消滅させることが考えられます。50年近く前の借金であれば、時効期間を過ぎていると考えてほぼ間違いないでしょう。消滅時効による債権の消滅を主張して抵当権登記の抹消手続を請求するのです。
X興業株式会社が応じない(協力してくれない)場合には、X興業株式会社を被告とする抵当権設定登記抹消登記請求の裁判を提起することになります。
ただし、この手続は、現在もX興業株式会社が存在している場合でなければできません。では、本件のようにX興業株式会社が存在していない場合はどのようにすればよいのでしょうか。
裁判所に特別代理人を選任してもらう
X興業株式会社を調査してもその存在が確認できず、実体がないことが明らかになった場合には、裁判所に抵当権設定登記抹消登記手続請求訴訟を提起すると同時に特別代理人選任命令の申立てをして、X興業株式会社の特別代理人を選任してもらうことになります。
通常、特別代理人には、千葉地方裁判所に候補者として登録している千葉県の弁護士が選任されます。なお、特別代理人の費用はAさんが負担する必要があります。通常10万円くらいです。
特別代理人となった弁護士が被告X興業株式会社のために訴訟行為をすることになりますが、余程の新事実が発見されない限りはAさんの勝訴判決が出ます。後は、判決書を使って抵当権設定登記の抹消手続をすればよいのです。
このように、昔つけられてそのままになっている抵当権の登記などは、債権者が存在しなくなっていても、裁判手続を利用することによって抹消することが可能です。
Aさんも抵当権設定登記の抹消登記手続を命じる判決をもらって無事に登記を抹消し、不動産業者に土地を売却することができました。

千葉県・東京23区を中心に活動する秋山慎太郎総合法律事務所です。
私たちは「身近な法律事務所」として、皆様の暮らしの安心を取り戻すお手伝いをしています。
当事務所は、相続、離婚、不動産、交通事故、債務整理、労働事件、刑事事件といった個人案件から、企業間の紛争、債権回収、労務管理等の法人案件、更には分野を特定できない法律問題まで幅広く取り扱う地域密着の総合法律事務所です。
特に、生活に直結する「借金・債務整理」や、突然のトラブルである「交通事故」の分野に力を入れており、豊富な解決実績がございます。法律の専門家として、ご相談者様一人ひとりに親身に寄り添い、迅速な解決を実現することをお約束します。
【借金・交通事故のご相談は初回30分無料】
お困りの際は、一人で悩まずに専門家にご相談ください。お電話やお問い合わせフォームから、まずはお気軽にご連絡いただければ幸いです。
【刑事事件】この程度で暴行罪になるの?
事例
Aは「顧客サービス第一」をモットーに千葉市中央区で飲食店を経営しています。
ある日、従業員Bが接客中にクレーマー体質のお客さんから無理な要求をされたのに腹を立て、お客様に暴言を吐くということがありました。
「顧客サービス第一」をモットーとしていたAは、Bに対してお客様に謝罪するよう言いましたが、Bはこれに応じませんでした。
閉店後、AはBを事務室に呼び出し、Bの顧客に対するサービス精神が欠けているとしてBを説教しましたが、Bがこれを無視して事務室を出て行こうとしたため、Bを引き留めようとBの衣服をつかんで引っ張り、その拍子にBが転倒してしまいました。
Bが千葉中央警察署に被害届を出したため、後日、Aは千葉中央警察署と千葉地方検察庁から事情聴取され、供述調書も作成しました。千葉地方検察庁に行った際、検察官からは示談をすすめられましたが、Aとしては、Bに対する教育の一貫でした行為であること、内容としても衣服をつかんで引っ張った程度であるから「犯罪などというのは大袈裟だ」と思って軽く考えています。本当に大丈夫でしょうか?
回答
上記のような行為でも刑法208条の暴行罪が成立します。検察官から示談をすすめられたということは、検察官は被害者Bの供述も踏まえて、Aの行為を暴行罪に該当すると判断していることは明らかです。軽く考えてはいけません。仮にAに前科がなかったような場合でも、Aは略式起訴されて罰金刑に処せられる可能性が高いです。Aが暴行に至った事情は、情状として考慮されますが、それは量刑(罰金の金額)に影響するだけで、不起訴となる訳ではありません。
<刑法208条>
暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
罰金も前科となります。これを回避するには一刻も早く被害者Bに誠実に謝罪し、示談する必要があります。
示談が成立すれば、検察官がAを不起訴処分とする可能性が高くなります。
<解説>暴行罪にいう「暴行」とは?
刑法208条にいう暴行とは,人の身体に対する不法な有形力の行使をいいます。
典型的なものとしては,殴る,蹴る,突く,押す,投げ飛ばすなど,身体への接触を伴う物理力を行使する行為です。過去には人の毛髪を不法に裁断する行為を暴行罪とした判例もあります(大判明45・6・20刑録18-896)。
また,刑法208条の暴行は,相手の五感に直接間接に作用して不快ないし苦痛を与える性質のものであれば,人の身体に向けられたものであれば足り,必ずしもそれが人の身体に直接接触することを要しないとされています。例えば,命中しなくても,通行人の数歩手前をねらって石を投げ付ける行為,人の乗っている自動車に石を投げて命中させ,ガラスを破損する行為,狭い四畳半の室内で日本刀の抜き身を振り回す行為,車両を衝突させるかのような気勢を示しながら,人に向かって走行させ,その身体に近接させる行為などにも暴行罪が成立します。
更に,音響,光,電気,熱等のエネルギーの作用を人に及ぼすことも有形力の行使に含まれるとされています。例えば,近くで太鼓や鉦等を連打し,頭脳の感覚が鈍り意識朦朧とした気分を与え,または脳貧血を起こらせる程度にさせるような行為,拡声器を用いて耳元で大声を発する行為などにも暴行罪が成立します。

千葉県・東京23区を中心に活動する秋山慎太郎総合法律事務所です。
私たちは「身近な法律事務所」として、皆様の暮らしの安心を取り戻すお手伝いをしています。
当事務所は、相続、離婚、不動産、交通事故、債務整理、労働事件、刑事事件といった個人案件から、企業間の紛争、債権回収、労務管理等の法人案件、更には分野を特定できない法律問題まで幅広く取り扱う地域密着の総合法律事務所です。
特に、生活に直結する「借金・債務整理」や、突然のトラブルである「交通事故」の分野に力を入れており、豊富な解決実績がございます。法律の専門家として、ご相談者様一人ひとりに親身に寄り添い、迅速な解決を実現することをお約束します。
【借金・交通事故のご相談は初回30分無料】
お困りの際は、一人で悩まずに専門家にご相談ください。お電話やお問い合わせフォームから、まずはお気軽にご連絡いただければ幸いです。
【労働】有給休暇の買上げを請求できるか?
年次有給休暇とは
労働基準法の年次有給休暇制度は,労働者の健康で文化的な生活の実現に資するために,労働者に対し,休日のほかに毎年一定日数の休暇を有給で保障する制度です(菅野和夫著『労働法』)。
労働者が6か月継続勤務し,その間の全労働日の8割以上出勤した場合には、労働者の勤続期間に応じた日数の年休権が発生します(労働基準法39条)。労働者は使用者に対し,具体的な時季を指定して有給休暇の請求をすることができます。
また,労働者が時季指定しなかったために未消化となった年休は,2年の時効(労働基準法115条)の範囲で翌年に繰越しできるものとされています。
年次有給休暇の買上げ
使用者が労働者に対し,未消化の年休日数に応じた手当を支給することを,俗に年次有給休暇の買上げといいます。
使用者と労働者との間で年次有給休暇の買上げについて合意することは特に問題はありません。但し,その合意が,使用者が手当を支払う代わりに労働者の年休取得を認めない趣旨を含むものである場合には,年次有給休暇の保障に反し違法とされます。
労働者から年次有給休暇の買上げを請求することはできるか
使用者に年休買上げの義務はありませんので,労働者から年休の買上げを請求することはできません。
但し,例えば,会社において,退職者の年休残日数の買上げが制度化されていたり,慣行となっているような場合には,使用者に年休買上げの義務が生じることになりますので,年休の買上げを請求することができます。
使用者から年次有給休暇の買上げを請求することはできるか
時効にかかっていない在職者の年休を買い上げるのは違法です。労働者の年休取得を認めないことになり制度趣旨に反するからです。
他方,既に時効にかかっている在職者の年休や,退職者の年休の残日数を買い上げることは,もはや労働者が使用できないものですから,適法となります。

千葉県・東京23区を中心に活動する秋山慎太郎総合法律事務所です。
私たちは「身近な法律事務所」として、皆様の暮らしの安心を取り戻すお手伝いをしています。
当事務所は、相続、離婚、不動産、交通事故、債務整理、労働事件、刑事事件といった個人案件から、企業間の紛争、債権回収、労務管理等の法人案件、更には分野を特定できない法律問題まで幅広く取り扱う地域密着の総合法律事務所です。
特に、生活に直結する「借金・債務整理」や、突然のトラブルである「交通事故」の分野に力を入れており、豊富な解決実績がございます。法律の専門家として、ご相談者様一人ひとりに親身に寄り添い、迅速な解決を実現することをお約束します。
【借金・交通事故のご相談は初回30分無料】
お困りの際は、一人で悩まずに専門家にご相談ください。お電話やお問い合わせフォームから、まずはお気軽にご連絡いただければ幸いです。
【相続】「相続財産」に含まれるもの、含まれないもの
遺産を相続するか放棄するかは、定められた期間に決定しなければなりません。しかし、相続財産の範囲を把握しなければ、その決定は下しにくいと思います。
今回は、どのようなものが相続財産に含まれるのか、どのようなものが相続財産に含まれないのかについて、ご説明します。
相続財産とは
民法896条本文には以下のように規定されています。
「相続人は、相続開始のときから、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する」
このことからわかるように相続人は、被相続人の権利とともに義務も承継することになっています。それはつまり、被相続人が所有していた土地や現金などの「プラスの財産」と一緒に被相続人が負っていた借金・債務などの「マイナスの財産」も相続するということです。
相続は被相続人が死亡した時点で開始され、手続がなくても、遺産はその時点で相続人に承継されます。
積極財産
「プラスの財産」は、積極財産と呼ばれます。
- 不動産(土地・建物・立木)
海外にあるものも含まれます。
- 動産
自動車・家財道具・コレクション品等
- 現金・預貯金
- 有価証券など
株式、投資信託、国債や地方債、施設などの会員権
但し、会員権の場合は、会員規約に「会員が死亡の場合、会員権は失効」などと規定されていれば承継できません。
- 借地権・借家権
なお、使用借権は、被相続人が亡くなると消滅してしまいますので承継できません(民法599条)。
- その他
知的財産権なども積極財産として承継されます。
消極財産
被相続人が負っていた借金などの「マイナスの財産」が消極財産です。これらのものもすべて承継されます。
- 債務
銀行や消費者金融からの借入れといったいわゆる借金はもちろん、クレジットカードで購入した商品の支払いや、未払いになっている賃料、固定資産税や住民税などの滞納分の支払義務も相続人に継承されます。
- 保証債務
通常の保証債務は、相続人に継承されます。
人的信用関係を基礎とする信用保証(根保証など)や身元保証は継承されないものとされています。
相続財産に含まれないもの
前述のとおり、相続が開始すると、被相続人の財産に属した一切の権利義務は、相続人がすべて承継するのが原則ですが、相続財産に属さない財産・権利も存在します。
- 一身専属権
冒頭の民法第896条但書には、以下のように規定されています。
「ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りでない。」
一身専属権とは、その性質上、特定の人にだけ帰属する権利、特定の人だけが行使できる権利です。
例えば、生活保護法に基づく保護受給権や、年金請求権、財産分与請求権、扶養請求権などです。但し、既に履行期を経過して具体的な請求権となっていた場合には、一般の金銭債権と変わらないため、相続の対象となります。
また、作家や画家が作品を作る債務などの交代が効かない債務のような一身専属義務も相続されません。
- 墓・位牌・仏壇などの祭祀財産
祭祀財産は、祖先の祭祀の主宰者が継承することになりますので(民法897条)、相続財産には含まれません。
- 遺骨
遺骨も祭祀の主宰者に帰属するため、相続財産には含まれません。
- 香典
香典は、祭祀主宰者への贈与と考えられるため、相続財産には含まれません。
- 身分上の権利
身分上の地位や権利などは相続財産に含まれません。被相続人が婚約していた場合の「婚約者」としての地位などがこれにあたります。婚約者の立場が継承されることはありません。
相続が開始された際、3か月以内に相続放棄をするか否か検討する前提として、相続財産の中にどの程度の消極財産があるのかを確認することはもちろんですが、そもそも何が相続財産なのか、何が相続財産ではないのかを知っておく必要があります。特に祭祀財産は、相続放棄しても祭祀の主宰者であれば継承することができるということを知っておいてください。

千葉県・東京23区を中心に活動する秋山慎太郎総合法律事務所です。
私たちは「身近な法律事務所」として、皆様の暮らしの安心を取り戻すお手伝いをしています。
当事務所は、相続、離婚、不動産、交通事故、債務整理、労働事件、刑事事件といった個人案件から、企業間の紛争、債権回収、労務管理等の法人案件、更には分野を特定できない法律問題まで幅広く取り扱う地域密着の総合法律事務所です。
特に、生活に直結する「借金・債務整理」や、突然のトラブルである「交通事故」の分野に力を入れており、豊富な解決実績がございます。法律の専門家として、ご相談者様一人ひとりに親身に寄り添い、迅速な解決を実現することをお約束します。
【借金・交通事故のご相談は初回30分無料】
お困りの際は、一人で悩まずに専門家にご相談ください。お電話やお問い合わせフォームから、まずはお気軽にご連絡いただければ幸いです。