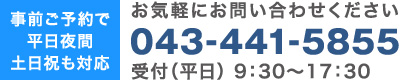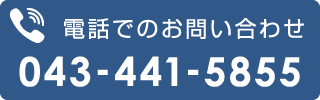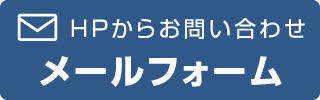Archive for the ‘千葉の弁護士コラム’ Category
【相続】内縁関係の夫や妻は、相続することはできないの?
「内縁の妻(夫)」と言ったら「愛人のようなもの」という認識をしている方がいるかもしれません。確かに内縁関係の妻や夫は法的には婚姻関係にある相手ではありませんが「愛人」と「内縁の妻(夫)」とでは、法的に保護を受けられる範囲がまったく異なります。婚姻関係にある人と比べれば保護を受けられる範囲は限定されますが「内縁の妻(夫)」であっても被相続人の遺産を受け取ることができる場合があります。
ここでは「内縁の妻(夫)」の法的な位置づけと、「内縁の妻(夫)」が被相続人の遺産を受け取ることができる場合についてご紹介します。
内縁の妻(夫)とは
「内縁の妻(夫)」(以下「内縁配偶者」といいます。)とは、「一緒に夫婦生活を送っているなど事実上婚姻の社会的実体はあるが、婚姻届が提出されておらず、法律上は配偶者として認められていない妻(夫)」のことをいいます。
法律上は婚姻関係が認められていないため、税金、保険、年金などに関して、結婚することで得られる優遇を受けることはできません。しかし、内縁配偶者も法律上「婚姻に準ずる関係」にあるとされ、法的保護を受けられるケースもいくつかあります。
ちなみに愛人は「一方もしくは両方が既婚者でありながら交際を続けること」と定義されます。いわゆる不倫関係であり、不倫関係に関しては法的な保護はありません。
内縁配偶者の権利義務
内縁配偶者には、法的に婚姻関係者と同等の権利義務が認められています。
・貞操の義務
・同居、協力、扶助義務(民法752条)
・婚姻費用分担義務(民法760条)
・日常家事債務の連帯責任(民法761条)
・夫婦別産制と帰属不明財産の共有推定(民法762条)
・財産分与(民法768条)
・不当な破棄への救済(慰謝料)
・第三者の不法行為に対する救済(内縁の配偶者に対する生命侵害、第三者との性的関係)
他方、内縁配偶者には認められないものとして、次のものがあります。
・氏の変更(民法750条)
・成年擬制(民法753条)
・子の嫡出性(民法772条)
・親権の所在(非嫡出子の親権者は原則として母)
・姻族関係の発生
・相続権
内縁配偶者が、被相続人の遺産を受け取ることができる場合
内縁配偶者には相続権はありません。相続権がないということは、内縁配偶者は相続人にはなれないということです。
しかし、相続人にはなれませんが、内縁配偶者が被相続人の財産を取得できる場合があります。
・居住用建物の賃借権の承継
居住用の建物の賃借人が相続人なしに死亡した場合には、被相続人の内縁配偶者(および事実上の養子)は、被相続人の借家権という財産を承継することができるので、そのまま借家に住み続けることができます(借地借家法36条)。
なお、相続人がいる場合には、借家権は相続人が相続することになりますが、判例上、内縁配偶者は相続人の借家権を援用して居住の権利を主張することが認められています。
・特別縁故者
特別縁故者とは「被相続人と生計を同じくしていた者、被相続人の療養看護に努めた者その他被相続人と特別の縁故があった者」のことです。被相続人に相続人がいない場合には、所定の手続きを経て家庭裁判所に特別縁故者と認められれば、遺産の全部または一部を受け取ることができるようになります。
具体的には、相続人不存在(相続人が相続放棄をしたなどで、相続人が一人もいない状況)による相続財産管理人選任の申立てをし、相続財産管理人による相続人捜索の公告期間の満了後3か月以内に「特別縁故者に対する財産分与の申立て」をすることになります。
家庭裁判所は、特別縁故者に対する財産分与の申立てがあると、相続財産管理人や家庭裁判所調査官の意見を踏まえた上で、特別縁故者に該当するか否か、該当するとして遺産の全部を分与すべきか、一部を分与すべきかを判断します。
・遺言書
被相続人の意思が尊重される遺言書は、遺産相続において大きな意味を持ちます。遺言書に自分の財産を内縁配偶者に遺贈することを書いておけば、内縁配偶者は、遺産を受け取ることができるようになります。
このように、内縁配偶者には婚姻関係者と同等の保護が与えられてはいますが、相続権はありません。そのため、自分が亡くなった後の内縁配偶者の保護を考えるならば、遺言書を作成しておくことが極めて重要です。
婚姻届を提出するかどうかは自由です。しかし、その際は自分が亡くなった後の内縁配偶者の生活にも思いを巡らせておいた方が良いでしょう。ここで紹介したことを参考にしてみてください。

千葉県・東京23区を中心に活動する秋山慎太郎総合法律事務所です。
私たちは「身近な法律事務所」として、皆様の暮らしの安心を取り戻すお手伝いをしています。
当事務所は、相続、離婚、不動産、交通事故、債務整理、労働事件、刑事事件といった個人案件から、企業間の紛争、債権回収、労務管理等の法人案件、更には分野を特定できない法律問題まで幅広く取り扱う地域密着の総合法律事務所です。
特に、生活に直結する「借金・債務整理」や、突然のトラブルである「交通事故」の分野に力を入れており、豊富な解決実績がございます。法律の専門家として、ご相談者様一人ひとりに親身に寄り添い、迅速な解決を実現することをお約束します。
【借金・交通事故のご相談は初回30分無料】
お困りの際は、一人で悩まずに専門家にご相談ください。お電話やお問い合わせフォームから、まずはお気軽にご連絡いただければ幸いです。
【相続】故人が誰かの保証人になっていた場合、相続人はどうなるの?
遺産相続で相続人が故人から受け取る財産には、プラスのものとマイナスのものとがあります。
プラスのものとは故人の現金や預貯金、不動産などです。マイナスのものとは故人の借金などの債務です。
それでは、故人が生前に誰かに頼まれて保証人になっていたような場合も、相続人はマイナスの財産である保証債務を引き継がなければならないのでしょうか。
保証人の地位は相続によってどうなる?
結論から申し上げると、相続人は、故人の保証人の地位も相続することになりますので、後で述べる一部の保証債務を除き、原則として保証債務は引き継がなければなりません。
よくあるのは、故人が友人に頼まれて借金の連帯保証人になっていた場合や友人がアパートやマンションの部屋を借りる際の連帯保証人になっていた場合ですが、いずれも相続によって連帯保証人の地位は引き継がれることになります。
相続人は、故人の連帯保証人としての責任を負わなければなりませんので、故人の友人が借金の返済を怠ったり、家賃を滞納した場合には、金融機関や大家さんから相続人のところへ請求が来ることになります。
【例外的に相続の対象とはならない保証債務】
身元保証の場合
会社に入社する際などに求められる身元保証の場合、身元保証人の地位は相続されません。身元保証契約は、入社した人が会社に損害を与えた場合などに、身元保証人がその損害を賠償するというものですが、その性質上、入社した人と身元保証を引き受けた人との間に強い信頼関係があることが前提とされています。入社した人と故人との間に強い信頼関係があったとしても、故人の相続人との間には信頼関係がないことの方が通常ですので、身元保証人としての地位は相続されないことになっているのです。なお、故人が亡くなる前に、既に会社に対する損害賠償責任が発生してしまっていたような場合には、その賠償義務は相続の対象となりますので、注意が必要です。
根保証の場合
継続的取引により将来発生する債務について保証することを根保証といいます。根保証の場合、限度額や期間に定めがない場合には、特段の事情のない限り相続の対象とはならないとされています。限度額や期間の定めがないような根保証は、債務者と故人との間に強い信頼関係があるはずであり、債務者と相続人との間にまで強い信頼関係がないことの方が通常だからです。ただし、故人が亡くなる前に、既に発生している債務については相続の対象となりますので、注意が必要です。
故人が誰かの保証人だったら
故人が誰かの借金などの保証人になっていた場合は、故人が実際に借金をしているわけではないため、そのことを周囲に話していなかったということがよくあります。そのため、故人が亡くなって数年してから、その事実が明らかになるというケースも多く見受けられます。
仮に借金の額が膨大で、とても払いきれそうにない場合には、相続放棄を検討する必要が出てきます。
相続開始から何年も経過しているのに相続放棄ができるのかと不安に思う方もあるかもしれませんが、相続放棄は一般的に「保証債務などの存在を知ってから3か月以内」であれば認められます。その際には、それまで保証債務の存在を知らなかったことを明らかにすることが必要です。
ただし、遺品整理などで故人の財産を処分していたなどの事実があった場合には、単純承認をしたものとみなされて相続放棄が認められないケースもあります。故人が誰かの保証人であるという事実が明らかになった場合は専門家に相談するようにしましょう。
以上述べてきましたとおり、故人の保証人の地位は、原則として相続されることになりますが、場合によっては相続放棄することが可能です。無用なトラブルに巻き込まれないよう、故人の遺品整理をする際は生前の交友関係、書類などを調べ、故人が誰かの保証人になっていないかどうか、しっかりと確認しておくようにしましょう。

千葉県・東京23区を中心に活動する秋山慎太郎総合法律事務所です。
私たちは「身近な法律事務所」として、皆様の暮らしの安心を取り戻すお手伝いをしています。
当事務所は、相続、離婚、不動産、交通事故、債務整理、労働事件、刑事事件といった個人案件から、企業間の紛争、債権回収、労務管理等の法人案件、更には分野を特定できない法律問題まで幅広く取り扱う地域密着の総合法律事務所です。
特に、生活に直結する「借金・債務整理」や、突然のトラブルである「交通事故」の分野に力を入れており、豊富な解決実績がございます。法律の専門家として、ご相談者様一人ひとりに親身に寄り添い、迅速な解決を実現することをお約束します。
【借金・交通事故のご相談は初回30分無料】
お困りの際は、一人で悩まずに専門家にご相談ください。お電話やお問い合わせフォームから、まずはお気軽にご連絡いただければ幸いです。
【相続】相続人を確定する手順は?
遺産分割協議は相続の資格がある人すべてが含まれた状態でおこなわれなければなりません。相続人(相続の資格がある人)が一人でも遺産分割協議に含まれていなければ、その遺産分割協議は無効になりますし、逆に遺産分割協議に相続人ではない人が含まれていても無効になります。そのため、遺産分割協議をする際には、事前にきちんと相続人の確定をする必要があるのです。
ここでは、相続人を確定するための方法や手順をご紹介します。
相続人調査をする方法
相続人を確定するには、何よりも相続人の調査が必要です。そのためには、被相続人の死亡が記載されている戸籍(除籍)謄本から、被相続人の出生についての記載がある除籍謄本もしくは改製原戸籍謄本までさかのぼって調べていかなくてはなりません。現在の戸籍だけでは被相続人の婚姻歴や子どもの有無などが確認できないこともあり、婚外子などが存在する可能性もあるからです。
戸籍(除籍)謄本は、先ずは被相続人の本籍地の市区町村で交付を受けることになります。
戸籍調査の手順
では次に、戸籍調査の手順を紹介しましょう。
ここでは、Aさんという人物を例に紹介します。
①Aさんの本籍地の市区町村からAさんの戸籍(除籍)謄本を取り寄せます。本籍地が不明の場合は、「住民票の除票」というものを「本籍地表示あり」という条件を付けて取り寄せ、本籍地を確認します。
②取り寄せた戸籍(除籍)謄本を調べ、もしもそこに「平成〇〇年〇月〇日千葉県佐倉市より転籍」などと記載があれば、転籍する以前の市区町村へ、戸籍謄本を請求します(この場合は佐倉市)。
③佐倉市から取り寄せた戸籍謄本に「平成〇〇年〇月改製」などとあれば、その戸籍謄本からでは改製前の内容が分からないので、更に改製原戸籍謄本を請求します。
④改製原戸籍謄本に「昭和〇〇年に千葉県市原市より転籍」などとあれば、今度はその市区町村(ここでは市原市)に戸籍謄本を請求します。
このように、戸籍調査をする際は、新しい物から古い物へさかのぼって調査するのがポイントです。
相続人の確定
被相続人Aさんの戸籍調査の過程で、Aさんの配偶者や子ども(Bさん・Cさん)が明らかになったら、今度はBさん・Cさんの戸籍謄本を取り寄せます。Bさん・CさんがそのままAさんの戸籍に一緒に入っていれば良いのですが、例えば結婚してAさんの戸籍から除籍となり別の戸籍に転籍している場合などは、転籍先の戸籍謄本を取り寄せます。このようにしてBさん・Cさんの現在の戸籍謄本まで辿りつきます。Bさん・Cさんが存命であれば、Aさんの配偶者とBさん・Cさんが相続人として確定します。
仮にBさんがAさんより先に亡くなっていた場合には、Bさんの子ども(Dさん)がAさんの代襲相続人として遺産分割協議に参加することになりますので、同様にDさんの現在の戸籍謄本に辿りつくまで戸籍謄本を取り寄せます。
仮にCさんがAさんの後で亡くなっていた場合には、CさんはAさんの相続人の資格を得た後に亡くなったことになりますので、Cさんの相続人を同様に調査し、Cさんの相続人(配偶者や子ども)がAさんの遺産分割協議に参加することになります。
このようにして、最終的にAさんの相続人を確定します。
なお、相続人の中に行方不明者(不在者)がいて、いくら調べても生存や行方が分からないといった場合もあります。その場合は、不在者の従来の住所地もしくは居所地の家庭裁判所に「不在者財産管理人」の選任を申し立て、選任された「不在者財産管理人」に遺産分割協議に参加してもらうことになります。
以上が相続人を確定するための大まかな手順の流れになります。参考にしてください。
遺産相続はいろいろとトラブルが起きやすいものです。何かわからないことがある場合はすぐに専門家や専門機関に相談することをおすすめします。

千葉県・東京23区を中心に活動する秋山慎太郎総合法律事務所です。
私たちは「身近な法律事務所」として、皆様の暮らしの安心を取り戻すお手伝いをしています。
当事務所は、相続、離婚、不動産、交通事故、債務整理、労働事件、刑事事件といった個人案件から、企業間の紛争、債権回収、労務管理等の法人案件、更には分野を特定できない法律問題まで幅広く取り扱う地域密着の総合法律事務所です。
特に、生活に直結する「借金・債務整理」や、突然のトラブルである「交通事故」の分野に力を入れており、豊富な解決実績がございます。法律の専門家として、ご相談者様一人ひとりに親身に寄り添い、迅速な解決を実現することをお約束します。
【借金・交通事故のご相談は初回30分無料】
お困りの際は、一人で悩まずに専門家にご相談ください。お電話やお問い合わせフォームから、まずはお気軽にご連絡いただければ幸いです。
【相続】離婚と相続
日本の離婚率は年々高くなっており、離婚は決して珍しいことではなくなっています。離婚する際には財産分与や慰謝料、養育費などのお金の問題を取り決めることになりますが、将来相続が発生した場合のことについてまで考えることは少ないもの。相続が起こる段階になってトラブルとなる場合もあります。ここでは、離婚と相続についてのポイントをご説明します。
離婚した元配偶者は相続人にはならない
民法では、亡くなった人に配偶者がいる場合、配偶者は常に相続人となると定めています。この場合の配偶者とは、あくまでも婚姻関係にある相手のことです。事実婚すなわち内縁関係の相手は、どんなに長くその関係にあったとしても相続人とはなりません(遺言により遺贈を行うことは可能です)。
かつて婚姻関係にあった元配偶者も、相続が発生した時点で婚姻関係にない以上、相続人とはなりません。離婚した時点で元配偶者に相続権はなくなるのです。
親が離婚しても子どもには相続権がある
離婚した場合に元配偶者は相続人とはなりませんが、相手との間に子がいる場合、その子は相続人となります。民法では、子は第一順位の相続人と定められています。たとえ両親が離婚して他人になったとしても、親子の関係がなくなるわけではありませんので、どちらが親権者になったのかとか、どちらと同居していたのかなどに関わらず、子は相続人となるのです。実際に「何十年も音信不通だった親が亡くなったということで、遺産相続の件で連絡が来た」あるいは逆に「遺産相続の件で前妻の子どもと連絡を取らなければならなくなった」というケースは少なくありません。
連れ子に相続権が発生するかは養子縁組の有無で決まる
では、結婚相手に子どもがいる場合、いわゆる「連れ子」に相続権は発生するのでしょうか。連れ子と義理の親との間にはそのままでは法律上の親子関係はありませんので、連れ子の親が結婚したからといって自動的に義理の親の相続人となるわけではありません。義理の親と連れ子は、養子縁組をしてはじめて法律上の親子関係が生じ、相続人となるのです。
離婚する際には、連れ子との離縁も必要?
逆に、結婚相手の連れ子と養子縁組をしていた場合、離婚しただけでは連れ子は養子として相続権を有することになります。元配偶者とは別れたが、養子縁組をした連れ子には愛情があり、是非とも財産を遺してやりたいという場合であれば良いのですが、そうでないならば、離婚をする際には同時に連れ子とも離縁しておかないと、後々トラブルに発展してしまう可能性がありますので注意が必要です。

千葉県・東京23区を中心に活動する秋山慎太郎総合法律事務所です。
私たちは「身近な法律事務所」として、皆様の暮らしの安心を取り戻すお手伝いをしています。
当事務所は、相続、離婚、不動産、交通事故、債務整理、労働事件、刑事事件といった個人案件から、企業間の紛争、債権回収、労務管理等の法人案件、更には分野を特定できない法律問題まで幅広く取り扱う地域密着の総合法律事務所です。
特に、生活に直結する「借金・債務整理」や、突然のトラブルである「交通事故」の分野に力を入れており、豊富な解決実績がございます。法律の専門家として、ご相談者様一人ひとりに親身に寄り添い、迅速な解決を実現することをお約束します。
【借金・交通事故のご相談は初回30分無料】
お困りの際は、一人で悩まずに専門家にご相談ください。お電話やお問い合わせフォームから、まずはお気軽にご連絡いただければ幸いです。
【相続】どんな分け方がある? 遺産分割の方法
遺産相続の際、遺言書があればそれに従って遺産を分割するのが原則ですが、遺言書がない場合、あるいは遺言書があっても遺言書に記載されていない遺産がある場合には、遺産分割協議が必要となります。遺産分割協議の際には、無用なトラブルを避けるためにも、具体的な遺産分割の方法を知っておく必要があります。
ここでは、遺産相続の際の「遺産分割の方法」についてご紹介します。
方法その1:現物分割
現物分割とは、個々の財産の形状や性質を変更することなく、遺産をそのまま各相続人に割り当てていくという方法です。
例えば「預金は妻に」「不動産は長男に」「現金と自動車は次男に」などというように分けることができれば、最も単純で分かりやすく、手続も簡単に行えますが、この場合、公平か否かをひと目で判断できないという難点があります。相続人同士の強い信頼関係と譲り合いの気持ちが必要です。
不動産の場合、公平性を重視して、土地であれば分筆、建物であれば区分して各相続人が取得するということも考えられますが、この場合、土地については地積測量図、建物については建物図面及び各階平面図を用いて取得部分を特定する必要があります。また、建築関係の法令等の確認も必要となります。
方法その2:代償分割
代償分割とは、一部の相続人に法定相続分を越える額の財産を取得させた上、他の相続人に対する債務を負担させるという方法です。例えば、相続人の1人が不動産を全部取得する代わりに、他の相続人に対して、各自の法定相続分に相当する金銭(代償金)を支払うという方法です。
現物分割が不可能な場合、現物分割をすると遺産の価値が損なわれてしまう場合、特定の相続人に特定の遺産を取得させる必要がある場合などに有用な分割方法です。
但し、代償分割の対象となる財産の評価をいくらと見るのかによって、支払うべき代償金の額が変わってきますので、この点で争いになることがあります。また、代償金が多額になると、そもそも高額な代償金を準備できるか否かという資力の問題も出てきます。
方法その3:換価分割
換価分割とは、不動産や株式といった遺産を売却等で換金した後に、それを分配するという方法です。
遺産を換金してしまうことで価値が明確になりますので、現物分割による不公平感や代償分割による財産の評価の問題は解消されますが、遺産に思い入れがある場合には、それを手放さなければならないという難点があります。また、常時価格が変動する株式などは、売却の時期についてもきちんと合意しておく必要があります。
方法その4:共有分割
共有分割とは、遺産の一部、遺産の全部を具体的相続分による物権法上の共有取得とする方法です。ある意味公平な分割方法ですが、将来的に共有状態を解消するには、改めて共有物分割請求をする必要がありますので、問題解決を先送りしているだけという感が否めません。因みに、家庭裁判所の審判では「現物分割」「代償分割」「換価分割」「共有分割」の順に検討することになっており、共有分割は限定的な場合にしか認められません。
遺産分割には、以上にご紹介した4つの方法があります。これらの枠組みの中で、更に具体的にどのように分割するのかを相続人同士で話し合うことになります。相続人同士の話合いで解決できない場合には、早めに弁護士に相談することをお勧めします。

千葉県・東京23区を中心に活動する秋山慎太郎総合法律事務所です。
私たちは「身近な法律事務所」として、皆様の暮らしの安心を取り戻すお手伝いをしています。
当事務所は、相続、離婚、不動産、交通事故、債務整理、労働事件、刑事事件といった個人案件から、企業間の紛争、債権回収、労務管理等の法人案件、更には分野を特定できない法律問題まで幅広く取り扱う地域密着の総合法律事務所です。
特に、生活に直結する「借金・債務整理」や、突然のトラブルである「交通事故」の分野に力を入れており、豊富な解決実績がございます。法律の専門家として、ご相談者様一人ひとりに親身に寄り添い、迅速な解決を実現することをお約束します。
【借金・交通事故のご相談は初回30分無料】
お困りの際は、一人で悩まずに専門家にご相談ください。お電話やお問い合わせフォームから、まずはお気軽にご連絡いただければ幸いです。
【借金】保証人と連帯保証人の違いって? それぞれの役割は?
お金を借りるときに銀行などの金融機関から求められる「連帯保証人」。
一般的には単に「保証人」と言っているかもしれませんが、単なる「保証人」と「連帯保証人」とでは、その責任の重さが異なります。
ここでは「保証人」と「連帯保証人」の違いについてご紹介します。
保証人の役割
保証人とは、債権者(お金を貸している人)に対して、万一債務者(お金を借りている人)が約束どおりの返済をしないときに、債務者に代わって返済をおこなうという約束をした人のことを言います。なお、保証契約は書面でしなければ無効となります。
保証人には「催告の抗弁権」「検索の抗弁権」「分別の利益」があります。それぞれの内容は以下のとおりです。
【催告の抗弁権】(民法452条)
債権者に対して、まずはお金を借りている張本人である債務者に対して催告するよう請求できる権利です。仮に債権者が保証人に債務者の借金を代わりに支払うよう請求してきたとしても、債務者が破産手続の開始決定を受けていたり、行方不明になっていたりしない限り、まずは自分ではなく債務者に請求するよう求めることができるのです。
【検索の抗弁権】(民法453条)
債権者が、先程の保証人からの「催告の抗弁」に従って債務者に催告をしたものの、やはり債務者は返済をしないということで、保証人に支払を請求してきた場合に、保証人が債務者には返済する資力があり、執行も容易であることを証明すれば、債権者は保証人ではなく債務者の財産に執行しなければならないということになっています。
債務者が、返済能力があるにもかかわらず借金の返済を拒んでいるという場合には、保証人は債権者に対して「まずは債務者から返済してもらいなさい」「まずは債務者の財産を差し押さえなさい」と言って支払を拒むことができるのです。
【分別の利益】(民法456条)
保証人が複数いる場合、保証人は債務者の借金の全額ではなく、保証人の人数で分割した額だけ負担すればよいということになっています。つまり、債務者が200万円の借金をしていたとして、その際に保証人が2人いた場合、保証人は200万円全額を返済する必要はなく、200万円を2人で割った100万円ずつの返済義務を負うということです。
連帯保証人の役割
これに対して、連帯保証人は、前述した「催告の抗弁権」「検索の抗弁権」がありません(民法454条)。
「保証人」が「万一債務者が返済できなくなったとき」にのみ支払う義務を負うのに対し、「連帯保証人」は債務者に返済能力があっても、債権者からの請求を拒否することができないのです。つまり「連帯保証人」の負う責任は債務者と同じ、すなわち自分自身が借金したのと同じ立場に立つことになるのです。
「連帯保証人」が複数いる場合も、「保証人」が複数いる場合とは異なり、人数で分割した額だけ負担すればよいという訳ではなく、連帯保証人の一人ひとりが、債務者の借金の全額について責任を負うことになります。
このように、連帯保証人は通常の保証人と比べてはるかに責任が重いのです。
「保証人」と「連帯保証人」はまったく異なるものです。
とは言え単なる「保証人」であっても、他人の借金の返済義務を負うことに変わりはありません。知人から保証人になって欲しいと頼まれたときには、安易に了承せず、じっくりと検討してから決めるようにしてください。

千葉県・東京23区を中心に活動する秋山慎太郎総合法律事務所です。
私たちは「身近な法律事務所」として、皆様の暮らしの安心を取り戻すお手伝いをしています。
当事務所は、相続、離婚、不動産、交通事故、債務整理、労働事件、刑事事件といった個人案件から、企業間の紛争、債権回収、労務管理等の法人案件、更には分野を特定できない法律問題まで幅広く取り扱う地域密着の総合法律事務所です。
特に、生活に直結する「借金・債務整理」や、突然のトラブルである「交通事故」の分野に力を入れており、豊富な解決実績がございます。法律の専門家として、ご相談者様一人ひとりに親身に寄り添い、迅速な解決を実現することをお約束します。
【借金・交通事故のご相談は初回30分無料】
お困りの際は、一人で悩まずに専門家にご相談ください。お電話やお問い合わせフォームから、まずはお気軽にご連絡いただければ幸いです。
【相続】遺言書に自分の名前がない場合は諦めるだけなの?(遺留分侵害額請求権)
遺産相続の際に大きな意味を持つ遺言書。そこに名前があれば、本来は相続権のない内縁の妻や夫でも、遺産を受け取ることができるようになります。
では、もしも相続人の立場にありながら遺言書に自分の名前がなかったら、その人は相続を諦めなければならないのでしょうか。
遺言書に名前がない、という問題は遺産相続においてよく発生します。
ここでは、遺言書に自分の名前がない場合における相続人の権利についてご紹介します。
相続人には遺留分がある!
遺言書に自分の名前がなかった場合でも、被相続人の兄弟姉妹以外の相続人(配偶者、子、親)であれば、法律で定められた最低限の遺産を受け取る権利があります。それを遺留分と呼びます。
本来、被相続人には自分の財産を自由に処分する権利があります。被相続人が特定の相続人に全財産を相続させたり、第三者に全財産を贈与したり遺贈したりすることは、被相続人の自由であり、相続人が口を挟むことではありません。しかし、これによって相続人の相続分に対する正当な期待が裏切られ、相続人の生活が脅かされるような事態になることは、決して好ましいことではありません。
そこで、被相続人の自由な財産処分と相続人の保護との調和の観点から、遺言でも侵し得ない、相続人の最低限の取得分の確保を目的として定められたのが遺留分という制度です。
相続人は、遺言書に自分の名前がなかったとしても、遺留分侵害額請求権を行使して、法律で定められた割合の遺産を取得することができるのです。
遺留分の割合
遺留分の割合については民法1028条で以下のように定められています。
① 直系尊属のみが相続人である場合 被相続人の財産の3分の1
② 前号に掲げる場合以外の場合 被相続人の財産の2分の1
被相続人の父母や祖父母などの直系尊属のみが相続人の場合(被相続人に配偶者や子どもがいない場合)は①に該当し、遺留分割合は3分の1。相続人が配偶者や子どもの場合は②に該当し、遺留分割合は2分の1になります。例えば、相続人が妻と子ども3人の場合には、妻の遺留分割合は4分の1、子どもの遺留分割合は各12分の1となります。
遺留分侵害額請求の方法
では、遺留分はどのようにして請求するのでしょうか。
遺留分は、受遺者および受贈者に対して遺留分侵害額請求の意思表示をします。遺留分侵害額請求は、口頭でも書面でもおこなうことができますが、請求したことを証拠に残しておくために内容証明郵便で通知した方が良いでしょう。なぜなら、遺留分侵害額請求権には消滅時効があるからです。民法1042条は「減殺の請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知った時から1年間行使しないときは、時効によって消滅する。」と定めています。以後は、遺留分を請求することができなくなってしまうのです。
遺留分侵害額請求の意思表示は、できるだけ早めに内容証明郵便で通知するようにしましょう。
以上のように、相続人には遺留分が認められており、遺言書に名前がなかった場合でも、相続財産に対して最低限の割合は確保することができます。
遺言書に自分の名前がなかったと言う方も、ここで紹介したことを参考に、落ち着いて対処するようにしてください。

千葉県・東京23区を中心に活動する秋山慎太郎総合法律事務所です。
私たちは「身近な法律事務所」として、皆様の暮らしの安心を取り戻すお手伝いをしています。
当事務所は、相続、離婚、不動産、交通事故、債務整理、労働事件、刑事事件といった個人案件から、企業間の紛争、債権回収、労務管理等の法人案件、更には分野を特定できない法律問題まで幅広く取り扱う地域密着の総合法律事務所です。
特に、生活に直結する「借金・債務整理」や、突然のトラブルである「交通事故」の分野に力を入れており、豊富な解決実績がございます。法律の専門家として、ご相談者様一人ひとりに親身に寄り添い、迅速な解決を実現することをお約束します。
【借金・交通事故のご相談は初回30分無料】
お困りの際は、一人で悩まずに専門家にご相談ください。お電話やお問い合わせフォームから、まずはお気軽にご連絡いただければ幸いです。
【相続】遺言書作成の注意点
「遺産相続をめぐるトラブルから事件に発展した」というようなニュースを耳にすることは少なくありません。こうした問題を未然に防止するための重要なカギとなるのが「遺言」です。ここでは遺言をする際の注意点について解説します。
そもそも「遺言」とは
「遺言」とは、自分の死後の財産の分け方などについて、遺族にその意思を伝えるものです。つまり遺言は人生で最終の意思表示と言えます。
自分で築いてきた財産を自分の意思に沿う形で相続人に分配し、後々の相続人間での争いを防ぐには、遺言はとても有効な方法です。また、遺言を利用することで、例えば内縁の妻のように相続人になることができない人に対しても、自分の死後に財産を遺すことも可能になります。
民法の定める方式に従って遺言書を作成する必要がある
このように遺言は上手に利用すれば非常に意味のある制度です。しかし、注意しなければならないのは、遺言の方式や効果については、民法が細かく定めており、民法の定める方式に従って作成された遺言書でなければ、遺言の効果は生じないということです。例えば相続人となる配偶者と子供達を全員枕元に呼び、全員の面前で遺産の分配方法を口頭で伝えたものをビデオ撮影していたという場合、一見、相続人全員に故人の意思が明確に伝わっている以上、相続人は故人の意思に拘束され、その後争いになる心配はないようにも思われます。しかし、このような場合でも、民法に定める方式に従っていない以上、法律上は有効な遺言があったとは認められません。もし相続人の一人が、故人の意思に反する主張をし出したとしても、その者に対して法的には故人の最終意思を尊重するよう要求することはできないのです。
遺言をしても、そのとおりに遺産分割がなされないこともある
遺言は故人の最終の意思を伝えるものなので、できる限り尊重されなければなりません。遺言による財産処分は、法定相続分に優先します。相続人は、法的な要件を満たした遺言には原則として従わなければなりません。
とは言え、全ての相続人と遺贈を受ける人(受遺者)の同意が得られる場合には、遺言と異なる遺産分割を行うことは認められます。関係者全員が遺言の内容とは異なる内容での遺産分割に合意する以上、そのような円満になされた合意を否定する理由はないからです(注:遺言者が遺言と異なる遺産分割を禁じている場合や、選任された遺言執行者の同意が得られない場合など認められない場合もあります。)。但し、税務上は、一旦遺言によって他の人が取得した遺産を別の人に譲渡したとみなされ、贈与税が発生する可能性もありますので、税理士さんに相談して、よく検討する必要はあります。
相続人には最低限の財産をもらう権利がある
遺言に定められていたとしても、亡くなった方の兄弟姉妹を除く相続人には、相続財産の一定割合が確保される制度があります。「遺留分」と呼ばれる制度です。この遺留分は、遺言によっても奪うことができない最低限の権利ですので、相続人が遺言の内容に拘束されないケースの一つといえるでしょう。遺言によって遺留分を侵害された相続人は、他の相続人や受遺者に対して遺留分侵害額請求を行い、遺産の返還を受けることができます。
遺言書作成の注意点
このように、遺言は、民法の定める方式に従って遺言書を作成しなければ効力が生じないという点に、先ずは注意が必要です。そして、仮に遺言書を作成したとしても、その内容が相続人の誰かの遺留分を侵害しているような場合には、後々トラブルになってしまうことがありますので、トラブルの防止を重視するならば、予め遺留分を考慮した内容で遺言書を作成するようにしましょう。

千葉県・東京23区を中心に活動する秋山慎太郎総合法律事務所です。
私たちは「身近な法律事務所」として、皆様の暮らしの安心を取り戻すお手伝いをしています。
当事務所は、相続、離婚、不動産、交通事故、債務整理、労働事件、刑事事件といった個人案件から、企業間の紛争、債権回収、労務管理等の法人案件、更には分野を特定できない法律問題まで幅広く取り扱う地域密着の総合法律事務所です。
特に、生活に直結する「借金・債務整理」や、突然のトラブルである「交通事故」の分野に力を入れており、豊富な解決実績がございます。法律の専門家として、ご相談者様一人ひとりに親身に寄り添い、迅速な解決を実現することをお約束します。
【借金・交通事故のご相談は初回30分無料】
お困りの際は、一人で悩まずに専門家にご相談ください。お電話やお問い合わせフォームから、まずはお気軽にご連絡いただければ幸いです。
【相続】遺産相続の際の法定相続分とは
遺産相続において、各相続人が取得すべき遺産の割合は法律で定められています。法律で定められた各相続人の取り分のことを「法定相続分」と言います。この法定相続分についてご説明します。
法定相続分は遺産分割の目安
亡くなった方の財産を分割する際に最優先されるのは、故人の意思すなわち「遺言」です。遺言によって決められた相続分(割合)は「指定相続分」と呼ばれます。
一方、遺言がない場合には、相続人が話合いで分け方を決めることになります。その分け方の目安として民法に定められているのが「法定相続分」です。
相続人となるのは誰?
亡くなった人の配偶者は常に相続人となります。なお、内縁関係の人は、相続人にはなりません。
配偶者以外の人は、以下の順序で配偶者と一緒に相続人になります。
第一順位 亡くなった人の「子」
第二順位 亡くなった人の「直系尊属」
第三順位 亡くなった人の「兄弟姉妹」
第一順位の人がいない場合は第二順位の人、第一順位の人も第二順位の人もいない場合は第三順位の人が相続人となります。
法定相続分はどう定められている?
民法は法定相続分を次のように定めています。
・配偶者と子が相続人である場合
配偶者2分の1 子2分の1
・配偶者と直系尊属が相続人である場合
配偶者3分の2 直系尊属3分の1
・配偶者と兄弟姉妹が相続人である場合
配偶者4分の3 兄弟姉妹4分の1
子、直系尊属、兄弟姉妹がそれぞれ2人以上いるときは、その中で均等に分けます。例えば、配偶者がおらず子が3人いる場合は、子それぞれが3分の1、配偶者と子3人がいる場合は、配偶者が2分の1、子それぞれが6分の1となります。
冒頭でもお伝えしましたとおり、民法に定められた法定相続分は、必ずこの相続分で遺産分割しなければならないというものではありません。実際には、法定相続分どおりの割合で分割されるケースよりも、相続人全員で話し合ってそれぞれが取得する遺産を決めるケースの方が多いのではないでしょうか。法定相続分は、そのような話合いの際に一つの目安として役立つものなのです。

千葉県・東京23区を中心に活動する秋山慎太郎総合法律事務所です。
私たちは「身近な法律事務所」として、皆様の暮らしの安心を取り戻すお手伝いをしています。
当事務所は、相続、離婚、不動産、交通事故、債務整理、労働事件、刑事事件といった個人案件から、企業間の紛争、債権回収、労務管理等の法人案件、更には分野を特定できない法律問題まで幅広く取り扱う地域密着の総合法律事務所です。
特に、生活に直結する「借金・債務整理」や、突然のトラブルである「交通事故」の分野に力を入れており、豊富な解決実績がございます。法律の専門家として、ご相談者様一人ひとりに親身に寄り添い、迅速な解決を実現することをお約束します。
【借金・交通事故のご相談は初回30分無料】
お困りの際は、一人で悩まずに専門家にご相談ください。お電話やお問い合わせフォームから、まずはお気軽にご連絡いただければ幸いです。