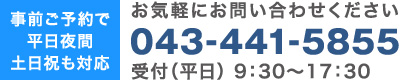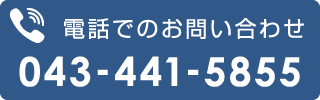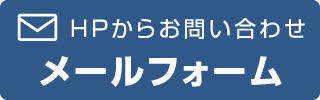Archive for the ‘企業法務コラム’ Category
【企業・顧問】就業規則を改定すべきケース
いったん就業規則を作成しても、時間が経過すると改定が必要となるケースがよくあります。古い就業規則をそのまま適用していても、効果的に社内規律を維持したりトラブル防止したりできません。
この記事では就業規則を改定すべき状況や改定方法について、弁護士が解説します。
1.就業規則を改定せず放置するデメリット
常時10人以上の従業員を雇用する事業所では、就業規則を作成して労基署へ届け出る必要があります。ただし10人未満の会社でも社内規律維持やトラブル防止のための就業規則を作成するよう推奨しています。
ではいったん作成した就業規則を長年見直さずに放置していても問題はないのでしょうか?
就業規則は定期的に見直すべきです。以下でその理由をお伝えします。
1-1.違法状態になってしまう可能性がある
労働関係法令をはじめとして、法律は頻繁に改正されます。
たとえば2022年10月には「産後パパ育休制度」とよばれる育休制度の改正法が施行されたことも記憶に新しいでしょう。
法改正が行われたら、就業規則もそれに合わせて改定しなければなりません。
放置すると、違法状態になってしまう可能性があります。
1-2.現状に合わない内容になってしまう
違法にはならなくても、就業規則を改定しないデメリットがあります。
たとえば古い就業規則をそのまま放置していると、会社の現状に合わない状況が発生してきます。それでは就業規則が形骸化してしまい、設置している意味がありません。
就業規則は常に最新のものにアップデートしておく必要があります。
2.就業規則を改定すべきタイミング
どのような状況になれば就業規則を改定すべきなのでしょうか?以下で就業規則を改定すべきタイミングをお伝えします。
2-1.法改正に対応するタイミング
1つは法改正に対応しなければならないタイミングです。
働き方改革関連法、育休関連など、最近でも多くの労働関係法令の改正が行われています。
法改正に追いつくには、就業規則の改定が必要になるケースが多いので、改正法が施行される前に就業規則をアップデートしましょう。
2-2.就業規則が形骸化している場合
就業規則が古くなって形骸化しているなら、改定すべきタイミングといえます。
就業規則は従業員に参照させて服務規律を守らせる役割も果たします。
せっかく就業規則を定めても従業員の参考にならない古い内容になっているなら、早めに現在の企業の状態に即した内容に改定しましょう。
2-3.トラブルを防止できなかった場合
せっかく就業規則があっても、効果的にトラブルを防止できなければ意味がありません。
たとえば懲戒解雇した場合などに就業規則が役に立たなかったなら、改定を検討すべき状況となっている可能性があります。
3.就業規則の改定方法
以下では就業規則を改定する手順をお知らせします。
STEP1 労働者の代表者の意見をきいて改定案を作成する
まずは過半数の労働者の代表者から意見を聞きながら改定案を作成しましょう。
労働組合がある場合、過半数が加入している労働組合の代表者が労働者の代表になります。
ただし労働者に不利益な内容に変更する場合、対象となる全労働者の合意が必要になります。
STEP2 就業規則・就業規則変更届を作成する
次に就業規則や就業規則変更届を作成しましょう。
就業規則を作成するときには、雛形を利用するとしても自社のニーズに応じたものとすべきです。
STEP3 所轄労働基準監督署へ提出する
次に所轄の労働基準監督署へ就業規則や就業規則変更届を提出します。
STEP4 労働者へ周知する
就業規則を提出したら、労働者へ周知しなければなりません。
事業所に備え付けていつでも従業員がアクセスできる状態にしたり、共有フォルダに入れて従業員がいつでも閲覧できる状態にしたりしましょう。
周知されなかった場合、就業規則には効力が認められません。周知義務違反として30万円以下の罰金刑となる可能性もあるので、違反しないように注意してください。
千葉県の秋山慎太郎総合法律事務所では労働問題に力を入れて取り組んでおります。就業規則の見直しをご検討の場合、お気軽にご相談ください。
【企業・顧問】就業規則とは?作成義務があるケースや罰則についても解説!
一定以上の規模の会社の場合、就業規則を作成しなければなりません。
作成しないと罰則が適用される可能性もあるので、違反状態にならないよう要注意です。
この記事では就業規則とは何か、どういった場合に作成義務があるのか、トラブル予防に効果的な就業規則の定め方について弁護士が解説します。
法律を守って従業員との労働トラブルを予防したい場合には、ぜひ参考にしてみてください。
1.就業規則とは
就業規則とは、従業員の労働条件や社内規律を定めたルールです。社内で通用する法律のようなものと理解すると良いでしょう。
いったん就業規則に定めると、社内ではその内容が有効になります。従業員側も会社側も違反できません。ただし就業規則の中でも法律に反する部分については無効になります。
また「就業規則」という名称でなくても就業規則として取り扱われるケースがあります。
たとえば賃金規程や退職金規程も一種の就業規則です。
2.就業規則の作成義務について
一定以上の規模の企業の場合、就業規則の作成が義務になります。
労働基準法では「常時10人以上の従業員を雇用する企業」については就業規則を作成して労働基準監督署へ届け出なければならない、と規定されています(労働基準法89条)。
就業規則は事業所ごとの作成や備え付けが必要であり、いくつかの支店や営業所のある企業では事業所ごとに作成しなければなりません。「常時10人以上」かどうかについても「事業所ごとにカウント」されます。
また従業員にはパートやアルバイト、契約社員などの非正規雇用の労働者も含めてカウントしなければなりません。一方で、業務委託の取引相手や派遣労働者、繁忙期の臨時社員などはカウントしません。
2-1.就業規則の義務がない場合も作成すべき
事業所内に常時10人以上の従業員がいない場合、就業規則を作成する必要はありません。
しかし実際には労働基準法上の作成義務がなくても就業規則を作成すべきです。
就業規則があると、社内の規律が明確になりますし、従業員に規律違反の行動があれば適正に対応できるからです。
就業規則があると社内のトラブルを防止できるメリットがありますし、万一トラブルが起こっても最小限に抑える効果があります。
2-2.就業規則は作成だけでなく届出が必要
就業規則作成義務のある事業所では、作成した就業規則を労働基準監督署へ届け出なくてはなりません。
また従業員に周知する必要もあります。事業所内の見やすい場所に設置するか、従業員がいつでもアクセスできる状態にしておきましょう。
2-3.就業規則作成義務違反の罰則
就業規則の作成義務があるにもかかわらず作成しなかったり届け出をしなかったりすると、「30万円以下」の罰金が科される可能性があります。
3.就業規則の作成方法
3-1.記載事項について
就業規則には必ず盛り込まねばならない絶対的必要記載事項があります。
- 始業時刻と終業時刻
- 休憩時間、休日、休暇
- 労働者を2組以上に分けて交代制で就業させる場合、就業時転換に関する事項
- 賃金や計算方法、支払方法
- 賃金の締切りや支払時期
- 昇給に関する事項
- 退職に関する事項、解雇事由
また該当する場合に盛り込まねばならない相対的必要記載事項もあります。
- 退職金制度がある場合には退職金に関する事項
- 賞与や最低賃金額がある場合、その事項
- 従業員に食費や作業用品などの負担をさせる場合、それに関する事項
- 安全衛生に関する定めをおく場合、それに関する事項
- 職業訓練に関する定めをする場合の内容
- 災害補償や業務外の傷病扶助に関する定めをする場合、それに関する事項
- 表彰や制裁の定めをおく場合、種類や程度に関する内容
- その他従業員に適用される定めをおく場合の内容
その他については任意的に盛り込める「任意的記載事項」となります。
3-2.効果的な就業規則の作成方法
就業規則を作成する場合、自社の状況に応じたものとしなければなりません。モデル書式もありますが、そのまま適用するのはおすすめではありません。
書式を利用しながらも、自社の個性に応じたものにアレンジして定めましょう。また法改正があればアップデートも必要です。
就業規則を定めるときには法律の専門家に相談しておくと安心です。作成・改訂の際には千葉県の秋山慎太郎総合法律事務所までお気軽にご相談ください。
【企業・顧問】電子契約の法的効力、有効性について弁護士が解説
近年ではビジネスの場においても急激にデジタル化が進んでおり「電子契約」を導入する企業が増えています。
ただ「電子契約や電子署名には法的効力が認められるのか?」「契約として有効なのか?」と不安を感じる方も少なくありません。
要件さえ満たせば電子署名にも法的効力が認められます。
今回は電子契約や電子署名の法的効力や有効性について、弁護士が解説します。
1,多くの契約では「契約書」は不要
「電子契約でも契約は有効に成立するのか?」
といった疑問を持つ方がおられます。
実は法律上、ほとんどの契約の成立に「契約書」は必要ありません。
書面やその他の資料がなくても、口頭で契約が成立するのです。
ただ口頭では証拠が残らず、後に証明できません。内容について争いが発生したときに大きなトラブルになってしまいます。
そこで契約内容を明らかにして証拠を残すため、通常のビジネスの場では契約書を作成するのです。
単純に「契約が成立するかどうか?」という意味では、電子契約であっても十分に契約が成立するといえます。
ただし一定の契約については「必ず書面(または電子)で締結しなければならない」と定められています。そういった類型の契約は、契約書や電子契約データを作成しなければ成立しません。
2.電子署名が有効となる要件
次に「電子署名」の有効性についてみてみましょう。
電子契約を締結する際には「電子署名」を付します。
電子データに付す署名であっても、電子署名法の定める要件を満たせば法的効力が認められます。
電子署名法では、2条において「有効な電子署名となるための要件」が規定されています。
- 本人が作成したもの(本人性)
- 改変されていないことを確認できるもの(非改ざん性)
つまり本人確認が行われていて、作成されてから改ざんされていないことを確認できるものであってはじめて有効な「電子署名」となります。
具体的には認証局の発行する「電子証明書」と「タイムスタンプ」によって上記の要件を満たします。
クラウドの電子署名サービスを利用した場合でも、きちんと本人確認されていてタイムスタンプが付与されていれば有効な電子署名となります。
3.電子署名に推定効が及ぶ要件
電子署名法3条では、電子署名に「推定効」が及ぶ要件が規定されています。
推定効とは「本人による電子署名が付されているときに電子データが真正に成立したと推定する」効力です。つまり本人が電子署名していれば、その電子データは署名者自身が作成したと推定できます。
第3条 電磁的記録であって情報を表すために作成されたもの(公務員が職務上作成したものを除く。)は、当該電磁的記録に記録された情報について本人による電子署名(これを行うために必要な符号及び物件を適正に管理することにより、本人だけが行うことができることとなるものに限る。)が行われているときは、真正に成立したものと推定する。
紙の書面に対する署名押印にも同様の効果が認められています。これを「2段の推定」といいます。
電子署名法3条の電子署名といえるには、以下の要件を満たさねばなりません。
- 本人性
- 非改ざん性
- 固有性
電子署名法2条の要件に足して、「本人だけが行うことができる」という固有性の要件を満たす必要があります。
具体的には以下のような方法が考えられます。
- 本人が認証局へ申請して電子証明書を取得して電子署名する
- クラウドの電子署名サービスを使う場合、2要素認証によって厳格に本人確認する
上記のような対応ができれば、電子契約であっても紙の契約書と同等の法的効力が認められます。
4.電子契約を適用される範囲が拡大
現在、電子契約を適用できる範囲は拡大しつつあります。従来は紙の契約書を必要としていた不動産の賃貸や売買などにおいても電子契約を利用できるようになる予定です(ただし事業用定期借地権契約を除く)。
電子契約導入の際に不安な点がありましたら弁護士がアドバイスいたしますので、お気軽にご相談ください。
【企業・顧問】商標権侵害で警告されたときの対処方法
「商標権侵害の差し止め警告書が届いたのですが、どう対応すれば良いのでしょうか?」
こういったご相談を受けるケースが少なくありません。
ウェブサイトやパンフレットなどでロゴやイラストなどのマークを利用していると、他社から「商標権侵害」と主張される可能性があります。
ただ、必ずしも相手の主張内容が正しいとは限りません。法的な観点から適切に判断して対応しましょう。
今回は商標権侵害で警告を受けた場合の対処方法を、弁護士がお伝えします。
1.相手の権利を確認
「商標権侵害」といわれたら、まずは対象となっている商標について、相手に権利があるのか確認すべきです。
1-1.そもそも商標権が存在するのか
そもそも相手の主張する商標権が存在するのか、特許庁で登録されているのか確認しましょう。
登録商標はこちらから検索できます。
https://www.jpo.go.jp/support/startup/shohyo_search.html
1-2.現在も有効なのか
商標が登録されているとしても、更新しなければ期限が切れて効力が失われている可能性があります。
現在も有効なのか、確認しましょう。
2.商標権侵害といえるか確認
次に、自社が本当に商標権侵害をしているのか確認すべきです。
商標権侵害といえるには、以下の2つの要件を満たさねばなりません。
2-1.同一または類似した商標を利用している
相手の登録商標と同じか、類似した商標を使っていることが1つ目の要件です。特に「類似」と主張されている場合、本当に「類似」しているといえるのか、これまでの裁判例も踏まえて慎重に検討しなければなりません。
類似しているかどうかについては、外観や読み方、商標から想起されるイメージなどを考慮して判断されます。
自社では判断が難しいと思われますので、類似性の有無については弁護士にご相談ください。
2-2.商品やサービスの類似
次に、標章を適用している商品やサービスが相手の登録商標の指定商品や指定役務と重なっているか、類似しているか検討しましょう。
商標権による保護は「指定商品」「指定役務」と同じか類似する範囲までしか及ばないためです。
商品やサービスの類似性について判断するには高度な法的知識が必要となりますので、自己判断せずに弁護士へ相談されるようおすすめします。
2-3.商標的な利用をしている
商標権侵害といえるには「商標的利用」をしている必要があります。
商標的利用とは、「自社の商品やサービスの識別のために利用すること」です。
単に他社商品やサービスを説明するために他社商標を利用した場合、普通名詞として使用した場合などには「商標としての使用」に該当しません。
3.先使用権を主張できる場合
他社の商標を利用した場合でも「先使用権」を主張できるケースがあります。
先使用権とは、商標登録を出願する前からその商標を使用している場合に認められる権利です。
他社が商標を出願する前から自社の商品やサービスを表示するために同じ商標や類似する商標を使っており、世間に広く認識されていた場合、例外的にその商標を使用しても商標権侵害になりません。
4.相手に対する返答方法
警告書が送られてきた場合、たいてい期限がついています。
放置すると訴訟を起こされるリスクがあるので、期限内に回答しましょう。
相手の請求に理由がないと考えられる場合、反論を述べて請求には応じられないと回答すべきです。
一方、相手の請求内容が正しくこちらが利用を停止するなら、差止請求に応じると回答しましょう。いつまでに停止するのかも明らかにするとよいでしょう。
損害賠償請求された場合でも、必ずしも相手の言い値を払う必要はありません。「任意に商標利用を停止するので賠償金を免除してもらいたい」といった交渉も可能です。
話し合いによって減額できるケースも多数あるので、そのまま支払いに応じないで交渉すべきと考えます。
商標権侵害の警告書が届くと、どのように対応すればよいかわからずあせってしまうものです。お困りの際にはお早めに弁護士までご相談ください。
【企業・顧問】商標権侵害が成立する要件、侵害されたときの対処方法を弁護士が解説
自社ブランディングのために商標権を獲得しても、他社や個人が勝手に使用するトラブルが少なからず発生しています。
商標権を侵害されたら、使用の差し止めや損害賠償請求ができます。
また商標権侵害には刑事罰も適用されるので、刑事告訴も可能です。
今回は商標権侵害が成立する要件や、侵害されたときの対処方法を弁護士がお伝えします。
自社の商標が勝手に使われてお困りの方はぜひ参考にしてみてください。
1.商標登録した人の権利やメリット
商標とは、事業者が自社の商品やサービスを他社のものと区別するために使用する「マーク(識別標識)」です。
文字の商標、イラストの商標、ロゴなどが代表的な商標です。
自社でロゴなどを作成した場合、特許庁で商標登録すると商標権が認められて独占的に利用できるようになります。
登録商標は自社のみが使うことができて、他人が勝手に使うことは許されません。
同じものだけではなく、類似した標章も利用できなくなります。
自社商品やサービスのブランディングに有効で、商標が世間に認知されると自社の商品やサービスへの信頼が高まるメリットがあります。
また自社商標を他社へ貸し出してライセンス契約を締結し、利益を得る活用方法もあります。
2.商標権侵害の要件
商標登録しても、他社から権利侵害されるケースが少なくありません。
商標権侵害となるには、以下の2つの要件を満たす必要があります。
2-1.無断で商標や類似の標章を利用
1つ目は、権利者の許可なく同一商標や類似商標を使ったことです。
まったく同じマークでなくても、類似していれば商標権侵害になる可能性があります。
2-2.商標的利用に該当する
2つ目に「商標的利用」に該当する必要があります。
商標的利用とは「自社商品やサービスであることを顧客に示す目的での使用」です。
つまり、自社商品やサービスのマークとして示す利用方法でなければ、商標を使っても商標権侵害にはなりません。
たとえば他社商品を説明するために他社商標を表示しても侵害にはなりません。
3.商標権侵害されたときの対処方法
3-1.証拠を集める
商標権侵害されたら、まずは自社商標が侵害された「証拠」を集めましょう。
- 他社商品に関する資料
パンフレットやHPの画面、カタログなど
- 商標が勝手に利用されていることがわかる資料
ウェブサイト画面やチラシ、配布物や商品紹介資料など
- 他社商品の売上や営業に関する資料
開示されている各種報告書など
3-2.差止請求する
商標権を勝手に使われたら、相手に利用の差止を請求できます。相手が利用をやめればこれ以上の損害の拡大を防げます。
証拠がそろった段階で、侵害者に対して商標利用の差止請求をしましょう。
内容証明郵便で警告書を送るのが一般的です。
3-3.損害賠償請求する
商標権侵害によって損害が発生すると、相手に損害賠償請求が可能です。
相手に差止請求書を送る際に、合わせて損害賠償も求めましょう。
3-4.話し合い
差し止めや損害賠償の請求をしたら、具体的な解決方法について相手と話し合います。
相手が利用を即刻停止して損害も発生していなければ、「二度と勝手に商標を使わない」という誓約書を書かせて示談してもかまいません。損害が発生していたら、一定額の賠償金を払わせて解決しましょう。
最適な解決方法はケースバイケースなので、迷ったら弁護士へご相談ください。
3-5.保全や訴訟
相手が請求に応じず商標利用もやめない場合には、裁判手続きをとらねばなりません。
まずは利用を停止させるため、民事保全を申し立てましょう。
損害賠償請求については、訴訟を提起する必要があります。
3-6.刑事告訴する
商標権侵害には刑事罰もあります。
相手が悪質で差し止めにも損害賠償請求にも応じないようなケースでは、刑事告訴も検討しましょう。
刑罰は10年以下の懲役または1000万円以下の罰金刑です。
当事務所では各業種の企業様への法的支援体制を整えています。千葉県で顧問弁護士をお探しの方がおられましたらお気軽にご相談ください。
【企業・顧問】従業員と締結すべき「競業避止義務契約」について
従業員が会社と競業する事業を行うと、会社に大きな損害が発生する可能性があります。
特に退職後の元従業員に競業させないためには「競業避止義務契約」を締結しなければなりません。
ただし競業避止義務契約を締結させても、必ずしも法的に有効になるとは限りません。
今回は従業員と締結すべき「競業避止義務契約」について、弁護士が解説します。
1.競業避止義務とは
競業避止義務とは、相手とライバル関係になる事業や仕事を行ってはならない義務です。
たとえば会社が従業員へ競業避止義務を課したり、M&Aの際に譲渡会社の元社長へ競業避止義務を課したりするケースがよくあります。
従業員は会社の内情をよく知る立場ですし、取引先とのコネクションを持つものも少なくありません。そういった立場を利用して会社と競業されると、会社には大きな損害が発生するリスクが発生します。
そこで会社の利益を守るため、従業員に競業避止義務を課す必要があるのです。
2.在職中の競業は禁止される
一般的に、従業員の在職中は当然に競業避止義務を負うと考えられています。
労働契約をまっとうするには競業避止義務が必須なので労働契約に付随するともいえますし、信義則上の義務ともいえるでしょう。
また多くの会社では就業規則で競業避止義務を定めているものです。そういった会社で在職中の従業員が競業行為をすると、懲戒処分や損害賠償請求できる可能性もあります。
3.退職後の元従業員とは競業避止義務契約が必要
一方、退職後の従業員には当然には競業避止義務が及びません。
退職した従業員には職業選択の自由が認められるので、どういった企業に就職するのも起業するのも基本的に自由だからです。退職後の元従業員に競業避止義務を負わせるには「競業避止義務契約」を締結するか、就業規則に退職後の競業も禁止する規定をもうけなければなりません。
4.競業避止義務契約を締結しないリスク
退職後の従業員に競業避止義務を課さなかったら、企業側には以下のようなリスクが発生します。
- 元従業員が会社の顧客情報を持ち出して営業する
- 元従業員が会社の取引先を奪ってしまう
- 元従業員が会社の他の従業員を引き抜く
- 元従業員が会社独自のノウハウを勝手に使って同種の営業をする
上記のような問題が起こっても差し止め請求できなければ、会社としては多大な損害を受けてしまうでしょう。そうならないために競業避止義務契約を締結すべきです。
5.競業避止義務契約が無効になるケース
ただし競業避止義務契約を締結しても、必ず有効になるとは限りません。
元従業員には「職業選択の自由」があるので、不当に侵害すると「公序良俗違反」として契約が無効になってしまう可能性があるのです。
裁判例では、以下のような事情を考慮して競業避止義務契約の有効性が判断されています。
- 使用者側の正当な利益の保護を目的としているか
- 元従業員の在職中の地位や職務内容
- 地域的な限定
- 競業避止義務の期間
- 競業行為の範囲の限定
- 代償措置の有無や内容
たとえば元従業員が役職のない平社員で在職中、特に重要な業務にも従事していなかったのに、エリアを限定せず無制限に競業を禁止すると無効と判断される可能性が高くなります。
競業避止義務が及ぶ年数としては6か月や1年程度であれば有効性が認められやすい傾向がありますが、2年を超えると無効と判断されるケースが多数です。
上記のほか、退職に至る経緯や背信性の強さ、転職可能性などが考慮されるケースもあります。
6.競業避止義務違反が発覚した場合の対処方法
競業避止義務違反が発覚すると、企業側は以下のような対応が可能です。
- 退職金の減額や不支給
- 競業行為の差し止め請求
- 損害賠償請求
退職後の従業員に競業避止義務を課すため、退職時には競業避止義務契約を締結しましょう。
【企業・顧問】外注で業務委託契約を締結する際の注意点
企業運営に際し、さまざまな業務を「外注」する場面があります。
商品や製品の開発、アプリやシステムの開発、デザインやホームページの制作など。
そんなときには「業務委託契約」を締結しなければなりません。
後にトラブルにならないよう、業務委託契約書を作成する際の注意点を弁護士がお伝えします。
1.業務委託契約とは
業務委託契約とは、外注者(委託者)が受注先(受託者)へ一定の業務を委託し、対価として報酬を支払う契約です。
以下のような際に業務委託契約を締結する例がよくあります。
- コンサルティング
- 商品や製品の開発
- アプリやシステム開発
- デザインやライティング、翻訳
- ホームページの制作
- SEO対策
- システムの保守管理
- 営業代行
- 広告出稿代行
- 建築設計監理の委託
- 運送業務の委託
- 社員研修の委託
社外の法人や個人に上記のような業務を外注する場合、業務委託契約書を作成すべきです。
契約書がなければ報酬の支払時期や成果物に対する権利、解約できる条件などが明らかにならずトラブルのもとになってしまいます。
2.業務委託契約書作成における注意点
業務委託契約書を作成する際には、以下のような点に注意しましょう。
2-1.契約目的と委託する業務の内容
まずは契約目的と委託する業務の内容を明らかにしましょう。特に業務内容については契約の核となる部分なので、できる限り明確にすべきです。
業務内容があいまいになっていると、受注者の裁量で業務を進められ、希望と異なるものが納品されてもクレーム言えなくなる可能性があります。
2-2.報酬の金額と支払時期
次に報酬の金額と支払時期を明確にしましょう。特に支払時期が不明確だとトラブルになりやすいので要注意です。
たとえば「納品されたタイミング(即時)」で払うのか「納品後2週間以内」とするのか「翌月末」とするのか、あるいは納品後検収期間をもうけるのかなど、相手と話し合って決定する必要があります。
2-3.納期
システム開発やデザインやライティング、翻訳などの「成果物の提出」を要する案件の場合、納期も定めておくべきです。納期が決まっていないと、いつまで経っても納品されず、発注企業側が不利益を受ける可能性があります。
2-4.契約期間
単発案件でない場合、契約期間も定めておくと良いでしょう。1年などとして、場合によっては自動更新条項をもうけましょう。
2-5.成果物に対する権利
成果物に対する権利が誰に帰属するのか、発注企業に帰属する場合にはいつのタイミングで権利が移転するのかなど、明確に記載しておきましょう。
たとえばデザインを外注した場合、基本的にはデザイナーに著作権が認められます。
納品と同時あるいは報酬支払と同時に著作権の譲渡を受けておかないと、企業側で自由な利用や改変ができません。
また著作権が問題になる場合には「著作者人格権を行使しない」ことも定めておくべきです。著作者人格権は譲渡できないので、行使しないと定めておかないと後に作品を活用できなくなる可能性があります。
2-6.秘密保持
業務を外注する場合、企業の内部機密を伝えなければならないケースも多く、外注先に秘密を漏えいされる可能性があります。
必ず秘密保持の条項を入れましょう。
ただし実際には業務委託契約書とは別途、秘密保持契約書を作成するケースが多数です。
2-7.再委託について
受注先が第三者に業務を再委託できるのか、できるとすればどういった条件下で認められるのかを記載しましょう。
再委託を認める場合には、「事前に発注者による書面(あるいは電子メール)による承諾を要する」と記載しておくと、無断で再委託されないので安心です。
また再委託先にも秘密保持の契約を締結させる必要があります。
2-8.解除と損害賠償
どういった場合に契約を解除できるのか、損害賠償ができる条件についても定めておきましょう。
当事務所では千葉県内の各企業様へ向けて法務アドバイスを積極的に行っています。企業法務に詳しい弁護士をお探しの方がおられましたら、お気軽にご相談ください。
【企業・顧問】従業員と秘密保持契約を締結すべき理由や注意点
会社が従業員を雇い入れる際には「秘密保持契約」を締結すべきです。企業の機密情報が流出すると、多大な損失が発生するリスクが発生します。従業員を通じて秘密漏洩し、世間を揺るがす不祥事となってしまうケースも少なくありません。
千葉県内の各企業にも独自のノウハウや取引先・顧客リスト、個人情報などの機密情報が蓄積しているでしょう。秘密保持契約を締結し、貴重な情報を守る必要があります。
この記事では企業が従業員と秘密保持契約を締結すべき理由や注意点を、弁護士が法的な観点からお伝えします。
1.秘密保持契約とは
秘密保持契約とは、契約当事者が相手にわたす情報の漏洩を禁止し、他への流出を防ぐための契約です。業務を外注する場合や製造委託する場合、ホームページ制作業者、SEO業者を利用する場合、M&Aを行う場合などにも秘密保持契約を締結するケースがよくあります。
従業員も会社の重要な情報を知る立場にあるので、秘密保持契約を締結すべき対象です。
2.企業が従業員と秘密保持契約を締結すべき理由
従業員は会社の重要な情報にアクセスできる立場にあります。
- 取引先や顧客のリスト
- 社内の従業員の個人情報
- 自社のノウハウ
- 製品開発情報
こういった情報を外部に漏洩されると、会社としては大きな損失を受けます。個人情報保護法違反の責任を問われるリスクも発生し、信用問題にも発展するでしょう。
秘密保持契約を締結しておけば、漏洩が禁止されるので、会社の機密情報を守りやすくなります。
万一従業員が違反して漏洩してしまった場合にも、世間や被害者に対し「会社としてできうる限りの適切な措置を行っていた」と説明しやすくなります。
企業にとって従業員との秘密保持契約締結は必須です。
3.秘密保持契約を締結する従業員の範囲
秘密保持契約は、可能な限りすべての従業員と締結すべきです。役職つきの人材や特殊スキルをもった人材だけではなく、平社員や新入社員などの従業員にも秘密を守らせる必要があります。
また正社員だけではなく、パートやアルバイトなどの非正規雇用者も会社の情報にアクセス可能です。SNSでアルバイト店員が行った投稿が原因で企業が損害を受ける事件も発生しているので、アルバイトやパートの従業員とも秘密保持契約を締結しましょう。
4.秘密保持契約書に盛り込むべき内容
4-1.秘密情報の定義や範囲
まずはどういった情報を「秘密情報」とするのか規定しましょう。
秘密情報の範囲を限定しすぎると「これは秘密情報にならない」といわれる可能性があるので「その他上記に準じる情報」などと包括的に定義しておくとよいでしょう。
秘密情報については、開示してはならないことを定め、第三者への漏洩を禁止します。
4-2.例外的に開示可能な場合
すでに知られている情報、法令によって開示しなければならない場合など、例外的に開示できる場合を定めます。
4-3.利用制限
秘密情報の目的外利用を禁止する条項です。不適切な複製行為も禁止しましょう。
4-4.損害賠償
秘密保持義務に反して従業員が情報漏えいした場合、企業側が損害賠償請求できることを定めます。
4-5.秘密情報の返還
雇用契約が終了したら、速やかに情報を返還する約束をします。
4-6. 有効期間
雇用契約の終了後も一定期間、秘密保持契約の効力を存続させることも可能です。
5.秘密保持契約書を締結するタイミング
秘密保持契約は、基本的に「雇用時(入社時)に締結しましょう。
新入社員であってもすぐにパソコンやタブレットから情報データベースへアクセスできるケースが多いですし、事業所内の書類も閲覧できるからです。
また秘密保持契約締結を入社の条件としておけば、労せず秘密保持契約を締結させられます。いったん雇用した後に秘密保持契約を要求すると、相手が拒否したときに強要できないリスクが発生します。
6.従業員の労務管理は弁護士へ相談を
従業員の労務管理においては、労働時間や解雇問題、秘密保持などさまざまな場面で法的に適切な対応を要求されます。千葉県で労務管理に詳しい弁護士をお探しの企業がありましたら、お気軽に弁護士までご相談ください。
【企業・顧問】副業禁止は違法?裁判例や副業解禁のメリット、デメリットを弁護士が解説
日本では従来、副業を禁止する企業が大多数でした。しかし近年では働き方改革の影響もあって、副業解禁の動きが加速しています。
就業規則で副業を禁止して懲戒すると「違法」になる可能性もあります。
今回は副業禁止規定にもとづく懲戒解雇が違法とされた裁判例を交えながら、副業を解禁するメリットやデメリットを弁護士が解説します。
1.副業を認めるかどうかは企業の自由
従業員に副業を認めるかどうかは、基本的に企業側の自由です。
確かに副業を認めると、本業への支障が及んだり労働時間の把握が難しくなったりする可能性があり、副業を制限する合理性も認められます。副業を禁止しても、必ずしも違法ではありません。
ただし最近では「働き方改革」のスローガンのもと政府の方針も転換され、副業を解禁する動きが目立ってきています。
2.副業禁止規定にもとづく懲戒解雇が違法になるケース
副業禁止は基本的に違法ではありませんが、副業禁止規定にもとづいて懲戒処分を行うと違法になってしまう可能性があります。
副業が本業に支障を及ぼしておらず、他にも会社に損害やリスクを発生させていないのに懲戒解雇する合理的な理由がないと考えられるためです。
2-1.副業禁止規定にもとづく解雇が無効とされた裁判例
副業禁止規定にもとづく懲戒解雇が違法と判断された裁判例を示します。
十和田運輸事件(東京地判平成13年6月5日)
運送会社のドライバーが年に1、2回程度、他社で貨物運送のアルバイトを行った事案です。会社は兼業禁止規定に基づいて懲戒解雇しました。
裁判所は、従業員が職務専念義務に違反しておらず勤務先との信頼関係を破壊したとまでいえないとして、解雇無効と判断しました。
2-2.副業禁止規定が違法と判断されやすい要素
副業禁止による懲戒解雇が違法になりやすいのは、以下のような場合です。
- 本業に対する影響がない、ほとんどない
- 副業の内容は本業と無関係で、競業の可能性がない
- 副業の規模が小さい
- 勤務先の信用やブランドが毀損されるおそれがない
一方、従業員が競業によって企業に迷惑をかけた場合、信用やブランドを毀損した場合、本業をおろそかにした場合、情報を漏洩した場合などには懲戒解雇が認められる可能性も高くなります。
3.副業解禁のメリット
3-1.労働者のスキルアップ
従業員が副業をすると、新たな知識や経験を身につけられるのでスキルアップにつながります。副業で身につけたスキルを本業に活かせれば企業にとっても強い戦力となり、メリットを得られます。
3-2.人材確保
副業を認めると「自由に働ける職場」と評価されて優秀な人材が集まりやすくなります。
はたらきやすい職場であれば、人材が定着しやすく戦力確保にもつながるでしょう。
3-3.事業拡大のチャンス
従業員が副業で獲得した人脈や情報、スキルを企業が積極的に活用すると、他企業や団体と関わりができて取引につながったり、共同で技術開発したりして、事業拡大の機会になる可能性もあります。
4.副業解禁のデメリット
4-1.本業がおろそかになる
本業の最中に副業のメールチェックや返信などの作業を行う人もいますし、本業が休みの際にアルバイトなどをして疲れが溜まったり睡眠不足になったりする人もいます。
本業に支障をきたし、生産性が低下してしまうリスクが発生します。
副業を解禁するなら、本業に支障の及ばない方法を検討し、従業員と会社がお互いに確認しておいた方がよいでしょう。
4-2.情報流出のリスク
従業員が副業の際に勤務先企業の情報を漏らしてしまうリスクも発生します。
副業を解禁するなら、情報取扱い方法についてしっかり取り決めておくべきといえるでしょう。
4-3.信用毀損リスク
従業員が副業の遂行に際して違法行為を行ったり不用意な発言をしたりして、企業の信用が害される可能性もあります。企業側が副業を解禁するなら、従業員の情報発信方法についても確認しておきましょう。
企業が副業を解禁するなら、リスクを軽減するためのルールを取り決めておくと安心です。労務管理に関してお悩みがある方は、お気軽に弁護士までご相談ください。
【企業・顧問】有給休暇の時季変更権の運用方法
従業員から有給休暇取得の申請があったとき、企業側は拒絶できません。
ただし「時季変更権」を行使して有給の取得時期をずらすことは可能です。
時季変更権の行使方法によっては違法と判断された事例もあるので、正しい知識を持って対応しましょう。
この記事では有給休暇の時季変更権の行使や運用の方法について、判例も交えて解説します。
1.時季変更権とは
時季変更権とは、従業員による年次有給休暇の申請に対し、企業側が取得日の変更を求める権利です。
労働基準法第39条5項
請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる
有給休暇の取得は労働者の権利なので、会社側が断ることは許されません。ただ業務に著しい支障を生じる場合もあるので、取得日を変更する権利が企業側に認められているのです。
2.時季変更権が認められる条件
時季変更権が認められるのは「事業の正常な運営を妨げる場合」のみです。そういった危険がないのに、企業側の都合で従業員に対して有給取得時期をずらすよう求めると、違法とされる可能性があります。
時季変更権が認められやすいのは、以下のような場合です。
- 有給休暇の取得希望日が繁忙期と重なる場合
- 有給休暇の取得希望日が集合研修の予定日と重なる場合
- 長期に渡って連続する有給休暇の申請
ただし繁忙期なら必ず時季変更が認められるとは限らず、個別的な事情も考慮されて判断されます。
3.時季変更権が認められた場合の効果
会社側が適法に時季変更権を行使すると、有給休暇の取得時期がずらされます。従業員が出勤日に出社拒否したら「欠勤」扱いとして賃金を控除できますし、状況によっては懲戒処分も検討できます。
ただし従業員側が「賃金控除や懲戒処分は不当」と主張してトラブルになるケースもあるので、これらの処分を課すときには慎重になるべきです。
4.時季変更権に関する裁判例
4-1.繁忙期の時季変更が適法とされた裁判例
夏季の繁忙期に有給休暇の取得者が多数発生し、企業側が業務に対応できないために時季変更権を行使したケース(前橋地方裁判所高崎支部判決平成11年3月11日)。
4-2.譴責の懲戒処分が適法となった裁判例
集合研修期間に有給休暇の申請があったため会社が時季変更権を行使すると、従業員が欠席したので、企業側は欠勤控除を行って「譴責」の懲戒処分をしました。
裁判所は企業側の対応を適法と判断しました(東京高等裁判所判決平成13年11月28日)。
4-3.懲戒解雇を適法としたもの
記者が約1か月間にわたる長期の有給休暇を申請し、会社が時季変更権を行使すると出社しなかったケースです。企業側が従業員を懲戒解雇したところ、裁判所は懲戒解雇を有効と判断しました(東京高等裁判所平成11年7月19日判決)。
4-4.時季変更が違法とされた裁判例
従業員が繁忙期に短時間の有給休暇を申請したケース。裁判所は、期間が短く代替勤務者がいなくても業務に支障がでないと判断し、時季変更を認めませんでした(東京地方裁判所判決平成5年12月8日)。
繁忙期であっても、有給休暇取得によってどういった支障が出るのか明らかでない場合や代替勤務者を確保できる場合には、時季変更権が違法とされる可能性が高くなります。
5.時季変更権行使のタイミングと行使方法
時季変更権は、従業員から有給休暇取得の申請を受けた直後に行使すべきです。
たとえば2か月前に有給休暇を申請されたのに、予定日の1日前になって時季変更権を行使すると、違法とされる可能性が高いでしょう。申請を受けたら速やかに検討し、変更の必要があるなら従業員へ通知してください。
時期変更の通知を行う際には書面を作成し、理由をそえて別の日に有給休暇を取得するよう求めましょう。書面通知を送るだけではなく従業員と直接話し、十分に説明をして理解を求めることも重要です。
代替日については提案しても構いませんが、企業側が時季変更権の行使に際し代替日を提案する義務はありません。
当事務所では労務管理のアドバイスやサポートに力を入れています。千葉で労働問題に詳しい弁護士をお探しの事業者さまがおられましたらお気軽にご相談ください。
« Older Entries