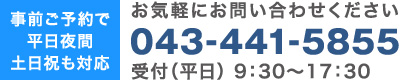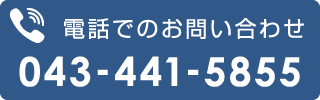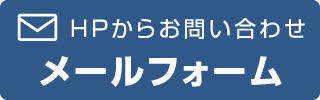Archive for the ‘千葉の弁護士コラム’ Category
【離婚男女】不倫、浮気の慰謝料請求で注意すべき「求償権」とは?
配偶者に不倫や浮気をされて慰謝料請求する際、「求償権」に注意しましょう。
求償権を軽視していると、せっかく相手から慰謝料を払ってもらってもその後配偶者に請求されて、慰謝料を取り戻されてしまうリスクが発生します。
今回は不倫や浮気の慰謝料請求の際に必須の知識となる「求償権」について、弁護士がわかりやすく解説します。
今後不倫相手に慰謝料請求したい方はぜひ参考にしてみてください。
1.求償権とは
求償権とは、連帯債務者や連帯保証人が支払いをしたとき、主債務者や他の債務者へ払いすぎた分の返還請求をする権利です。
わかりやすいように、連帯債務者の場合をみてみましょう。
連帯債務を負うと、すべての連帯債務者は債権の全額について支払いをしなければなりません。ただし当事者間では「負担部分」があります。自分の負担部分を超えて支払いをした場合には、他の連帯債務者へ払いすぎた分を請求できます。これが求償権です。
たとえばAさんとBさんが300万円の連帯債務を負っており、Aさんの負担部分が100万円、Bさんの負担部分が200万円としましょう。
このときAさんが債権者の要求で300万円払ったら、後にBさんに対して払いすぎた200万円を請求できます。
2.不倫慰謝料と求償権
実は不倫慰謝料も一種の「連帯債務」です。
不倫は配偶者と不倫相手が共同で行う不法行為なので、「共同不法行為」となります。
共同不法行為が成立すると、共同不法行為者は「不真正連帯債務」という連帯債務の関係になるのです。
そこで不倫した配偶者と不倫相手は、連帯して慰謝料を全額払わねばなりません。
不倫相手が慰謝料を全額払うと、自分の負担部分を超えた金額を配偶者へ求償できてしまいます。
不倫慰謝料の求償権を行使された具体例
たとえば夫が女性と不倫したとしましょう。妻が不倫相手に慰謝料請求して300万円の慰謝料を獲得します。しかし不倫相手の女性は後に夫へ求償権を行使して、200万円を取り戻すことができます。
そうなると、妻はせっかく300万円の慰謝料を獲得しても夫を通じて200万円を取り戻されてしまい、手元には100万円しか残らない結果となってしまいます。
そうなっては慰謝料請求の意義が半減するので、請求者としては求償権を封じる必要があるといえるでしょう。
3.求償権に注意すべきケース
浮気の慰謝料請求で特に求償権に注意しなければならないのは、「浮気されても配偶者と離婚しないケース」です。
離婚しない場合に求償権を行使されると、配偶者を通じて慰謝料を取り戻されてしまい、実質的に手元に残る慰謝料が減ってしまいます。
一方、配偶者と離婚するなら配偶者とは財布が別々になるのでさほど大きな影響は及びにくいでしょう。その場合でも、配偶者の手持ち資金が少なくなって慰謝料や財産分与を払ってもらいにくくなるリスクは発生します。
4.求償権トラブルを避ける方法
不倫相手に慰謝料請求をするとき、求償権トラブルを避ける方法は以下のとおりです。
示談締結時に求償権を放棄させる
もっとも確実なのは、示談締結時に相手に求償権を放棄させる方法です。
求償権を放棄したら、相手は後に配偶者へ支払った慰謝料を求償できません。
後に慰謝料を取り戻される心配がなくなります。
ただし求償権を放棄させるには、相手を説得しなければなりません。求償権放棄を合意する条件として、示談書にも求償権放棄の条項を入れましょう。
弁護士が代理人になっていれば、相手に強く求償権を放棄するよう説得できますし、示談書にも間違いなく求償権放棄の条項を入れることができます。後に慰謝料を取り戻されたくない場合、弁護士に慰謝料請求を依頼するとよいでしょう。
当事務所では男女トラブルの解決に力を入れて取り組んでいます。これから不倫相手に慰謝料請求する方、すでに自分で慰謝料請求を行って交渉中の方など、お気軽にご相談ください。

千葉県・東京23区を中心に活動する秋山慎太郎総合法律事務所です。
私たちは「身近な法律事務所」として、皆様の暮らしの安心を取り戻すお手伝いをしています。
当事務所は、相続、離婚、不動産、交通事故、債務整理、労働事件、刑事事件といった個人案件から、企業間の紛争、債権回収、労務管理等の法人案件、更には分野を特定できない法律問題まで幅広く取り扱う地域密着の総合法律事務所です。
特に、生活に直結する「借金・債務整理」や、突然のトラブルである「交通事故」の分野に力を入れており、豊富な解決実績がございます。法律の専門家として、ご相談者様一人ひとりに親身に寄り添い、迅速な解決を実現することをお約束します。
【借金・交通事故のご相談は初回30分無料】
お困りの際は、一人で悩まずに専門家にご相談ください。お電話やお問い合わせフォームから、まずはお気軽にご連絡いただければ幸いです。
【離婚男女】不倫の示談書の書き方をテンプレートつきで解説!
配偶者に不倫されたら、不倫相手に慰謝料を請求できます。話し合いの結果、慰謝料を払ってもらうことに決まったら「示談書」を作成しましょう。
とはいえ示談書をどうやって作成したらよいかわからない方も多いのではないでしょうか?
今回は不倫の示談書の書き方をテンプレート(書式)つきで解決しますので、ぜひ参考にしてみてください。
1.示談書とは
示談書とは、損害賠償金について当事者間で話し合って合意した内容をまとめた書面です。
いったん示談書に署名押印したら、当事者はその内容に拘束されます。
相手が約束を守らず慰謝料を支払わない場合、示談書があれば裁判を起こしたり相手の財産を差し押さえたりして取り立てることができます。
不倫されて相手から慰謝料を払ってもらう場合には、必ず示談書を作成する必要があるといえるでしょう。
ただし後にきちんと取り立てを行うため、示談書は正しい方法で作成しなければなりません。
2.不倫の示談書のテンプレート(書式、雛形)
不倫の示談書のテンプレートを示します(不倫相手のみに慰謝料請求するケース)。
|
示談書
○○○○(以下「甲」という)と○○○○(以下「乙」という)は、乙と甲の妻である○○○○(以下「丙」という)の不貞行為にもとづく甲に対する慰謝料について以下のとおり合意した。
第1条 乙は甲の妻である丙と不貞関係を結んだ事実を認め、甲に対して深く謝罪する。
第2条 乙は甲に対し、丙との不貞行為にもとづく慰謝料として、金○円の支払義務のあることを認める。
第3条 乙は前項の慰謝料を○年○月○日限り、以下の甲の指定する銀行口座に振り込む方法にて支払う。振込手数料は乙の負担とする。 ○○銀行 ○○支店 普通預金 口座番号○○○○○○○ 口座名義人 ○○○○
第4条 乙は第2条、第3条の慰謝料について乙と丙との共同不法行為における乙の負担部分であることを認め、丙に対する一切の求償権を放棄する。
第5条 乙が第2条、第3条の慰謝料の支払を遅延した場合、甲に対して年14.6%の割合にて遅延損害金を支払う。
第6条 乙は本示談書締結日以降、丙に対して一切接触しないことを約束する。乙がこれに反した場合には違約金として甲に対し100万円を支払う。
第7条 甲及び乙は、本件不貞行為や示談の内容について一切第三者に口外しない。
第8条 甲および乙は本示談書にさだめるほか、相互に債権債務のないことを確認する。
以上、本件示談の成立を証するため、本書を2通作成し、甲乙各自署名捺印のうえ各1通ずつ保有する。
○年○月○日 (住所) 甲:○○○○ 印 (住所) 乙:○○○○ 印 |
3.不倫の示談書の書き方、注意点
以下では不倫の示談書を作成するときの注意点をみていきましょう。
3-1.金額や支払期限、支払い方法
慰謝料の金額は間違いなく記載し、支払期限も設定しましょう。振り込みにする場合、銀行口座も正確に記載する必要があります。
3-2.求償権の放棄
不貞に基づく慰謝料は連帯債務となるため、不倫相手から慰謝料を受け取ると、不倫相手が配偶者へ「求償権」を行使して慰謝料を取り戻す可能性があります。
配偶者と婚姻関係を続ける場合には「求償権」を放棄させる必要があるでしょう(第4条)。
3-3.接触禁止条項、違約金の条項
配偶者との婚姻関係を継続するなら、不倫相手と二度と接触しないように接触禁止条項を入れましょう。
約束を破って接触した場合には違約金を支払う旨定めておくと効果的です(第6条)。
3-4.秘密保持条項
不倫トラブルを周囲に広められないため、お互いに秘密保持を約する条項を定めましょう(第7条)。
3-5.清算条項
示談後のトラブルを避けるため、本件以外にお互いに債権債務関係がないと確認する清算条項を入れましょう(第8条)。
3-6.公正証書にする
示談書ができたら、必ず公正証書にしましょう。公正証書を作成すると、相手が支払いをしないときにすぐに差押ができて便利だからです。
公正証書がなかったら、いったん裁判をしないと差押ができません。
まとめ
不倫された場合の示談書は、適切な方法で作成しないと後日のトラブルにつながってしまうおそれがあります。
相手方との示談交渉も弁護士が代行できますので、配偶者の不倫にお悩みの方がおられましたらお気軽に千葉の秋山慎太郎総合法律事務所までご相談ください。

千葉県・東京23区を中心に活動する秋山慎太郎総合法律事務所です。
私たちは「身近な法律事務所」として、皆様の暮らしの安心を取り戻すお手伝いをしています。
当事務所は、相続、離婚、不動産、交通事故、債務整理、労働事件、刑事事件といった個人案件から、企業間の紛争、債権回収、労務管理等の法人案件、更には分野を特定できない法律問題まで幅広く取り扱う地域密着の総合法律事務所です。
特に、生活に直結する「借金・債務整理」や、突然のトラブルである「交通事故」の分野に力を入れており、豊富な解決実績がございます。法律の専門家として、ご相談者様一人ひとりに親身に寄り添い、迅速な解決を実現することをお約束します。
【借金・交通事故のご相談は初回30分無料】
お困りの際は、一人で悩まずに専門家にご相談ください。お電話やお問い合わせフォームから、まずはお気軽にご連絡いただければ幸いです。
【離婚男女】離婚前に別居するとき、押さえておくべき知識を弁護士が解説
離婚協議や調停を進めるときには、別居されるご夫婦が数多くおられます。同居したままでは冷静に話を進めにくく、お互いにストレスが溜まったり子どもにも悪影響を与えてしまったりするためです。
ただし別居する際には生活費や証拠集めなど、事前に検討しておかねばならないポイントがいくつかあります。
今回は離婚前に別居する際、押さえておきたい重要ポイントを弁護士が解説しますので、ぜひ参考にしてみてください。
1.別居後の生活費について
夫婦が別居する際には、別居後の「生活費」について意識すべきと考えます。
たとえば専業主婦で今まで夫の収入に頼っていた方は、別居するとたちまち生活に困ってしまう可能性があるでしょう。「本当は別居したいけれど、別居したら生活できないから仕方なく我慢している」方もおられます。
しかしそういったケースでも相手に「婚姻費用」を請求できるので、心配しすぎる必要はありません。
1-1.婚姻費用とは
婚姻費用とは、夫婦が互いに負担しあうべき生活費です。法律上、夫婦にはお互いに扶養し合うべき「生活保持義務」が認められます(民法752条)。そして、夫婦は資産や収入などの状況に応じて、お互いに相手の生活費を負担しなければなりません(民法759条)。
こういった法律上の義務があるため、収入の少ない配偶者は多い方の配偶者へと生活費を請求できるのです。
1-2.婚姻費用の取り決め方
別居後、相手に婚姻費用を払ってもらうため、別居前に夫婦で話し合って婚姻費用の金額や支払い方法を決定しましょう。通常は月1回、定額を支払います。ボーナス時に増額してもかまいません。
金額については合意できればいくらにしてもかまいませんが、裁判所の定める基準の額があります。そこではお互いの年収や子どもの養育状況によっても金額が変わってきます。
迷ったときにはこちらの裁判所の婚姻費用算定表を参考にして金額を定めるとよいでしょう。
https://www.courts.go.jp/toukei_siryou/siryo/H30shihou_houkoku/index.html
2.別居前に集めておくべき証拠資料について
別居すると、夫婦がお互いに冷静になり離婚協議や調停を進めやすくなるメリットがあります。余計なストレスもかからなくなるでしょう。一方で、離婚を有利に進めるための「証拠集め」が困難になる可能性があるので、注意しなければなりません。
離婚の際には、さまざまな証拠が必要となります。
たとえば以下のようなものを集めなければ交渉や調停、訴訟で不利になるおそれがあるでしょう。
2-1.財産分与の資料
相手名義の預貯金、生命保険、社内積立、不動産や車などの資料です。
これらがなければ、財産分与の際に漏れが生じて受け取れる財産が減ってしまう可能性があります。
別居前にできるだけたくさんの資料を集めておきましょう。
コピーをとったりメモをとったりして、保存してください。
2-2.相手の収入資料
離婚の際、相手の収入も問題となる可能性があります。
たとえば婚姻費用を決めるときには相手の収入に関する情報が必要となりますし、給与明細書に書かれている社内積立や保険の引き落としによって夫婦共有財産を明らかにできるケースもあります。
相手の給与明細についてもコピーをとっておくとよいでしょう。
2-3.相手の不倫の証拠
相手が不倫していたら慰謝料を請求できますが、そのためには証拠が必要です。
写真や動画、メールやLINEのメッセージ、相手の日記やスケジュール帳の写しなど、入手できるものは確実に全て集めておいてください。
2-4.相手からDVやモラハラ被害を受けていた証拠
もしもDVやモラハラ被害を受けているなら、同居中にしか取得が難しい証拠があります。殴られたときのケガの写真、相手が怒鳴っているときの録音データ、詳細に状況を記した日記など、証拠をしっかりとっておきましょう。
当事務所では、これまで多数の離婚に悩む方からご相談をお受けし、解決に導いてまいりました。親身になってお話をお伺いしますので、お困りの方はお気軽にご相談ください。

千葉県・東京23区を中心に活動する秋山慎太郎総合法律事務所です。
私たちは「身近な法律事務所」として、皆様の暮らしの安心を取り戻すお手伝いをしています。
当事務所は、相続、離婚、不動産、交通事故、債務整理、労働事件、刑事事件といった個人案件から、企業間の紛争、債権回収、労務管理等の法人案件、更には分野を特定できない法律問題まで幅広く取り扱う地域密着の総合法律事務所です。
特に、生活に直結する「借金・債務整理」や、突然のトラブルである「交通事故」の分野に力を入れており、豊富な解決実績がございます。法律の専門家として、ご相談者様一人ひとりに親身に寄り添い、迅速な解決を実現することをお約束します。
【借金・交通事故のご相談は初回30分無料】
お困りの際は、一人で悩まずに専門家にご相談ください。お電話やお問い合わせフォームから、まずはお気軽にご連絡いただければ幸いです。
【離婚男女】不倫相手の名前、住所がわからないときの対処方法
配偶者に不倫されて慰謝料を払ってほしくても、不倫相手の「名前」や「住所」がわからなければ請求できません。
現実にはLINEなどで不倫が発覚しても、ニックネームが登録されていて不倫相手の素性が不明なケースも多く、注意が必要です。
今回は不倫相手の名前や住所がわからない場合の対処方法をお伝えしますので、配偶者に浮気されて悩まれている方はぜひ参考にしてみてください。
1.慰謝料請求には名前と請求書の送付先情報が必要
不倫相手に慰謝料請求するには、基本的に「相手の氏名」と「住所」の情報が必要です。
これらの情報がないと、相手に請求書を送れません。
「メールやLINEで請求できる」と思うかもしれませんが、メールやLINEは無視されるとそれ以上追求できなくなります。相手がメールアドレスを変えたりLINEを退会したりしたら、請求の手段がなくなってしまうでしょう。裁判を起こすときにも相手の名前と訴状の送達先情報が必要となります。
慰謝料請求する前に、必ず不倫相手の名前と住所を把握しておかねばなりません。
ただし不倫相手が配偶者の勤務先の上司や部下の場合など、「勤務先」がわかっていれば「住所」がわからなくても請求書の送付が可能です。
2.弁護士照会で調査できるケースがある
相手の名前や住所がわからなくても、電話番号などの情報があれば「弁護士照会」によって明らかにできる可能性があります。
弁護士照会とは、弁護士が法律の規定により、各種の機関へ情報照会できる制度です。
弁護士が慰謝料請求などの事案を受任すると、弁護士法23条によって必要な情報を調査する権限が認められます。
以下で不倫相手の氏名や住所を弁護士照会によって調べる方法を、パターン別にみていきましょう。
2-1.相手の電話番号がわかる場合
配偶者が相手の電話番号をニックネームで登録していると、不倫相手の名前がわかりません。こういった場合、相手の契約している電話会社に電話番号で照会すれば「契約者情報」の開示を受けられる可能性があります。
- 契約者の氏名
- 契約書の送付先
- 登録住所
こういった情報を取得できるので、内容証明郵便を送ったり訴訟を申し立てたりするのに役立ちます。
ただし電話会社によっては個人情報保護を理由に回答を拒否するため、必ず情報を得られるとは限りません。
2-2.メールアドレスがわかる場合
相手のメールアドレスがわかる場合には、プロバイダや通信会社に弁護士照会をかけて契約者情報を調べられる可能性があります。
ただし電話会社と同様、会社によっては個人情報保護を理由に開示を拒否するケースがあるので、確実ではありません。またGmailなど、外国企業が運営しているメールサービスの場合にも基本的には弁護士照会を利用できないと考えましょう。
2-3.LINEのIDがわかる場合
最近では、不倫相手とLINEでやり取りする方が多いので、相手のLINEのIDのみわかるケースもあります。
IDがわかれば「LINE株式会社」へ弁護士照会をかけて、LINEに登録している電話番号を調べられます。それがわかったら、さらに判明した電話会社へ照会を行って相手の契約者情報を取得できる可能性があります。
3.何の情報もない場合
配偶者が「不倫している」事実だけがわかっていて電話番号など何の手がかりもない場合には、弁護士照会を利用できません。
その場合、尾行調査によって明らかにするしかないでしょう。ただし自分であとをつけると見つかってトラブルになる可能性があります。写真や動画を撮影するのも難しくなるでしょう。より確実に調査を成功させるには、探偵事務所や興信所に依頼してみてください。
まとめ
不倫相手の氏名や住所がわからなくても慰謝料請求をあきらめる必要はありません。
困ったときには証拠の集め方をご説明しますので、お早めに弁護士までご相談ください。

千葉県・東京23区を中心に活動する秋山慎太郎総合法律事務所です。
私たちは「身近な法律事務所」として、皆様の暮らしの安心を取り戻すお手伝いをしています。
当事務所は、相続、離婚、不動産、交通事故、債務整理、労働事件、刑事事件といった個人案件から、企業間の紛争、債権回収、労務管理等の法人案件、更には分野を特定できない法律問題まで幅広く取り扱う地域密着の総合法律事務所です。
特に、生活に直結する「借金・債務整理」や、突然のトラブルである「交通事故」の分野に力を入れており、豊富な解決実績がございます。法律の専門家として、ご相談者様一人ひとりに親身に寄り添い、迅速な解決を実現することをお約束します。
【借金・交通事故のご相談は初回30分無料】
お困りの際は、一人で悩まずに専門家にご相談ください。お電話やお問い合わせフォームから、まずはお気軽にご連絡いただければ幸いです。
【離婚男女】不倫慰謝料の証拠収集方法と注意点
不倫相手に慰謝料請求するには、「不倫の証拠」が必要です。
証拠がないのに慰謝料請求しても「不倫していない」とごまかされてしまうでしょう。
慰謝料を払ってもらえないだけではなく「思い込み」「被害妄想」「名誉毀損」などと言われてしまう可能性もあります。
こういったリスクを防ぐには、事前に肉体関係を証明できる資料を集めてから慰謝料請求を開始すべきです。
今回は不倫慰謝料の証拠収集方法やその際の注意点をお知らせします。
配偶者に不倫されてお困りの方はぜひ参考にしてみてください。
1.不倫の証拠は「肉体関係」を証明するものが有効
不倫の証拠を集めるときには、できるだけ「肉体関係」を直接示すものを探しましょう。
法律上、不倫を「不貞」といいます。不貞とは「既婚者が配偶者以外の異性と肉体関係をもつこと」であり、不貞には強い違法性が認められています。不貞を証明できれば、裁判で離婚請求もできます。
一方、肉体関係のない交際は「不貞」になりません。違法性が認められないか、認められるとしても非常に弱くなってしまいます。慰謝料も請求できない可能性が高くなりますし、認められるとしても低額になるでしょう。
そこで不倫の証拠としては「肉体関係を証明できるか」がポイントになってくるのです。
2.不倫を証明できる強い証拠と弱い証拠
以下で不倫を証明する証拠として強い証明力のあるものと証明力が弱いものを分類してご紹介します。
2-1.証明力の高い証拠
- 肉体関係をもっていることがわかるメール、メッセージのやり取り
- 性交渉の最中に撮影した動画や写真
- 避妊具など
- 肉体関係を認める自認書
- 一緒に旅行に行ったことがわかるメールや航空券の予約データ、旅館の領収証など
- ホテルの領収証、利用記録
- ホテルに行ったり相手の家に泊まったりしたことがわかる日記やスケジュール帳
- 探偵の調査報告書
こういったものは直接肉体関係を示すので、証明力の高い証拠といえます。
2-2.証明力の低い証拠
- 肉体関係を直接示さない親しげなメール、メッセージのやり取り
- 親密な手紙、メッセージカードなど
- 不倫相手からのプレゼント
- デートの際に利用したお店や買い物の領収証、クレジットカードの明細書
- 電話の通話記録
- 交通ICカードやETCカードの利用履歴
上記のようなものは直接肉体関係を示しませんが、積み重ねると不倫を強く推察させる資料になりえます。
3.不倫の証拠集めのポイント、注意点
不倫の証拠集めをするときには、以下のような点に注意しましょう。
3-1.多くの証拠を集める
まずはできるだけたくさんの証拠を集めることが重要です。
証明力が高いものはもちろん、肉体関係を直接証明できなくても多くの資料をそろえましょう。
最終的に肉体関係を証明できなくても、証拠の積み重ねによって「常識的な範疇を超えた親密な交際関係」を証明できれば、一定額の慰謝料が認められる可能性があります。
3-2.相手に気づかれる前に証拠を集める
配偶者に「不倫しているでしょう?」などと言ってしまったら、相手は警戒してしばらく会うのを控えたり、メールなどの証拠を破棄したりする可能性が高くなります。
相手には不倫に気づいていないフリをしながら証拠を集めていきましょう。
慰謝料請求などの具体的なアクションは、証拠が揃った後に起こすべきです。
3-3.違法行為に要注意
不倫の証拠集めをするとき、知らず知らずに違法行為をしてしまうケースがあるので注意が必要です。
たとえば不正なアプリを相手のスマホに入れて行動調査をすると、「ウイルス供用罪」という犯罪が成立してしまう可能性があります。尾行調査に熱を入れすぎて住居侵入罪や道路交通法違反になってしまうケースもあります。
3-4.トラブルになる可能性
探偵事務所に尾行調査を依頼すると費用がかかるので、自分や友人、親戚などに依頼して尾行調査する方がおられます。
しかし自力で配偶者や不倫相手を尾行すると、相手と鉢合わせしてトラブルになってしまうケースも少なくありません。素人が尾行すると、せっかく不倫のシーンを確認できても有効な写真や動画などを撮影できない場合が多数です。行動調査をするのであれば、探偵事務所に任せた方がよいでしょう。
不倫の証拠集めに困ったときには、弁護士がご相談に応じます。お気軽にお問い合わせください。

千葉県・東京23区を中心に活動する秋山慎太郎総合法律事務所です。
私たちは「身近な法律事務所」として、皆様の暮らしの安心を取り戻すお手伝いをしています。
当事務所は、相続、離婚、不動産、交通事故、債務整理、労働事件、刑事事件といった個人案件から、企業間の紛争、債権回収、労務管理等の法人案件、更には分野を特定できない法律問題まで幅広く取り扱う地域密着の総合法律事務所です。
特に、生活に直結する「借金・債務整理」や、突然のトラブルである「交通事故」の分野に力を入れており、豊富な解決実績がございます。法律の専門家として、ご相談者様一人ひとりに親身に寄り添い、迅速な解決を実現することをお約束します。
【借金・交通事故のご相談は初回30分無料】
お困りの際は、一人で悩まずに専門家にご相談ください。お電話やお問い合わせフォームから、まずはお気軽にご連絡いただければ幸いです。
【離婚男女】財産分与で相手の資産を調査する方法
離婚の際、「財産分与」は極めて重要です。
婚姻中に仕事をしていなかった方の場合、離婚後しばらく分与された財産を使って生活を維持しなければならないでしょう。そうでない方であっても手持ち財産が多ければ心の安定につながります。
財産分与で損をしないためには、相手による財産隠しを防がねばなりません。
今回は財産分与の話し合いの際に相手が財産を隠すときの調査方法について、弁護士が解説します。
1.財産分与では「財産開示」が非常に重要!
財産分与とは、婚姻中に夫婦が積み立てた共有財産を離婚時に分け合う手続きです。
婚姻中、夫婦が協力して積み立てた財産の一部は共有となります。しかし離婚したら共有状態を解消し、それぞれの取り分に分ける必要があるでしょう。
そこで離婚時に共有財産の清算を行います。それが「離婚時財産分与」です。
以下のような資産が財産分与の対象になります。
- 預貯金
- 不動産
- 車
- 生命保険、学資保険
- 積立金
- 退職金
- 金や仮想通貨
- その他の価値のある動産類
財産分与の際には、夫婦がお互いに手持ちの資産を開示しなければなりません。
このとき、相手に財産を隠されると大きな不利益が及ぶ可能性があるので注意しましょう。隠し財産に気づかなければ、その資産は「ないもの」として財産分与額が計算されてしまうためです。
そうなったら、本来受けられるはずの財産分与を受けられなくなり、払ってもらえる財産が目減りしてしまいます。
そのような不利益を受けないため、相手の財産状況を調べる必要があります。
2.財産を隠されたときの対処方法
相手の財産隠しを防ぐには、以下のような手順で財産調査を進めましょう。
2-1.自分で探す
自力で相手の財産を調べたい場合、相手に勘づかれると隠される可能性があります。
財産分与の話を始める前に資料を集めましょう。
- 自宅に保管されている資料を探す(預貯金通帳、生命保険証書、証券会社からのお知らせ、不動産売買契約書、権利証、車検証など)
- 相手のスマホやPCをチェックする(ネット銀行やネット証券、仮想通貨などの取引状況がわかる可能性があります)
- 郵便物をチェックする(生命保険会社、銀行、証券会社、役所などからさまざまな連絡書や納付用紙などが届きます)。
- 通帳や証券、契約書や権利証などが見つかったらコピーやメモをとり、表を作成する
2-2.弁護士に照会を依頼する
自力で探すのに限界を感じたら、弁護士に相談してみてください。
弁護士は「弁護士法23条」という法律にもとづいて、各種機関へ情報照会する権限を有しています。
弁護士に協議離婚の代理などを任せると、弁護士が23条照会によって証券会社、生命保険会社、相手の勤務先などへ照会をかけて資産状況を調べられる可能性があります。
2-3.裁判所で職権調査嘱託をしてもらう
弁護士照会によっても回答を得られないときには、裁判所から調査してもらう方法が有効です。裁判所からの調査を「職権調査嘱託」といいます。
調停や訴訟になると、申立をすれば裁判所が必要に応じて金融機関や保険会社などへ「職権調査嘱託」をしてくれる可能性があります。裁判所から調査嘱託がきたら、たいていの機関は回答するので相手の財産状況を調べやすくなります。
また裁判所が提出を促すことにより、相手が任意に財産資料を提出するケースも少なくありません。
3.財産資料の収集は弁護士へご相談を
自力で相手の財産を調べきるのは簡単ではありません。きっちり調査するには弁護士照会や裁判所の利用が必要となるでしょう。
また相手に寄る使い込みや財産の処分を防止するには、気づかれる前に財産調査すべきです。スピーディかつ確実に財産を調べるには、弁護士による支援が必要となるでしょう。当事務所では離婚案件に力を入れておりますので、財産分与で不利益を受けないためにもお早めにご相談ください。

千葉県・東京23区を中心に活動する秋山慎太郎総合法律事務所です。
私たちは「身近な法律事務所」として、皆様の暮らしの安心を取り戻すお手伝いをしています。
当事務所は、相続、離婚、不動産、交通事故、債務整理、労働事件、刑事事件といった個人案件から、企業間の紛争、債権回収、労務管理等の法人案件、更には分野を特定できない法律問題まで幅広く取り扱う地域密着の総合法律事務所です。
特に、生活に直結する「借金・債務整理」や、突然のトラブルである「交通事故」の分野に力を入れており、豊富な解決実績がございます。法律の専門家として、ご相談者様一人ひとりに親身に寄り添い、迅速な解決を実現することをお約束します。
【借金・交通事故のご相談は初回30分無料】
お困りの際は、一人で悩まずに専門家にご相談ください。お電話やお問い合わせフォームから、まずはお気軽にご連絡いただければ幸いです。
【相続】代襲相続について
相続人の中に「被相続人より先に亡くなっていた人」がいたら、「代襲相続」が発生する可能性があります。
代襲相続人がいる場合、次順位の相続人に相続権が移りません。遺産分割協議の際には代襲相続人を入れて話し合う必要があります。
今回は代襲相続がどういったケースで発生するのか、代襲相続人の法定相続割合も含めて解説します。
1.代襲相続とは
代襲相続とは、相続人が被相続人より先に死亡したなどの事情によって相続できないときに、相続人の子どもが代わって相続することです。
たとえば父親が死亡したとき、長男が先に死亡していたら長男の子どもである「孫」が代襲相続人となります。
このように代襲相続する人(上記の例では孫)を「代襲相続人」、代襲相続される人(上記の例では長男)を「被代襲者」といいます。
代襲相続が起こる場合、相続権は次順位の相続人へ移りません。たとえば父親が死亡したときに長男が先に死亡していて孫が代襲相続するならば、父親の「親(第2順位の相続人)」や「兄弟姉妹(第3順位の相続人)」は相続人になりません。
また代襲相続が発生するのは、相続人が子どもや兄弟姉妹の場合です。親が先に死亡していた場合には代襲相続は起こりません。
2.代襲相続の範囲
代襲相続の範囲は、相続人の種類によって異なります。
2-1.子どもが被代襲者になる場合
子どもが親より先に死亡していれば、孫が代襲相続人になります。
孫も先に死亡していれば、孫の子どもであるひ孫が「再代襲相続人」として相続人になります。
このように、直系卑属の場合には、延々と代襲相続が続いていきます。「何代限り」などの制限はありません。
2-2.兄弟姉妹が被代襲者になる場合
兄弟姉妹が相続人になる場合、代襲相続に制限がかかります。
兄弟姉妹などの血族を「傍系」といいますが、傍系は直系ほど血が濃くないからです。
傍系の再代襲相続を認めると、被相続人とほとんど無関係な人に財産が引き継がれてしまい、不合理な結果となるでしょう。そこで兄弟姉妹の子どもが代襲相続できるのは「一代限り」とされています。
兄弟姉妹が被相続人より先に死亡していれば甥や姪が代襲相続できますが、甥や姪も先に死亡している場合にはその子どもは相続できません。
3.相続欠格、相続廃除と代襲相続
代襲相続が起こるのは、相続人が被相続人より先に死亡していた場合だけではありません。
相続欠格者となった場合や相続廃除された場合にも代襲相続が発生します。
3-1.相続欠格者とは
相続欠格者とは、法律上当然に相続権を失った人です。被相続人を殺したり遺言書を偽造、変造したり破棄したり、被相続人を脅迫して遺言書を書かせたり書き直させたりした場合などに相続欠格者となります。
もともとの相続人が相続欠格者となった場合、その子どもが代襲相続人になります。
3-2.相続廃除とは
相続廃除とは、非行のある相続人に対し、被相続人が自ら相続権を奪うことです。
たとえば被相続人を虐待したり著しい迷惑をかけたりした相続人がいたら、被相続人は家庭裁判所へ申し立てることによって相続廃除できます。
もともとの相続人が廃除されると、その子どもが代襲相続人になります。
4.相続放棄と代襲相続
相続人が相続放棄しても、代襲相続は発生しません。
相続放棄すると、本人は「当初から相続人ではなかった」扱いになるからです。
たとえば親の借金の相続を避けるために相続放棄した場合、放棄者の子ども(孫)に借金が引き継がれてしまう心配は要りません。
5.代襲相続人の相続分
代襲相続人の相続分は、被代襲者のものと同じです。たとえば被代襲者が子どもで孫が代襲相続する場合、子どもの法定相続分が3分の1なら孫の相続分も3分の1。孫が2人いたら、それぞれの相続分は6分の1ずつになります。遺留分も同じように引き継がれます。
相続のお悩みは弁護士へご相談を
代襲相続が発生すると、相続人調査が非常に複雑になり相続人の確定に手間がかかるケースも少なくありません。代襲相続人と他の相続人が疎遠で遺産分割協議を進めにくい事案もよくあります。遺産相続でお困りの際には、お気軽に弁護士までご相談ください。

千葉県・東京23区を中心に活動する秋山慎太郎総合法律事務所です。
私たちは「身近な法律事務所」として、皆様の暮らしの安心を取り戻すお手伝いをしています。
当事務所は、相続、離婚、不動産、交通事故、債務整理、労働事件、刑事事件といった個人案件から、企業間の紛争、債権回収、労務管理等の法人案件、更には分野を特定できない法律問題まで幅広く取り扱う地域密着の総合法律事務所です。
特に、生活に直結する「借金・債務整理」や、突然のトラブルである「交通事故」の分野に力を入れており、豊富な解決実績がございます。法律の専門家として、ご相談者様一人ひとりに親身に寄り添い、迅速な解決を実現することをお約束します。
【借金・交通事故のご相談は初回30分無料】
お困りの際は、一人で悩まずに専門家にご相談ください。お電話やお問い合わせフォームから、まずはお気軽にご連絡いただければ幸いです。
【離婚男女】離婚の流れを詳しく解説!~離婚を決意した方へ~
「離婚したい!」と思っても、何から始めて良いかわからない方がたくさんおられます。
まずは離婚の流れを把握しておきましょう。
今回は協議離婚の進め方や注意点を弁護士が解説しますので、離婚にお悩みの方はぜひ、参考にしてみてください。
1.協議離婚の流れ
離婚したいときには、まずは「協議離婚」を目指しましょう。
協議離婚とは、夫婦が合意して離婚届を提出することによって成立させる離婚の方法です。
日本で離婚する夫婦の9割は協議離婚しており、「離婚の原則的な方法」といえます。
以下でその流れや対処方法をみていきましょう。
1-1.準備をする
離婚したいときには、まずは準備が必要です。
- 財産分与の準備
預貯金通帳や保険証書、自宅不動産に関する書類、相手の給与明細書など、財産分与に関する資料を集めましょう。
- 慰謝料請求の準備
相手が不倫しているので慰謝料請求したい場合などには、不倫の証拠を先に集めておく必要があります。
- 別居の準備
離婚前に別居する場合には、転居先の確保や引っ越し代等のお金など、別居の準備もしましょう。
- 親権を獲得するための準備
子どもの親権を獲得したい場合、親権者になるための環境整備や計画も必要です。
- 離婚条件の検討
自分がどのような条件で離婚したいのか、希望する条件を考えておきましょう。
財産分与をどのくらい受け取りたいのか、慰謝料を払ってほしいのか、親権や養育費、年金分割についての希望などを紙やデータにまとめておくようお勧めします。
1-2.相手に切り出す
離婚の準備が整ったら相手に切り出しましょう。
お互いに冷静になってゆっくり話し合えるように、休日の時間があるタイミングなどを見計らって話をするようお勧めします。
1-3.離婚条件を決める
話し合いにより、離婚条件を決めていきましょう。
主に決めるべき事項は以下のようなポイントです。
事前に検討していた離婚条件を相手に提示し、相手の返答を聞いてお互いの妥協点を探っていきましょう。
- 財産分与
- 慰謝料
- 親権
- 養育費
- 年金分割
- 離婚後の子どもとの面会交流
1-4.別居する
相手が離婚に応じない場合や離婚協議がストレスとなって同居が苦痛になる場合などには、別居も検討しましょう。
相手が離婚を拒絶する場合でも、別居すると相手が諦めて離婚に応じるケースが少なくありません。お互いが冷静になって話しやすくなるメリットもあります。
専業主婦の方など、相手の収入に頼って生活してきた方は別居すると相手に「婚姻費用」という生活費を請求できます。「別居したら生活できなくなる」という心配は不要ですので、相手と喧嘩が絶えないなど精神的に厳しくなってきたら弁護士に相談してみてください。
1-5.離婚公正証書を作成する
相手と話し合って離婚条件に合意できたら、離婚公正証書を作成しましょう。
公正証書にすると、単なる当事者間の合意書よりも強い法的効力が与えられます。
たとえば支払義務者が養育費などの支払いを怠ると、すぐに強制執行ができて回収しやすくなります。原本が公証役場で保管されるので、紛失や書き換えなどのおそれもありません。
公正証書を作成したいときにはお近くの公証役場へ申込みをしましょう。なお離婚公正証書を作成するには費用がかかり、相手の承諾も必要です。
1-6.離婚届を提出する
離婚公正証書が完成したら、離婚届を作成して役所へ提出しましょう。
離婚届には、夫婦がそれぞれ署名押印する必要があります。また右側に2名分の「証人」の署名押印欄もあるので、誰かに証人を依頼しなければなりません。
一般的にはお互いの親族1名ずつに証人になってもらうケースが多数となっていますが、まったくの他人に依頼してもかまいません。
2.合意できない場合には調停離婚を
相手と話し合っても合意できない場合には、家庭裁判所で離婚調停を申し立てましょう。
調停では、裁判所の調停委員会が間に入って夫婦の意見を調整してくれます。
調停で合意ができたら裁判所から「調停調書」が送られてくるので、それを役所へ持参すれば離婚届を受け付けてもらえます。
離婚を進めるときには、準備や相手との交渉などさまざまな事項に対応しなければなりません。有利な条件で合意するには弁護士によるサポートが必要です。これから離婚したい方、すでに協議を開始されている方など、お気軽に弁護士までご相談ください。

千葉県・東京23区を中心に活動する秋山慎太郎総合法律事務所です。
私たちは「身近な法律事務所」として、皆様の暮らしの安心を取り戻すお手伝いをしています。
当事務所は、相続、離婚、不動産、交通事故、債務整理、労働事件、刑事事件といった個人案件から、企業間の紛争、債権回収、労務管理等の法人案件、更には分野を特定できない法律問題まで幅広く取り扱う地域密着の総合法律事務所です。
特に、生活に直結する「借金・債務整理」や、突然のトラブルである「交通事故」の分野に力を入れており、豊富な解決実績がございます。法律の専門家として、ご相談者様一人ひとりに親身に寄り添い、迅速な解決を実現することをお約束します。
【借金・交通事故のご相談は初回30分無料】
お困りの際は、一人で悩まずに専門家にご相談ください。お電話やお問い合わせフォームから、まずはお気軽にご連絡いただければ幸いです。
【離婚男女】養育費の取り決め方法は公正証書で!金額の相場についても解説
離婚するときに未成年のお子様を引き取るなら、必ず相手との間で養育費の取り決めをしましょう。
日本では離婚後に養育費が払われないケースが非常に多いことが知られています。ただ適切な方法で取り決めをしてさえいれば、払われる可能性が大きく高まるのです。
今回は養育費の相場や不払いを防ぐための公正証書による取り決め方法を解説しますので、不払いが心配な方はぜひ参考にしてみてください。
1.養育費が支払われる割合は4分の1程度
日本では、離婚後に養育費が払われる割合が非常に低くなっています。
厚生労働省が5年ごとに発表している「全国ひとり親世帯等調査結果報告」によると、平成28年に母子家庭で養育費を受け取っている世帯はわずか24.3%。5年前の平成23年には19.7%だったので増加はしていますが、まだまだ全体の4分の1にもなりません。
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11920000-Kodomokateikyoku/0000188168.pdf
何の対策もしていなければ、離婚後に養育費を払ってもらうのは難しい状況ともいえるでしょう。
養育費を払ってもらうには、必ず離婚時に相手との間で「養育費支払についての約束」をしなければなりません。金額や支払方法、支払時期などを確認して合意書を作成しましょう。
2.養育費の金額や相場
「養育費をいくらにすればよいのか?」と悩まれる方も多いので相場の金額を説明します。
裁判所の考え方によると、養育費の金額は基本的に以下の要素によって決まります。
- 両親それぞれの年収
支払う側の年収が高ければ養育費は高額になります。支払われる側の年収が高いと養育費の金額は下がります。
- 子どもの年齢
子どもの年齢が14歳未満の場合、比較的低額です。15歳以上になると生活費がかかるようになるので養育費が増額されます。
- 子どもの人数
子どもの人数が多いとその分生活費がかさむので養育費の金額が上がります。
実際には養育費の金額について複雑な計算式がありますが、個別の事案でいちいち難しい計算をするのは大変です。そこで裁判所では親の収入や子どもの年齢、人数に応じておよその相場を明らかにし、以下の算定表にまとめています。
ご夫婦で話し合って養育費を決めるときにも、こちらを参照してみてください。
https://www.courts.go.jp/toukei_siryou/siryo/H30shihou_houkoku/index.html
なお裁判所の算定表の金額は令和元年12月に改定され、金額が全体的に増額されています。それ以前に約束した方の場合、新しい算定表によって養育費を増額できる可能性もあるので、一度確かめてみましょう。
3.養育費は必ず公正証書で取り決める
離婚時に養育費の約束をするとき、自分たちで作成して署名押印しただけの合意書では強い効果が認められません。約束を破られたとき、あらためて養育費調停を申し立てなければ差し押さえなどの対応は難しくなります。
そうなると時間もかかりますし、その間に相手に逃げられる可能性もあるでしょう。
そこで、養育費の約束をするなら必ず「公正証書」を作成するようお勧めします。
公正証書があれば、相手が不払いを起こしたときに公正証書を使ってすぐに給料や預貯金、保険などを差し押さえられます。
調停を申し立てる手間を省けますし、相手が財産隠しをする余裕も与えずに済むでしょう。
4.公正証書の作成方法
公正証書を作成する際には、お近くの公証役場に申込みをする必要があります。
夫婦で合意した内容を伝えて、公正証書の作成を依頼しましょう。
公証人と日程を調整し、必要書類を当日持参すればその場で公正証書を作成してもらえます。
公正証書の作成日には基本的に夫婦の双方が出頭しなければなりません。どうしても本人が出頭できない場合、代理人への依頼も可能です。
弁護士が公正証書作成の手続を代行することもできるので、ご自身で対応するのが難しい場合にはお気軽にご相談ください。
当事務所では離婚を考えている方へ積極的に支援させていただいています。親権や養育費、面会交流など子どもの問題や財産分与などでお悩みを抱えた方がいらっしゃいましたら、お気軽にご相談ください。

千葉県・東京23区を中心に活動する秋山慎太郎総合法律事務所です。
私たちは「身近な法律事務所」として、皆様の暮らしの安心を取り戻すお手伝いをしています。
当事務所は、相続、離婚、不動産、交通事故、債務整理、労働事件、刑事事件といった個人案件から、企業間の紛争、債権回収、労務管理等の法人案件、更には分野を特定できない法律問題まで幅広く取り扱う地域密着の総合法律事務所です。
特に、生活に直結する「借金・債務整理」や、突然のトラブルである「交通事故」の分野に力を入れており、豊富な解決実績がございます。法律の専門家として、ご相談者様一人ひとりに親身に寄り添い、迅速な解決を実現することをお約束します。
【借金・交通事故のご相談は初回30分無料】
お困りの際は、一人で悩まずに専門家にご相談ください。お電話やお問い合わせフォームから、まずはお気軽にご連絡いただければ幸いです。
【離婚男女】不倫慰謝料の相場や高額になりやすいケースについて
夫や妻に不倫されたら、慰謝料を請求したいと考えるのも当然です。
ただ「どのくらいの慰謝料を請求すればよいのだろう?」と迷われる方が少なくありません。
今回は不倫慰謝料の法的な相場や高額な慰謝料を請求するためのポイントを解説します。
これから慰謝料請求を進めたいと考えている方はぜひ、参考にしてみてください。
1.不倫慰謝料の一般的な相場
配偶者に不倫されたら、法律上の離婚原因になりますし慰謝料も請求できます。
1-1.不貞慰謝料を請求するための条件
ただし裁判で離婚原因として認められるには「配偶者と不倫相手の肉体関係」を立証しなければなりません。このように「配偶者のある人が別の異性と肉体関係をもつこと」を法律的に「不貞」といいます。
肉体関係のない「プラトニックな関係」では離婚原因にならず慰謝料も請求しにくいので、慰謝料請求するならまずは男女の性関係を証明できる証拠を集めましょう。
1-2.不貞慰謝料の相場
裁判で認められる不貞の慰謝料相場は以下のとおりです。
50~300万円
このように随分と幅があります。どういったケースで慰謝料が高額になるのか、みていきましょう。
2.不倫慰謝料が高額になりやすい条件
2-1.婚姻期間が長い
不倫の慰謝料は、夫婦の婚姻年数に比例して高額になる傾向があります。
一般的に婚姻期間が1~3年程度の場合、慰謝料の金額は100~150万円程度。
一方で婚姻期間が10年以上になると300万円以上になるケースも少なくありません。
婚姻年数が3~10年までの間であれば、だいたい150~300万円の範囲内で慰謝料が決定される事例が多数です。
2-2.夫婦関係が破綻した
不倫によって慰謝料が発生するのは、被害者が大きな精神的苦痛を受けるからです。一方で不倫されても夫婦関係が破綻せず修復可能であれば、被害者の精神的苦痛はあまり大きいとはいえないでしょう。慰謝料が低額になります。
婚姻関係が破綻したら慰謝料額は100万円~300万円程度になりますが、夫婦関係を修復した場合には慰謝料は50~100万円程度になると考えましょう。
2-3.その他慰謝料が高額になりやすい要素
以下のような要素があると、不倫慰謝料は高額になりやすい傾向があります。
- 不倫関係が長い、不倫が行われた回数が多い
- 不倫によって夫婦生活に大きな悪影響を与えた
- 不倫した当事者が家出した、生活費を払わなくなった
- 夫婦に未成年の子どもがいる、子どもの人数が多い
- 不倫相手や不倫した妻が妊娠した
- 不倫相手が積極的に夫婦関係を破綻させるための嫌がらせをした
- 不倫が発覚した後の態度が不誠実
なお法律上「不貞」といえるには「配偶者と不倫相手の肉体関係」が必要ですが、肉体関係を立証できなくても低額な慰謝料が発生する可能性があります。それは、社会通念の常識を超えるような不適切な交際関係により、平穏な夫婦関係を侵害したといえる場合。
常識的な限度を超えて配偶者のある人と恋愛関係となり親密なやり取りをしていた場合などには、50万円程度の慰謝料が認められた裁判例がいくつもあります。
肉体関係を立証できなくても、必ずしも慰謝料請求をあきらめる必要はありません。
3.なるべく高額な慰謝料を請求するためのポイント
なるべく高額な慰謝料を支払わせるには、以下のような点に注意しましょう。
3-1.確実な肉体関係の証拠を集める
まずは不倫(肉体関係)の確実な証拠を集めましょう。証拠がなかったら、相手にしらを切られてしまい支払を受けられないリスクが大きく高まります。
相手に慰謝料請求通知を送る前に綿密に証拠集めをしましょう。
3-2.話し合いで解決する
裁判になると裁判費用もかかりますし、慰謝料額は法的な相場に限定されます。
相手に支払い能力があるなら、話し合いで解決した方が高額な慰謝料を払ってもらいやすい可能性があります。
たとえば相手が納得するなら慰謝料を500万円やそれ以上に設定しても違法ではありません。
状況にもよりますが、上手に交渉すればより高額な慰謝料を獲得しやすくなります。
3-3.弁護士に依頼する
不倫の慰謝料請求は弁護士に依頼しましょう。弁護士であれば的確に証拠を集められますし、相手との交渉も有利に進められるものです。合意ができたら公正証書を作成し、確実に支払を受けられるための対策もできます。
当事務所では離婚や男女問題の解決に積極的に取り組んでいます。配偶者の不倫や浮気にお悩みの方がおられましたら、お気軽にご相談ください。

千葉県・東京23区を中心に活動する秋山慎太郎総合法律事務所です。
私たちは「身近な法律事務所」として、皆様の暮らしの安心を取り戻すお手伝いをしています。
当事務所は、相続、離婚、不動産、交通事故、債務整理、労働事件、刑事事件といった個人案件から、企業間の紛争、債権回収、労務管理等の法人案件、更には分野を特定できない法律問題まで幅広く取り扱う地域密着の総合法律事務所です。
特に、生活に直結する「借金・債務整理」や、突然のトラブルである「交通事故」の分野に力を入れており、豊富な解決実績がございます。法律の専門家として、ご相談者様一人ひとりに親身に寄り添い、迅速な解決を実現することをお約束します。
【借金・交通事故のご相談は初回30分無料】
お困りの際は、一人で悩まずに専門家にご相談ください。お電話やお問い合わせフォームから、まずはお気軽にご連絡いただければ幸いです。